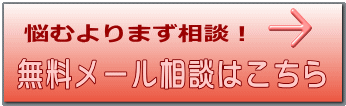関節の構造と機能(不動性関節、可動性の関節など)
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
関節の構造と機能
人体には206個の骨がありますが、2つ以上の骨を連結する構造体と関節といいます。
関節は主に、関節腔を持たない不動性の関節と、関節腔を持つ可動性の関節に大別されます。
1.不動性の関節
可動性が全くないか、ごくわずかしかない関節のことをいい、骨を連結する組織の種類によって以下の3つに分類されます。
①線維性結合
骨が線維性の総合組織で結合されているもの。頭蓋骨の縫合や遠位脛腓骨などがあります。
②軟骨結合
骨が線維軟骨や硝子軟骨で結合されているもの。椎間板や恥骨結合、肋軟骨などがあります。
③骨結合
発生期の個別の骨が結合して単一の骨になったもの。寛骨(腸骨+恥骨+坐骨)や仙骨(5個の仙椎)などがあります。
2.可動性の関節
可動性を持つ関節のことで、通常は関節といえばこのことをいい、四肢の関節の大多数が可動性の関節です。
相対する骨の端は硝子軟骨である関節軟骨で覆われ、関節包という線維性の袋に包まれています。関節包の内部は関節腔とよばれ、滑液が存在しています。
関節包は内外二層構造になっており、内層は血管が富む特殊な結合組織の膜で、滑液を分泌することから滑膜とよばれています。外層は繊維膜とよばれる密な結合組織からなる丈夫な膜で、関節を挟む両骨の骨膜に付着しています。
一部の関節では、関節を補助するために靭帯、関節唇、関節半月、関節円板などが存在します。
3.肩関節(けんかんせつ)の構造と機能
肩関節は、狭義には上腕骨と肩甲骨との間の関節を指しますが、実際の運動の際には肩甲帯の複数の関節が連動して動いています。
肩甲帯には肩甲上腕関節、肩鎖関節、胸鎖関節という三つの解剖学的関節と、肩峰下関節、肩甲胸郭関節という二つの機能的関節が含まれ、これらの関節を構成する骨は鎖骨、肩甲骨、上腕骨です。
4.肘関節(ちゅうかんせつ)の構造と機能
肘関節は上腕骨(じょうわんこつ)、尺骨(しゃっこつ)と橈骨(とうこつ)によって構成されます。上腕骨と橈骨の間の腕橈関節(わんとうかんせつ)、上腕骨と尺骨の間の腕尺関節(わんしゃくかんせつ)、尺骨と橈骨の間の近位上橈尺関節が、関節包に包まれ、靱帯によって安定性が保たれています。
肘関節の運動は基本的には屈曲・伸展(まげる・のばす)のみで、正常可動域は屈曲が145度、伸展が5度となっています。
屈曲動作(肘をまげる)はものを持ち上げたり、食べ物を口に運んだりする際に重要な役割を果たし、伸展動作(肘を伸ばす)は物を押したり投げたりする際に重要な役割を果たします。
この他に前腕の運動として回内・回外の回旋運動があります。回内は手のひらを下に向ける動作、回外は手のひらを上に向ける動作です。
5.手関節(しゅかんせつ)の構造と機能
手関節は橈骨、尺骨と8個の手根骨(しゅこんこつ)で構成されます。
8個の手根骨は舟状骨(じゅうじょうこつ)、月状骨(げつじょうこつ)、三角骨(さんかくこつ)、豆状骨(とうじょうこつ)、大菱形骨(だいりょうけいこつ)、小菱形骨(しょうりょうけいこつ)、有頭骨(ゆうとうこつ)、有鉤骨(ゆうこうこつ)です。
8個の手根骨のうち、近位(橈骨に近い方)が舟状骨、月状骨、三角骨、豆状骨で、遠位(橈骨から遠い方、指先に近い方)大菱形骨、小菱形骨、有頭骨、有鉤骨となり、橈骨と近位の手根骨で構成するのが橈骨手根関節、近位の手根骨と遠位の手根骨で構成するのが手根中央関節で、この二つの関節を合わせて手関節といい、この二つの関節が連携して手関節の背屈(伸展)や掌屈(屈曲)などの運動を行っています。
手関節側の橈骨と尺骨の間を遠位橈尺関節といい、TFCC(三角線維軟骨複合体)で連結され、手関節の回旋運動(回内、回外運動)をつかさどっています。
6.股関節(こかんせつ)の構造と機能
股関節は骨盤と大腿骨の間の関節です。ソケットに相当する骨盤側の寛骨臼(かんこつきゅう)と、ボールに相当する大腿骨側の大腿骨頭で関節を形成しています。
骨盤は左右の寛骨と仙骨(せんこつ)、尾骨(びこつ)で構成される盤上の骨で、寛骨は腸骨(ちょうこつ)、坐骨(ざこつ)、恥骨(ちこつ)の骨が結合したものです。
大腿骨は人体の中で最も長い骨で、近位端(体の中心に近い方)は大腿骨頭とよばれて内側に突出して大腿骨頚部によって大腿骨骨幹部につながっています。
関節は線維性の関節包で包まれています。関節包の内側には滑膜があり、関節の潤滑や軟骨に栄養を与える働きがある関節液を作っています。
股関節は多軸性の臼状(きゅうじょう)関節で、大きな可動域を持っています。屈曲・伸展、外転・内転、外旋・内旋の3方向の運動が可能です。
標準的な可動域角度は、屈曲125度、伸展15度、外転45度、内転20度、外旋と内旋はともに45度となっています。
7.膝関節(しつかんせつ)の構造と機能
膝関節は人体で最も大きな可動関節で、ほぼ全体重を支えるとともに、膝の屈伸運動をかのうにするという二つの大きな機能を担っています。
膝関節を構成する主要な骨は大腿骨、脛骨(けいこつ)、膝蓋骨(しつがいこつ)で、大腿脛骨関節と膝蓋大腿関節の二つの関節を構成します。
腓骨は膝関節の運動に直接関与しませんが、靱帯や腱の付着部として重要です。
関節面は軟骨組織で覆われ、関節の動きを滑らかにするとともに衝撃を緩和します。さらに大腿骨と脛骨の間には外側半月と内側半月という二つの線維軟骨があり、クッションの役割を果たしています。
関節の安定性は靭帯、筋肉と腱、関節を覆う関節包によってもたらされています。
関節包の内側は滑膜となっていて、滑膜から出される関節液は関節内を満たし、関節軟骨に栄養を与えています。
脛骨大腿関節を支持する靭帯は、主に内側と外側の側副靱帯と、関節内にある前後の十字靭帯です。内側側副靱帯は、外反といって下腿が体の外側に動く動きをコントロールしており、外側側副靱帯は下腿が内反する動きをコントロールしています。
十字靭帯は関節包内でクロスするように存在し、前十字靭帯は下腿の前方への動きをコントロールし、後十字靭帯は下腿の後方への動きをコントロールしています。
脛骨大腿関節(つまり膝の関節)は屈曲・伸展と内旋・外旋の二方向の運動が可能です。
標準的な可動域角度は、屈曲130度、伸展0度となっています。
8.足関節(そくかんせつ)の構造と機能
足関節は足部の関節と共同して直接荷重を地面に伝え、反力を受けます。また歩行時の衝撃の吸収や、重心の微妙な調整などの役割も担っています。
足部には多くの関節がありますが、足関節という場合、通常は距腿関節のことを指します。距腿関節は距骨滑車、脛骨、腓骨からなります。
足関節を安定させるために、内側には三角靭帯、外側には前・後距腓靭帯(きょひじんたい)と距踵靭帯(きょしょうじんたい)があり、足関節が過度に内外反することを防いでいます。
捻挫などで過度の内外反を受けた時に損傷しやすいのは前距腓靭帯と距踵靭帯です。
| 関連項目 |
- 後遺障害の定義と系列
- 等級認定のルール
(併合、加重) -
診断書、レセプトのポイント診断書の見方
- レセプトの見方
- 後遺障害診断書のポイント
- 関節可動域について
-
部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- ↳下肢の外傷・種類と
後遺障害 - もっと詳しく
当事務所について
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去の相談メール