��ʎ��̂Ɋւ���R�������f�ڂ��Ă���܂�
TEL.03-5393-5133
��177-0042 �����s���n�扺�ΐ_��1-8-27-305
���{�s�����m������
- �g�b�v�y�[�W
- �n�V���g�̃R����
�n�V���g�̃R����
�J�Ђ���x������Ă��Ă����̑��Ɏ����ӂ���S�z�x�����邱�Ƃ�����I�H(2018/10/11�j
-
����30�N9��28���̓ǔ��V�����u�i�J�Ђ���̋��t���Ă��Ă��j�����ӂ����Q�҂ɑS�z�x�����v�Ƃ����L�����o�Ă��܂����B
�ō��ق�9��27���ɏo�������̂悤�ł��B
�u���v���E���āH�v�̃y�[�W�ł��������Ă���܂����A��Q�҂̐����悪����̎����ӂ�A�����̘J�Еی���l�g���Q�ی��Ȃǂ����������Ă��A�������ڂɂ��ē�d���͂ł��Ȃ��̂������ł��B
����̍ō��ٔ���́A���̌��������̂Ȃ̂��H�ƋC�ɂȂ����̂ŁA���̍ō��ق̔��������Ă݂܂����B
���_�Ƃ��ẮA�����i��Q�҂̓�d����h���j���Ƃ������e�ł͂���܂���ł����B
���̔���̓��e�������
�@��Q�҂́A�Z���^�[���C�����z���Ă������Q�ԗ��Ƃ̎ԓ��m�̐ڐG���̂ŁA�E�F�f���ɉE���ߋ@�\��Q���c���A�J�Ђ���×{�⏞���t�i���Ô�j�A�x�ƕ⏞���t�y�я��Q�⏞���t���܂����i�ō��ٔ���ɂ͂��̕����̋��z�̋L�ڂ͂���܂���ł����j�B
�����̂��ƂŁA�J�Еی��@12����4��1���ɂ��A���t�������z�̌��x�ő���������ӕی��ւ̒��ڐ������́A���Ɉړ]���܂��B
�A��Q�҂̎咣�Ƃ��ẮA��L�J�Ђ��狋�t�������ȊO�ɁA���Q�Ŗ�303���~�A����Q��290���~�̑��Q������Ǝ咣���Ă��܂��B
���J�Ђ́u�Ԏӗ��v�̊T�O������܂���̂ŁA��L��Q�҂́u�J�ЈȊO�̕��v�́A�ʉ@�̈Ԏӗ���x�Ƒ��Q��4�����A����Q�̈Ԏӗ��Ȃǂƍl�����܂��B
�B��L�@�̔�Q�҂���J�ЂɈړ]�������ڐ������ƁA�A�̔�Q�҂Ɏc���Ă��钼�ڐ������̂ǂ��炪�D�悳��đ�����̎����ӂ���x������̂��A�Ƃ������Ƃ�����ꂽ�ٔ��ł����B
�܂�u��Q�҂��J�ЂƎ����ӂ����d���ł���̂��ǂ����v�ł͂Ȃ��A�����ӕی��̌��x�z�͌����Ă���̂Łi����͌���Q����12���Ȃ̂ŏ��Q��120���~�ƌ���Q12����224���~�̍��v344���~�j�A�u�J�Ёi���j����Q�҂��ǂ���ɂ�����������ӂɑ��鐳���Ȑ����������邪�A���̂ǂ��炪�D�悳���̂��v�Ƃ������̂ł����B
����������ӕی���Ђ́u�J�Ђ̐������̂�����z�ƁA��Q�҂̘J�ЈȊO�̑��Q�z���ĕ����Ď����ӂ���o���Ɏx�����v�Ǝ咣���Ă����悤�ł����A���ǂ͌f��̂Ƃ���u��Q�҂�D�悵�đS�z�i344���~�j��Q�҂Ɏx�����v�Ƃ������Ƃł����B�����1�R���������̂܂x���������̂ł��B
�l���Ă݂�A�����ԑ��Q�����ۏ�@�i�����@�j�⎩���ԑ��Q�����ӔC�ی��i�����ӕی��j�͔�Q�ҕی��}�邱�Ƃ��ړI�ō���Ă��܂�����A��Q�҂ւ̕⏞�́A���̐������Ɠ����Ȃǂł͂Ȃ��D�悳���͓̂��R�Ƃ������܂��B
�Ƃ͂����ō��ق̔��Ⴊ�o���ȏ�A����͂��̉^�p����ʓI�ɂȂ�Ǝv���܂��B�܂�u�����ӂ̌���ꂽ�ی������Q�҂ƍ��ƂŎ�荇�����ꍇ�͔�Q�҂��D�悳���v�Ƃ������Ƃł��B
���Ƌ��^�]�������ꍇ�̉ߎ������́H�i2018/10/3�j
-
���̂Ɋ������܂��Ɛg�̓I�ȋ�ɂ̂ق��ɁA�����ł�������̂��Ƃ��s���Ŏd���Ȃ��̂ɁA���ɂ���Ď��̂̑��肪���Ƌ��^�]�������ꍇ�A�ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂ł��傤���B
�E����̕ی��͂����̂�
�E������Ɣ������Ă��炦��̂�
�E������ɂƂ��ĕs���ɂȂ�����L���ɂȂ����肷�邱�Ƃ�����̂�
���Ƌ��^�]�͔ƍ߂ł��B�ƍ߂ɂ͌Y�����Ƃ��Ĕ����⒦���Ȃǂ��Ȃ����܂��i���H��ʖ@��117����2��2�j�B
��ʎ��̂ő��l�ɉ���������邱�Ƃ��u�����ԉ^�]�ߎ��v���v�Ƃ����ƍ߂ł����A���Ƌ��^�]�ʼn����������Ɓu�댯�^�]�ߎ��v���v�Ƃ����\�������܂�܂��B�܂���ɏd�������Ȃ�����A�Ƃ������Ƃł��B
����͖��Ƌ��^�]�������l�������̂ŁA�d�������ۂ����Ă��d������܂���B������ɂ͊W�Ȃ����Ƃł��B
���́u���肪���Ƌ����������ƂŁA������ɕs���v���������Ȃ����ǂ����v�ł��B
��ʎ��̂̔�Q�҂����Q�҂ƊW����̂́u��Q�҂̑��Q�����Q�ҁi�̕ی��j�ɔ������Ă��炤�v�Ƃ��������ł��B
���Q�ґ��́u�ΐl�����E�Ε������v�͎g����
����̎Ԃ��C�ӕی��ɓ����Ă���A���Ƌ��^�]�ł��ΐl������Ε������Ȃǁu���l�ɑ��锅���v�͕ی�����x�����܂��B�����ӕی������l�ł��B
�܂��Q�҂ɂƂ��ẮA���̕����͑��肪���Ƌ��ł����Ă������łȂ��Ă��ς��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
���肪�C�ӕی��ɓ����Ă���Ƃ肠��������S�ł����A�����������Ƌ��^�]������悤�Ȑl�̓��������Ⴂ�Ƃ������Ƃł�����A�C�ӕی��ɓ����Ă��Ȃ��\�����ʏ��荂���Ǝv���܂��B
���肪�C�ӕی��ɓ����Ă��Ȃ���A�����ł����Ă���C�ӕی��́u�l�g���Q�ی��v�𗊂邱�ƂɂȂ�܂��B
����́u�{�����Q�҂������ׂ����������A�����̕ی��������Ă����i���̕��͌�������̕ی���Ђ����Q�҂ɐ������܂��j�v�Ƃ������̂ł�����A��ϗ���ɂȂ�܂��B
�����A�ی����|���Ă���Ԃɏ�Ԓ��̏ꍇ�ɂ����x������Ƃ��A���]�Ԃɏ���Ă���������Ă���Ƃ��ɂق��̎ԂɂԂ���ꂽ�肵���Ƃ��ł��x������ȂǁA���������܂��܂Ȃ̂ŁA����Ƃ������g�̕ی��̓��e���m�F���Ă����Ă��������B
�i���Ɨp�Ԃ�������Γ���܂��j
�ߎ������́A���Ƌ��^�]�́u�d�ߎ��v�ɊY�����ďC���v�f�ƂȂ�ꍇ������
�o��������̎��̂ȂǁA�ǂ��瑤�ɂ��ߎ�������悤�ȏꍇ�ɂ́A���Ƌ��^�]�́u�d�ߎ��v�Ƃ��đ�����ɗL���ɂȂ�悤�ɉߎ��̊������C������邱�Ƃ�����܂��B
�����A�ԐM����~���ɒǓ˂��ꂽ�Ԃ̉^�]��i��Q�ҁj�����Ƌ��������悤�ȏꍇ�A���Ƌ����������߂Ɏ��̂��N�����i�Ǔ˂��ꂽ�j�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�܂莖�̂Ɩ��Ƌ��Ƃ̈��ʊW�͂���܂���A���̂悤�ȏꍇ�ɖ��Ƌ��^�]�̏C���͂Ȃ���܂���B
�����͌����Ă����̓����ҊԂł̉ߎ������ɉe�����Ȃ��Ƃ��������ł����āA���Ƌ��͔ƍ߂Ȃ̂ŁA����Ƃ͕ʂɌY����s�����͉Ȃ����\��������܂�
�ً}�ԗ��Ǝ��̂��N�������ꍇ�̉ߎ������́H�i2018/7/10�j
-
�߂����ɂȂ����Ƃł����A�ɂ܂�ɋً}�����Ԃ���ʎ��̂̓����ԗ��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�ً}�����Ԃƈ�ʎԗ����Փ˂���A�Ƃ������Ƃł��B
���̂悤�ȏꍇ���ߎ������͂ǂ��l����̂ł��傤���B�ً}�����ԂƂ�
�܂��u�ً}�����ԂƂ͉����v�Ƃ������Ƃł����A�ً}�����ԂƂ�
�u���h�p�����ԁA�~�}�p�����Ԃ��̑��̐��߂Œ�߂鎩���ԂŁA���Y�ً}�p���̂��߁A���߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A�^�]���̂��̂������v�i����@39��1���̂��������j
�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B������₷�������ƁA�T�C������炵�ĐԐF�̌x���������Ă���~�}�Ԃ��p�g�J�[�����h�Ԃƍl��������Ǝv���܂��B
�����p�g�J�[��~�}�Ԃł���ً}�����Ԃł͂Ȃ��A�T�C�����ƐԐF���̗������g�p���Ă����ԂłȂ���ً}�����ԂƂ͂����܂���B
�ً}�����ԂɔF�߂������
����Ƃ��Ď�Ȃ��̂́A
�E�ǂ��z��������ꍇ���̑���ނȂ��ꍇ�ɂ́A�͂ݏo���֎~�ꏊ�ł����H�̉E���ɂ͂ݏo���Ă��ǂ��B
�E�@�߂̋K��ɂ���~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ꍇ�i��\�I�Ȃ̂͐ԐM���̌����_�j�ł���~���邱�Ƃ�v���Ȃ��B���������̌�ʂɒ��ӂ��ď��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂�A�ً}�����Ԃ͐ԐM���Œ�~���邱�Ƃ܂ŋ��߂��Ă��Ȃ����A���ӂ��ď��s���Ȃ�����A�Ƃ������Ƃł��B
��ʎԗ��̋`��
�E�ً}�ԗ����߂Â����Ƃ��́A��ʂ̎ԗ��͌����_������ē��H�̍����Ɋ���Ĉꎞ��~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Ƃ���Ă��܂��B
�ً}�����Ԃ��ԐM���A��ʎԗ����M���́A�����_�ł̏o��������̎��̂̏ꍇ
�����_�ł̈�����M���A����������ԐM���̎��̂̏ꍇ�A��ʎԗ����m�Ȃ瓖�R�ԐM�����̎ԗ��ɉߎ�100���Ƃ������ƂɂȂ邩�Ǝv���܂����A�����ԗ����ً}�����ԂɂȂ�Ə�L�Ő��������悤��
�E�ԐM���ł̒�~�`�����Ə�����Ă���B
�E��ʎԗ��͌����_�܂��͂��̕t�߂ŋً}�����Ԃ��ڋ߂��Ă����Ƃ��́A�����_������A�����H�̍����Ɋ���Ĉꎞ��~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��`��������B
�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B��������Ƌً}�����ԐԐM���A��ʎԗ��M���̂��̂悤�ȏꍇ�ɁA��~���ׂ��͈�ʎԗ��̕��Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��ʎԗ��͐M���Ō����_�ɐi�����Ă��Ă��A�ꎞ��~�`����ӂ������ƂɂȂ��Ă��܂��A�ꎞ��~�`�������ꂪ�t�]���Ă��܂��܂��B
�Ƃ͂����ً}�����Ԃ��A�ԐM���ňꎞ��~����K�v�͂Ȃ����̂́A���̌�ʂɒ��ӂ��ď��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����`���͂���܂��̂ŁA���S�ɖƐӂƂ����킯�ł�����܂���B
�ߎ�����������ƁA�ʍ�����^�C���Y38�u�ߎ����E���̔F���v�ł�
�u�ً}�����ԑ����ԐM���v�u��ʎԗ������M���v�́A�l�֎ԓ��m�̌����_�ł̏o��������̎���
�ɂ��āA20�i�ً}�����ԁj��80�i��ʎԗ��j�Ƃ��Ă��܂��B
����͌��ʂ��̈��������_��z�肵�Ă���A�C���v�f�Ƃ��āu���ʂ������������_�v�Ȃ��ʎԗ��Ɂ{10���Ƃ��A�ً}�����Ԃ����s���Ă����Ƃ����炳��Ɉ�ʎԗ��Ɂ{10���ȂǂƂ��Ă��܂��B
��ʎԗ��ɗL���ȏC���Ƃ��ẮA��ʎԗ������s���Ă������H���������H�������ꍇ�ɁA��ʎԗ��Ɂ|10���Ƃ��Ă��܂��B
�^�]�Ƌ��̋��K���ɒʂ��Ă������납��A�ً}�����Ԃ�������~�܂��ē�������Ȃ����A�ƏK���Ă����Ƃ���ł����A������ً}�����ԂƂ̎��̂��N�������ꍇ�A�����͈�ʎԗ��̉ߎ��ɂȂ��Ă��܂��A�Ƃ������Ƃ�S���Ă����܂��傤�B
�u���撆�v�Ɠ����̑������ʊW�Ƃ́i2018/4/30�j
-
�O��u���撆�Ƃ͂ǂ�������Ԃ��v�u���撆�łȂ��Ă�����ҏ��Q�ی��Ȃǂ��ł�v�Ƃ������b�����܂����B
 �����čō��ق̔���Łu���撆���ǂ����A�ȂǂƂ��������ׂȂ��Ƃɂ�������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�������ʊW������Εی����̎x�����͋��ۂł��܂�����v�Ƃ������f���o�����Ƃ��Љ�܂����B
�����čō��ق̔���Łu���撆���ǂ����A�ȂǂƂ��������ׂȂ��Ƃɂ�������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�������ʊW������Εی����̎x�����͋��ۂł��܂�����v�Ƃ������f���o�����Ƃ��Љ�܂����B
��������ƁA���撆�ł͂Ȃ����ǎ��S�Ǝ������̂̑������ʊW�����邩�ǂ����ɂ��Ă��߂����Ƃ��\�z�����̂ł����A���ꂪ���ƂȂ������Ⴊ����܂����̂ł��Љ�܂��B
���撆�Ɠ����̈��ʊW�����邩�ǂ���
��Q�҂�80�Βj���i���ɁuA�v�Ƃ��܂��j�ŁA�[��ɎԂ��^�]���Ă��ĎԂ��Ɠc��ڂɓ]�����鎩�����̂��N�����܂����B
���̌�j���͎ԊO�ɏo�āA�Ԃ̎�����������A�Ԃ���4���[�g���قǗ��ꂽ�ꏊ�œ]�|���A�ӎ��s���̏�Ԃ�5�`6���Ԍ�ɔ�������܂������A���̎��ɓD�����z�������߂ɔx�����������A40����Ɏ��S�����Ƃ������̂ł��B
���̎��̂ň⑰�́A�D�����z������Ŕx���ɂȂ莀�S�������Ƃ́i���撆�Ƃ͌����Ȃ����̂́j���̂Ƃ̈��ʊW������Ƃ��āA�������Ă��������ԋ��ςɎ������̏��Q���ς𐿋����܂����B
����ɑ��ĂȂ��1�R�i�����n�فj�́A�uA�̔x���ɂ�鎀�S�Ǝ��̂Ƃ̊ԂɈ��ʊW������v�Ƃ��āA���ϋ��̎x�����𖽂��܂����B
���̗��R��
�u�{�������ԋ��ό_��ɒ�߂�wA�Ԃ̉^�s�ɋN������}�������R�ȊO���̎��́x�ɂ�菝�Q����A���́w���ڂ̌��ʂƂ��āx���S�����ꍇ�ɓ�����A�������ʊW���F�߂���v
�Ƃ̂��Ƃł����B
�ł������̔����́A2�R�ŕ�����A�������ق́uA�̔x���ɂ�鎀�S�Ǝ��̂Ƃ̊ԂɈ��ʊW�͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���܂��B
2�R�̔����ł́A���撆�Ɠ���������قǂ̈��ʊW�ɂ�
�u�@A���g�̂̑��������˂Ȃ��ؔ������댯������邽�߂ɎԊO�ɔ�����Ȃ��ɒu����
�A���̔��s���͔��o�H���܂߂ď�L�댯�ɂ��炳�ꂽ�s���Ƃ��Ď��R�Ȃ��̂ł���
�BA�̎��S���{�����̂Ǝ��ԓI�ɂ��ꏊ�I�ɂ��ߐڂ��Đ����Ă�������
�̂�������F�߂���K�v������v
�Ƃ̍ō��ق̗Ꭶ�������A���̂����Ŗ{����
�u�M�A�̓p�[�L���O�ɓ����Ă����ԁv�Łu�G���W���͂������Ă���A�O�Ɠ��͓_���v�u�ڂ������j�����ʂ��F�߂�ꂸ�v�A�u�E�o�㏕��ȑ��œ|��Ă����v���ƂȂǂ���O�L�@�`�B�ɊY�������A�������ʊW�͔F�߂��Ȃ��A�Ƃ��܂����B
���̌�͍ō��قɎ������݂܂��������ꂸ�A���ق̔������m�肵�Ă��܂��B
���ʂɍl���Ă݂�ƁA�������ق̔��������ʂȂ悤�Ɏv���܂����A�ꎞ�͂��̂悤�Ȏ��̂ł��^�s�Ɣx���ł̎��S�Ƃ̑������ʊW������A�Ƃ����������o�Ă���܂��̂ŁA���ɔ����Ȃ��ƂȂ̂��Ƃ������Ƃ������܂��B
�����A�������g�̌��ł͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ��������ƂŖ�������Y�肳��Ă��܂�����A�����Ȃ����₢���킹���������B
2.�u���撆�v�͂���Ȃɏd�v���H
���̎��̂́A�������H�Ŏ������̂��N���������ߘH���ɑҔ����悤�ƎԊO�ɏo�Ă����Ƃ��㑱�ԂɂЂ���Ď��S�����Ƃ������̂ł����A�ی���Ђ́u���撆�v�ł͂Ȃ��̂����瓋��ҏ��Q�ی������x����Ȃ��Ƃ��Ă��܂����B
����19�N5��29�������̍ō��ٔ���ł����A�u�ȉ��̏���������A�{���ԗ��̉^�s�ɋN�����鎖�̂ł̎��S�Ⴕ���͓��撆�̎��S�Ɠ���������v�Ƃ��Ă���A���̏�����
�@A�i��ی��ҁF���S�j���g�̂̑��������˂Ȃ��ؔ������댯������邽�߂ɎԊO�ɔ�����Ȃ��ɒu����
�A���̔��s���͔��o�H���܂߂ď�L�댯�ɂ��炳�ꂽ���̂̍s���Ƃ��Ď��R�Ȃ��̂ł���
�BA�̎��S���{�����̂Ǝ��ԓI�ɂ��ꏊ�I�ɂ��ߐڂ��Đ����Ă�������
�̂�������F�߂���ꍇ�A
�Ƃ��Ă���܂��B�ł�����A���̎��̂œ��撆�ł͂Ȃ��̂ŕی������x����Ȃ��Ƃ������f��
�u�{���������̂Ƃ`�̎��S�Ƃ̊ԂɔF�߂��鑊�����ʊW��������̂ł����āA�����ł͂Ȃ��B�v
�u�^�s�N�����̂ɂ���Ďԓ��ɂ��Ă��ԊO�ɂ��Ă��������g�̂̑��Q�����˂Ȃ��ؔ�������@�����������ꍇ�A�ԓ��ɂ��ĕ�������Εی����̎x�������邱�Ƃ��ł��A�ԊO�ɏo�ĕ�������Εی����̎x���������Ȃ��Ƃ����̂��s�����ł���v
�u�{������ҏ��Q�����ɂ����ẮC�^�s�N�����̂ɂ���ی��҂̏��Q�́C�^�s�N�����̂Ƒ������ʊW�̂�������ی��҂���ی������Ԃ̓��撆�ɔ�������̂Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�v
�Ƃ��āA����ҏ��Q�ی�����̎x�����𖽂�����̂ł����B
�������n�ʂɂ��Ă��邩�ǂ����i���撆���ǂ����j�ȂǂƂ��������ׂȂ��Ƃɂ�������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�������ʊW������Εی����̎x�����͋��ۂł��܂����A�Ƃ������f�ł��B
���̂悤�Ȕ��f�͔�Q�҂ɂƂ��Ă͗L���ŗǂ������Ɏv���܂����A��Q�҂Ƃ��Ắu���撆���������ǂ����v������w�����܂��ō���ȁu�������ʊW������̂��ǂ����v�Ƃ������Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����A�Ƃ�������Ǝv���܂��B
�������f�ɖ����Ă��������������Ⴂ�܂�����A�����Ȃ����₢���킹���������B
�u���撆�v�Ƃ͂ǂ�������Ԃ��H�i2018/4/19�j
-
�����ԕی��ł́A�ΐl��Ε��̂悤�ɑ��l�ɑ��Q��^�����ꍇ�ɕ⏞�����Ă����ی��ƁA����������������ꍇ�ɕ⏞���Ă����ی�������܂��B
�����ɑ���⏞�Ƃ́A��̓I�ɂ́u����ҏ��Q�ی��i����j�v�u�������̕⏞�ی��i����j�v�u�l�g���Q�⏞�ی��i����j�v�ȂǂŁA�ی��������Ă��鎩���ԂɁu���撆�v�ɑ��������̂ł̉��䂪�ΏۂƂȂ��Ă��܂��i�l�g���Q�⏞�ی��͈ꕔ�ԊO�ł̎��̂ɂ��Ή�����j�B
1.�u���撆�v�Ƃ͉���
 �����Ă��́u���撆�v�A�܂�Ԃɏ���Ă����ԂȂ̂��ǂ������A���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�����Ă��́u���撆�v�A�܂�Ԃɏ���Ă����ԂȂ̂��ǂ������A���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�u���撆�v�Ƃ́A�����ԕی��̖ɂ���
�u��ی������Ԃ̐��K�̏�Ԉʒu�܂��͓��Y���u�̂��鎺���i�u�Ǔ��ɂ��ʍs�ł��Ȃ��悤�Ɏd���Ă���ꏊ�������܂��B�j�ɓ��撆�̎҂������܂��B�v�Ƃ���Ă��܂��B
���K�̏�Ԉʒu�ł͂Ȃ��̂́A�Ⴆ�Ή����̏�ɏ���Ă����葋�g�ɍ������đ̂��O�ɏo���Ă�����i�܂�u�n�R�m���v�j�̓_������A�Ƃ������Ƃł��B
�g���b�N�̉ב�Ȃǂ����K�̏�Ԉʒu�ł͂���܂���B
�����āA���n�߂���~��I���܂ł̓���̒��ł��ǂ�����ǂ��܂ł����撆�Ȃ̂��A�Ƃ������Ƃ�����Ŏ�����Ă��܂��B
����ɂ��Γ��撆�Ƃ́A��ʓI�ɂ�
�u���ȂȂǂɏ�邽�߂ɁA�葫���͍��Ȃǂ��h�A�A���A�X�e�b�v�ȂȂǂ��痣���A�ԊO�ɗ�����t���鎞�܂ł̊Ԃ������v�i�����n�����a60�E11�E22�j
�Ƃ̂��Ƃł��B
�܂藼����n�ʂɂ��ĎԂ��痣���A���撆�ł͂Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ŏ������G�Ȃ̂ł����A�ō��ق̔���Łu���撆�ł͂Ȃ�����ƌ����ĕK����������ҏ��Q�ی����x�����Ȃ��̂͂��������v���u���撆�łȂ��Ă��A���̏���������Γ���ҏ��Q�ی����x������ׂ����v�Ƃ������̂�����܂��B
2.�u���撆�v�͂���Ȃɏd�v���H
���̎��̂́A�������H�Ŏ������̂��N���������ߘH���ɑҔ����悤�ƎԊO�ɏo�Ă����Ƃ��㑱�ԂɂЂ���Ď��S�����Ƃ������̂ł����A�ی���Ђ́u���撆�v�ł͂Ȃ��̂����瓋��ҏ��Q�ی������x����Ȃ��Ƃ��Ă��܂����B
����19�N5��29�������̍ō��ٔ���ł����A�u�ȉ��̏���������A�{���ԗ��̉^�s�ɋN�����鎖�̂ł̎��S�Ⴕ���͓��撆�̎��S�Ɠ���������v�Ƃ��Ă���A���̏�����
�@A�i��ی��ҁF���S�j���g�̂̑��������˂Ȃ��ؔ������댯������邽�߂ɎԊO�ɔ�����Ȃ��ɒu����
�A���̔��s���͔��o�H���܂߂ď�L�댯�ɂ��炳�ꂽ���̂̍s���Ƃ��Ď��R�Ȃ��̂ł���
�BA�̎��S���{�����̂Ǝ��ԓI�ɂ��ꏊ�I�ɂ��ߐڂ��Đ����Ă�������
�̂�������F�߂���ꍇ�A
�Ƃ��Ă���܂��B�ł�����A���̎��̂œ��撆�ł͂Ȃ��̂ŕی������x����Ȃ��Ƃ������f��
�u�{���������̂Ƃ`�̎��S�Ƃ̊ԂɔF�߂��鑊�����ʊW��������̂ł����āA�����ł͂Ȃ��B�v
�u�^�s�N�����̂ɂ���Ďԓ��ɂ��Ă��ԊO�ɂ��Ă��������g�̂̑��Q�����˂Ȃ��ؔ�������@�����������ꍇ�A�ԓ��ɂ��ĕ�������Εی����̎x�������邱�Ƃ��ł��A�ԊO�ɏo�ĕ�������Εی����̎x���������Ȃ��Ƃ����̂��s�����ł���v
�u�{������ҏ��Q�����ɂ����ẮC�^�s�N�����̂ɂ���ی��҂̏��Q�́C�^�s�N�����̂Ƒ������ʊW�̂�������ی��҂���ی������Ԃ̓��撆�ɔ�������̂Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�v
�Ƃ��āA����ҏ��Q�ی�����̎x�����𖽂�����̂ł����B
�������n�ʂɂ��Ă��邩�ǂ����i���撆���ǂ����j�ȂǂƂ��������ׂȂ��Ƃɂ�������Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��A�������ʊW������Εی����̎x�����͋��ۂł��܂����A�Ƃ������f�ł��B
���̂悤�Ȕ��f�͔�Q�҂ɂƂ��Ă͗L���ŗǂ������Ɏv���܂����A��Q�҂Ƃ��Ắu���撆���������ǂ����v������w�����܂��ō���ȁu�������ʊW������̂��ǂ����v�Ƃ������Ƃ��ؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����A�Ƃ�������Ǝv���܂��B
�������f�ɖ����Ă��������������Ⴂ�܂�����A�����Ȃ����₢���킹���������B
�z�X�e�X�̈편���v�̍l�����́H�i2017/12/20�j
-
����Q���c�����ꍇ�̈편���v�̍l�����́A��{�I�ɂ͈ȉ��̗l�Ȍv�Z���ŎZ�o����܂��B
�편���v�i�~�j����b�����z�i�~�j�~�J���\�͑r�����i���j�~�Ώ۔N���̌W��
�편���v�́u����������͂��������̂ɓ����Ȃ��Ȃ����Ǝv���闘�v�v�̂��ƂŁA�����܂Ńt�B�N�V�����ł���A�����z�肷�邽�߂ɂ������̂��Ƃ���茈�߂Ă���܂��B
�@��b�����z�́A�����̂��Ƃ͕�����Ȃ��̂łƂ肠�������̒��O�̌����������̗p���܂��傤�B
�A�J���\�͑r�����́A����Q�����ɉ����Ď����ӎx������̕ʕ\�T�̘J���\�͑r�������g���܂��傤�B
�B�Ώۊ��ԁi�J���\�͑r�����ԁj�́A�P����Ŗo�ȂLjȊO�́u�������ɂ͖߂�Ȃ�����Q�v�⎀�S�̏ꍇ��67�܂œ������ł��낤�A�ƍl���܂��傤�B
����3�_��O��Ƃ��Ĉ편���v�����܂��Ă��܂��B
�ł����E�Ƃɂ���ẮA���s�ɍ��E���ꂽ��A���邢�͔N��I�Ȑ���������Ȃǂ��Č��݂̎�����67�܂ł����Ɠ���ꑱ����ƍl���邱�Ƃɖ��������邱�Ƃ�����܂��B
��̓I�ȐE�ƂŌ����ƁA�z�X�e�X��z�X�g�A�o�D��^�����g�A�X�|�[�c�I��ł����A�ٔ���ł͏�L�́u��茈�߁v�Ɋւ�炸�A��b�����z��Ώۊ��Ԃɂ��ď_��ɍl���邱�Ƃ������悤�ł��B
����́A���̒��ł����Ɏ���̑����z�X�e�X�̈편���v�Ɋւ��āA�ٔ���ł̊�b�����z�ƑΏ۔N���̍l�����ɂ��Č������Ă݂܂��B
�S�̓I�ɂ�����̂́A��ʎ��̂ɑ����������̎��������ϒ�����葽�������ꍇ�Ɂu���鎞���܂ł̓z�X�e�X�Ƃ��Ă̌����ɓ��Ă����N���Ōv�Z�v�u����ȍ~�͕��ϒ����i�N��ʂ�S�N��ςȂǁj��N���Ƃ��Čv�Z�v����邱�Ƃ������悤�ł��B
1.���n�ٕ���10�N10��19�������i�W31��5��1543�Łj
�@���S���N��F28�i�����E�z�X�e�X�j
�A�J���\�͑r���̑Ώۊ��ԁF28����67�܂�
�B��b�����z�F33�܂ł̓z�X�e�X�Ƃ��Ă̎����i691��4268�~�j�A���̌�67�܂ł͒����Z���T�X���q�w���v30�`34�̕��ϒ����i370��4300�~�j
�������i��Q�ҁj���́A���S����������67�܂Ńz�X�e�X�Ƃ��ē������͂����Ǝ咣���A�퍐�i���Q�ҁj���́A�������z�X�e�X�Ƃ��ē������̂͂�������30�܂ł��Ǝ咣���܂������A�ٔ�����33�܂ł��炢�̓z�X�e�X�Ƃ��ē����W�R��������Ɣ��f���܂����B
2.���É��n�ٕ���21�N8��28�������i�W42��4��1118�Łj
�@�Ǐ�Œ莞�N��F22�i�����E�z�X�e�X�E�E�ҊߒE�P���A�X��7�������j
�A�J���\�͑r���̑Ώۊ��ԁF22����67�܂�
�B��b�����z�F35�܂ł̓z�X�e�X�Ƃ��Ă̎����i477��1280�~�j�A���̌�67�܂ł͒����Z���T�X�S�J���ґS�N��ϒ����i343��4400�~�j
���ٔ����́A�{���̔�Q�҂�����܂�1�N�ȏ�z�X�e�X�𑱂��Ă���A�����������ӌ�������������A���Ȃ��Ƃ�35�܂ł̓z�X�e�X�Ƃ��ē������ł��낤�Ɣ��f���܂����B
3.�����n�ٕ���16�N3��23�������i���ۃW���[�i��1556���j
�@�Ǐ�Œ莞�N��F40�i�����E�z�X�e�X�A���D�A��w�E���b���ɓ��ŕ���11���j
�A�Ώۊ��ԁF40����67�܂�
�B��b�����z�F45�܂ł͏��D����уz�X�e�X�Ƃ̎����i���z2��421�~�j�A���̌�60�܂ł͒����Z���T�X�S�J���ґS�N��ϒ����i�N�z487��9700�~�j�A���̌�67�܂ł͒����Z���T�X���q�w���v�S�N��ϒ����i329��4200�~�j
���ٔ����̔��f�́A�z�X�e�X�ƁA���D�͌������o�ϕs���̉��A�i�C�ɂ�蔄��グ���ϓ�������̂ł���A�N���u�̌o�c�͓���A���ۂɔ�Q�҂��Ζ����Ă����N���u���X���Ă��邱�ƂȂǂ���A67�܂Ō��݂̎������ێ��ł���W�R���͔F�߂������A�Ƃ������Ƃł����B
4.�����n�ٕ���14�N9��2�������i���ۃW���[�i��1498���j
�@�Ǐ�Œ莞�N��F46�i�����E���͎������Ŗ�̓z�X�e�X�A�Ғ��ό`��Q�ŕ���10���j
�A�Ώۊ��ԁF46����67�܂�
�B��b�����z�F51�܂ł̓z�X�e�X�Ƃ��Ă̎����i�N�z199��800�~�j���܂ގ����A���̌�67�܂ł͒����Z���T�X���q����45�`49�̕��ϒ����i�N�z351��7300�~�j
���ٔ����́A��������Ȃ��Ƃ�5�N�Ԃ̓z�X�e�X�Ƃ��ĉғ����A���̑O�Ɠ����x�̎������W�R�������邪�A���̌�̗͑͂̒ቺ�Ȃǂɂ���Ď����������邱�Ƃ͔������Ȃ����낤�A�Ɣ��f���Ă���ȍ~�͍����̕��ϒ����Ɣ��f���܂����B
5.�����n�ٕ���13�N1��30�������i�W34��1��138�Łj
�@�Ǐ�Œ莞�N��F47�i�����E��Ј����z�X�e�X�A�̔j�����ŕ���10���j
�A�Ώۊ��ԁF47����67�܂�
�B��b�����z�F�����Z���T�X���q�w���v�S�N��ϒ����i�N�z340��2100�~�j
�������i��Q�ҁj�͊�b�����z���z�X�e�X�Ƃ��Ă̎������܂ތ��z34��6000�~�j���咣���Ă��܂������A�ٔ����͍���20�N�Ԃɂ킽���Č��z34��6000�~����W�R�����Ȃ��Ƃ��āA���ϒ������̗p���܂����B
6.�����n�ٕ���12�N9��20�������i���ۃW���[�i��1394���j
�@���S���N��F25�i�����E�z�X�e�X�j
�A�Ώۊ��ԁF67�܂�
�B��b�����z�F30�܂Ńz�X�e�X�Ƃ��Ă̎����i�N�z432��1600�~�j�A���̌�67�܂ł͒����Z���T�X���q�w���v30�`34�̕��ϒ����i�N�z384��4600�~�j
���ٔ����́A�z�X�e�X�Ƃ����d���̐�����A���̋Ζ����Ԃɂ킽���Čp�����A���������ێ�����W�R����F�߂�͍̂�����A����5�N���炢�͑������ƍl���Ă������ł��傤�A�Ƃ������f�����܂����B
�����̗�͑S�Ď��S�����ɖ߂�Ȃ�����Q�̎���ŁA�ʏ�Ȃ�J���\�͑r�����Ԃ�67�܂ŔF�߂��鎖��ł��B
�z�X�e�X�ł��J���\�͑r���̑Ώۊ��Ԃ͂ق�67�܂ŔF�߂��Ă��܂����A���ς����������ƂȂ��z�X�e�X�Ƃ��Ă̎����z�́A�Ǐ�Œ�i�܂��͎��S�j��������Ԃ����F�߂��Ȃ����Ƃ������悤�ł��B
���̈����Ԃ��ǂ̒��x���Ƃ������Ƃ́A20�`30��̎Ⴂ����A�܂荡��̐l���������l���������A40�`50��́A����܂Œ����z�X�e�X�𑱂��Ă����l�����̕����z�X�e�X�Ƃ��Ă̎����̊��Ԃ����߂ɔF�߂����ۂł��B
��Q�҂̕��݂͂�Ȃ��ٔ�������킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�ی���ЂƂ̎��k���̍ۂɂ��A�Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ԏ��\���̌l���Ǝ�̈편���v�͂ǂ��Ȃ�H�i2017/12/4�j
-
�Ԏ����Ƃ��c�ތl���Ǝ�̊�b�����z�͂ǂ��l����̂�
1.�편���v�̍l�����ƌv�Z���@
���̂̉���Ŕ�Q�҂Ɍ���Q���c�����ꍇ�A�����͂��̌���Q�̂��߂Ɏ��̑O�Ɠ����悤�ɓ������Ƃ�����ɂȂ�܂��B
�����Łu����Q�̂��߂ɏ����̘J���\�͂����p�[�Z���g��������v�ƍl���A�����u����Q��������Γ���ꂽ�ł��낤�����v������Q�ɂ��편���v�ŁA��Q�҂��Ԏӗ��ȂǂƂƂ��ɑ��Q���������̍��ڂł��B
���z�Ɋ��Z������@�Ƃ��ẮA�u�N���̉��p�[�Z���g�����A���㉽�N���ɂ킽���Ď�����v�Ƃ����̂���{�I�ȍl�����ŁA�ȉ��̂悤�Ȍv�Z���ɂȂ�܂��B
�편���v�@���@��b�����z�@�~�@�J���\�͑r�����@�~�@�J���\�͑r������
�J���\�͑r�����́A����Q�����ɂ���Č��܂�܂��B�J���\�͑r�������́A�����I�ɂ͏Ǐ�Œ肩��67�܂ł̔N���ɑΉ�����u���C�v�j�b�c�W���v�ł��B
����ł͊�b�����z�͂ǂ��l����̂ł��傤���B
2.��b�����z���ǂ��l���邩
��b�����z�͌����Ƃ��Ď��̂̑O�N�̔N���ōl���܂��B�편���v�͏����̂��Ƃ����z�����Č��߂�Ƃ����A�����Ȃ�t�B�N�V�����ł����A�̗p����̂͌����̐��l�i���z�j�Ȃ̂ł��B
�N���͉�Ј��Ȃ猹���[�ȂǂŊm�F�ł��܂����A�l���Ǝ�i���c�Ǝҁj�͊m��\�����ȂǂŊm�F���܂��B
�����l���Ƃ̔N���́A����グ���珔�o��������������u�����v�ōl���܂��B�����̋��z�ɘJ���\�͑r������C�v�j�b�c�W����������̂ł��B
����ł͂��̏������}�C�i�X�A�܂����̎��Ƃ��Ԏ��������ꍇ�́A�ǂ�����̂ł��傤���B
�N�����[���ȉ�������편���v�͂��炦�Ȃ��H
����Ȃ��Ƃ͂���܂��A�Ԏ����Ƃ��c�ތl���Ǝ傪�A�����A��b�����z����W�R�����F�߂��邩�ǂ����A�܂����͐Ԏ������Ǐ����͍����ɂȂ��Ă�����Ə�������悤�Ȑ������ł��邩�ǂ����A�Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��B
���̊W�R���̔��f�́A��Q�҂̔N��A���Ɠ��e�A�A�ƏA������A����܂ł̔���グ�̐��ڂ܂��Ď��Ƃ���芪�����Ȃǂ����Ă��āA���ꂼ��ʂɔ��f����K�v������܂��B
���z�Ƃ��ẮA�����̂��ƂȂ̂ŕ�����܂��A�����Ȃ�����J���Ȃ����v������Ă�������Z���T�X�ɂ�镽�ϒ����́A�ꉞ�̖ڈ��Ƃ���܂��B
3.��N�̌l���Ǝ�ƔN�z�̌l���Ǝ�
�W�R���̈�̍l�����ł��B
��N�̌l���Ǝ�̏ꍇ�́A�편���v�v�Z�̗v�f�ƂȂ�u�J���\�͑r�����ԁv�����������Ȃ邱�Ƃ��l�����܂��̂ŁA����������Ǝ��̎��̐Ԏ����Ƃɏ]���������邱�Ƃ�K�������O��Ƃ����ɁA���ϒ������x�̎�������W�R��������A�ƍl���Ă��s���R�ł͂Ȃ��ł��傤�B
����ɁA�E�T�����Ď��Ƃ��n�߂�����Ŏ��т��\���ł͂Ȃ��悤�ȏꍇ�́A���̎��Ƃ̎��x�̏Ŋ�b�����z�����߂邱�Ƃ͓K�ł͂Ȃ����Ƃ������A���ϒ�����A�T�����[�}������̎�������b�Ƃ��čl����ꍇ������܂��B
����A������x�̔N�z�̌l���Ǝ�̏ꍇ�A����܂ł̎��Ƃ̐��ڂ�Ԏ��̊��ԂȂǂɂ��A�p���I�ȐԎ���ԂɂȂ��Ă���悤�ȏꍇ�Ȃǂɂ́A���㕽�ϒ�������W�R����F�肷�邱�Ƃ͓���A�Ƃ������Ƃ����蓾�܂��B
��Q�҂��편���v�̓��e����z�������鑊��́A��ɉ��Q�҂̕ی���Ђł��傤�B
�Ԏ����Ƃ̏ꍇ�A�ی���Ђ͍ٔ����ȏ�ɔ�Q�҂̊�]�z��F�߂邱�Ƃɂ͌������Ǝv���܂��B�ł�����L�̂��ƂȂǂ𗝉�������ŁA�K�v������Ήߋ��̍ٔ����T������A�ꍇ�ɂ���Ă͍s�����m��ٌ�m�̃A�h�o�C�X���Ȃ���A�Ȃ�Ƃ��u�����ȁv�����z����������Ă������������Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ԏ��\���̌l���Ǝ�̋x�Ƒ��Q�͂ǂ��Ȃ�H�i2017/11/28�j
-
1.�܂��͍����̌l���Ǝ�i�T�����[�}���ȊO�j�̋x�Ƒ��Q
��Ј��i�T�����[�}���j�ȊO�́A�Ⴆ�Όl�Ŏ��Ƃ����Ă���l���Ǝ傪���̂̔�Q�҂ɂȂ����ꍇ�ɁA�x�Ƒ��Q�ɂ��Ăǂ��l���Ăǂ��v�Z����̂��ɂ��āA���L�̃y�[�W�Ő������܂����B
�u�T�����[�}���ȊO�̋x�Ƒ��Q�́H�v

�ȒP�Ɍ����A����グ���珔�o����������u�����v�Ɋւ��A���̂̑O�N�Ǝ��̂ɑ����ĉ�������Ďd�����x���N�̋��z���r���āA���������z���x�Ƒ��Q�Ƃ���A�Ƃ������Ƃł��B
���ۂɂ́A�O�N�ɔ�ׂĔ���グ�⏊�����������̂́A���̂̉���Ŏd�����x���Ƃ������Ȃ̂��A����Ƃ��ʂ̗v���Ō������̂��̔��f�́A������Ƃ������̂ł����A���������Ƃ��Ă͏�L�̂悤�ɂȂ�܂��B
�Ⴆ�A����28�N�Ɏ��̂ɑ������l���Ǝ傪�A���N�ԋx�Ƃ�����Ȃ��Ȃ����Ƃ��āA���̕���27�N�ƕ���28�N�̎��x���ȉ��̂悤�������Ƃ��܂��B�i�P�ʖ��~�j
�y��1�z����27�N 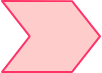
����28�N ����グ 1000 ����グ 500 ���㌴�� 300 ���㌴�� 150 �Œ�o�� 200 �Œ�o�� 200 �����o�� 200 �����o�� 100 ���� 300 ���� 50
����28�N��1�N�̂����̔������x�̂ŁA����グ�┄�㌴���◬���o��͔����ɂȂ�܂����A�Œ�o��i�ƒ���ی����Ȃǁj�͋x�Ƃ��Ă��Ă��ς��Ȃ��̂ŁA������50�ƂȂ�܂��B���̑O�N�Ƃ̍��z��250���~�ł��B
���ꂪ�A�����̌����z�ƂȂ�A�x�Ƒ��Q�̑Ώۂƍl�����܂��B
�ł������ۂɂ́A��ł����������悤�Ɍl���Ƃ̔���グ�⏊���z�́A���̂������Ă����̔N�ɂ���ĕϓ����邱�Ƃ���ʓI�ł�����A����250���~�̂����̂ǂ̒��x�����̂ł̋x�Ƃɂ�镔���Ȃ̂��A�Ƃ����c�_���Ȃ���邱�Ƃ͂悭���邱�Ƃł��B
�]���āA���̋�̓I�Ȍ����z�܂��āA��Q�҂̕a��⎖�Ƃ̓��e�������Ă��A���̂Ƃ̑������ʊW���F�߂���͈͂����ɂ߂�K�v������܂��B
�Ƃ�����A���ꂪ�l���Ǝ�i�T�����[�}���ȊO�j�̋x�Ƒ��Q�̍l�����ƂȂ�܂��B
2.�Ԏ��̌l���Ǝ�̋x�Ƒ��Q
�Ԏ��̏ꍇ�́A�ȉ��́u��Q�v�̂悤�ȏ�Ԃ��l�����܂��B
�i����28�N�͎��̂ɑ����Ĕ��N�ԋx�Ƃ����Ƃ���j
�y��2�z����27�N 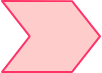
����28�N ����グ 1000 ����グ 500 ���㌴�� 500 ���㌴�� 250 �Œ�o�� 300 �Œ�o�� 300 �����o�� 400 �����o�� 200 ���� -200 ���� -250
�Œ�o��i�ƒ���ی����Ȃǁj�͋x�Ƃ��Ă��Ă�������܂�����A�ω�����܂��A����グ�┄�㌴���A�����o��͂��ꂼ�ꔼ���ƂȂ�A���̌��ʏ����́|200���~����|250���~�ƁA�����z���g�債�Ă��܂��B
���̂Ŏd�����ł��Ȃ��������ʁA�������傫���Ȃ����̂ŁA���̍��z���x�Ƒ��Q�z�ƍl���܂��傤�A�Ƃ������̂ł��B���̗�ł��������z��50���~���x�Ƒ��Q�z�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ٔ���ɂ���ẮA�u��Q�v�̎��̑O�̐��l�i����27�N�j�͏�����-200���~�����Œ�o��Ɋ|������300���~�����Z����v���X100���~���ƍl���A����100���~�ɋx�Ɗ��Ԃ̊����ł���5�����������u50���~�v���x�Ƒ��Q���A�Ƃ����l���������������̂�����܂��B
3.����ɐԎ��z���傫���ꍇ
�ꍇ�ɂ���ẮA����グ�ɑ���o��̊����������Ƒ傫���P�[�X�����蓾�܂��B���L�́u��3�v�ł��B
�y��3�z����27�N 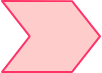
����28�N ����グ 1000 ����グ 500 ���㌴�� 800 ���㌴�� 400 �Œ�o�� 600 �Œ�o�� 600 �����o�� 800 �����o�� 400 ���� -1200 ���� -900
�Œ�o��ȊO�͔����ɂȂ������ʁA�x�Ƃ������Ƃɂ��Ԏ��z���k���������̂ł��B�Ԏ����Ƃ��c�ގ҂́A�x�Ƃ��邱�Ƃɂ���đ�����Ƃ���Ƃ�������������܂��B
���̂悤�ȏꍇ�̍l�����͔��ɓ���A����ł���肵�Ă���Ƃ͂�����������Ԃ̂悤�ł��B
�x�Ƃɂ�鑹�Q�͂Ȃ������ƍl����A�Ƃ������Ƃ����蓾�邩������܂��A�Ⴆ�Ζ��ʂɂȂ����Œ�o��݂̂Q�ƍl���āA����ɋx�Ɗ��Ԃ̊����������ĎZ�o����A�Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B
���̂悤�ɁA�ٔ���ł��l�X�ȎZ�o���@�A�F�茋�ʂ�����悤�Ȃ̂ŁA�����̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂��Ƃ������Ƃɂ��ẮA�����̂��Ƃ𗝉����������Ŏ����ɂƂ��ėL���ƂȂ�l�����Ȃǂ������o���Ă����K�v������Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ƒ��Ԃł͑ΐl�����͏o�Ȃ�!?�@�ł�������߂��!!�i�Ɛӎ��R�͌ʑΉ��j�i2017/10/17�j
- �Ɛӎ��R�ɊY�����Ă�������߂Ȃ�
�C�ӕی��̑ΐl�����ی��́A�ȒP�Ɍ����Ɣ�Q�҂����Q�҂̉Ƒ��������ꍇ�ɂ͎x�����܂���i�ƐӁj�B
�ی��̗p����g���čs���Ɓu��Q�҂��A��ی��҂̕���A�z��ҁA�q�̏ꍇ�ɂ͑ΐl�����͎g���Ȃ��v�ƂȂ�܂��B
��ی��҂Ƃ́A
�E�L����ی��ҁi�ی��̌_��ҁj
�E�L����ی��҂̔z���
�E�L����ی��҂܂��͔z��҂̓����̐e��
�E�L����ی��҂܂��͔z��҂̕ʋ��̖����̎q
�E�L����ی��҂̏������g�p��
�L����ی��҂�Ԃ̏��L�҂͎����Ƃ��܂��B�Ƒ������̎��̎Ԃ̎��̂Ŕ�Q�҂ɂȂ����ꍇ�A���̔C�ӕی��̑ΐl�����͎g���Ȃ��A�Ƃ����̂���{�I�ȍl�����ł��B
�ł��������ԕی��̏ꍇ�A�����ԑ��Q�����ۏ�@�̍l�����i�^�s���p�ҐӔC�j�����ƂɁA���Q�҂���Q�҂ɔ��������x�����Ƃ��������u��ی��҂���Q�҂ɔ��������x�����v�ƍl���A���ꂼ��̔�ی��҂��ƂɌʂɓK�p���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�ǂ��������Ƃ��A�ȉ��̗�ōl���Ă݂܂��B
����1��
���i�L����ی��ҁj�����̎Ԃ��^�]���Ă��Ď������̂��N�����A���悵�Ă������̎q�����d�������Ƃ��܂��B
���̏ꍇ�͔�Q�҂���ی��҂ł��鎄�̎q�Ȃ̂ŁA�ƐӂƂȂ�C�ӕی��̑ΐl�����ی�����̎x�����͂���܂���B����͕�����܂��B
�������̎��^�]���Ă����̂��A���̏����Ďg���Ă������̗F�l�i���l�j�������ꍇ�A���͋L����ی��҂Ȃ̂Ŕ�ی��҂ł����A���̗F�l���u�L����ی��҂̏������g�p�ҁv�Ƃ��Ĕ�ی��҂ƂȂ�܂��B���������̗F�l�Ǝ��̎q�͐e���W�ɂ͂���܂���̂ŁA���̏ꍇ�͖Ɛӎ�L�ɊY�������A���̕ی��̑ΐl�������g���Ď��̎q�ɑ��Ďx�������Ȃ���܂��B
����2��
�����}�X�I�����Ԃ������Ƃ��܂��B�����́u�Ȃ̗��e�v�Ɓu�Ȃ̂��傤�����v�Ɓu���ƍȂ̎q�v�ł��B���̉Ƒ��\������A�������P�g���C�ŕʋ������Ă��܂����B
���������P�g���C�̂܂܂ł����A���钷���x�ɂ̎��Ɏ��͎����L����ی��҂Ƃ��鎩���ԕی��ɓ����Ă��鎄���`�̎ԂŎ��Ƃɖ߂�܂����B�A�Ȓ��A���̎Ԃ��g���A���̍Ȃ������̎����̕���w�܂ő����čs���r���Ŏ������̂��N�����A�Ȃ̕ꂪ��������܂����B
���̏ꍇ�A��Q�҂͔�ی��҂ł��鎄�̍ȂƓ����̐e���Ȃ̂ŁA�Ɛӂőΐl�����ی��͎g���܂���B�ł����K��Łu��ی��҂��ƂɌʂɓK�p����v�ƂȂ��Ă���܂��B
���͋L����ی��҂Ȃ̂œ��R��ی��҂ł���A�����猩��ƍȂ̕�́u�����̐e���v�ł͂Ȃ��̂ŁA�Ɛӎ��R�ɓ�����܂����B
�]���āA���̏ꍇ�����_�Ƃ��Ă͑ΐl�����ی����x�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�ł�����Ƒ��ɂ����������Ă��܂����A��Q�҂������̉Ƒ�������ΐl�����ی��͎g���Ȃ��A�Ƃ����ɂ�����߂�̂ł͂Ȃ��A�悭��ǂ�Ō�������K�v������Ƃ������Ƃł��B
�����̎v�����݂�A���Ԉ�ʂɌ����Ă��邱�Ƃ����݂̂ɂ���̂ł͂Ȃ��A��x���Ƃɑ��k���Ă݂Ă��������B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

��ی��҂̈Ⴂ�i�����ӂƔC�ӕی��̑ΐl�����̔�r�j�i2017/10/13�j
- �����ӂ͑ΐl�����݂̂ł����A�u�����ӕی��v�Ɓu�C�ӕی��̑ΐl�����̕����v���r����ƁA�u��ی����v�������Ⴂ�܂��B
��ی��҂Ƃ́A�u���l���P�K�������Ƃ��ɕی����g����v�l�̂��Ƃł��B
�����ӂ̔�ی��҂́u�^�s���p�ҁv�u�^�]�ҁv�ƂȂ��Ă���A�C�ӕی��i�ΐl�����j��
�u�L����ی��ҁi�ی��̌_��҂ƍl��������ł��j�v
�u�L����ی��҂̔z��ҁv
�u�L����ی��҂܂��͔z��҂̓����̐e���v
�u�ʋ��̖����̎q�v
�u�L����ی��҂̏������g�p�ҁv
�ƖŒ�߂��Ă��܂��B
�C�ӕی��ɂ��u�L����ی��҂̏������g�p�ҁv�Ƃ������ڂ�����̂ŁA�����㎩���ӕی��Ƃقړ����l���ΏۂƂȂ�܂����A�����ӕی��̕������͈͂��L���ł��B
�ł����ł������I�ȈႢ�́A�u��Q�҂��N�Ȃ̂��ɂ���ĕی�����̎x��������������Ȃ������肷��v�Ƃ������Ƃł��B
�C�ӕی��̑ΐl�����ł́A�ȉ��̐l����Q�҂ɂȂ����ꍇ�͑ΐl�����̎x����������܂���B
�E�L����ی���
�E��ی������Ԃ��^�]���̎҂܂��͂��̕���A�z��҂������͎q
�E��ی��҂܂��͂��̕���A�z��҂������͎q
�E��ی��҂̋Ɩ��ɏ]�����̎g�p�l
�E��ی��҂̎g�p�҂̋Ɩ��ɏ]�����̑��̎g�p�l
���̂����A�����ӕی�������x�����������̂́A��Q�҂��u���Ȃ̂��߂Ɏ����Ԃ��^�s�̗p�ɋ�����҂���ѓ��Y�����Ԃ̉^�]�ҁv�̏ꍇ�ł��B������₷�������Ɓu�����Ԃ̎�����Ɖ^�]�ҁv�ƂȂ�܂��B
�܂��u�����ӕی��̕����K�p�����͈͂��L���v�̂ł��B
�C�ӕی��̑ΐl�����́A���̂悤�ɔ�Q�҂��N�Ȃ̂��ɂ���Ĕ͈͂����肳��Ă��܂��̂ŁA���ۂɂ͑ΐl�����̑��́u�l�g���Q�ی��v�ȂǁA�����ɑ���⏞�̕ی��ŕ���Ă���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����ӂ́u���ʊW�s���̌��z�v�Ƃ́i2017/9/19�j
- �����ӕی��́A�C�ӕی��̎x��������ʓI�ȑ��Q�����Ɣ�ׂāA��������Q�҂ɑ���~�ϑ[�u������Ă��܂��B
�u�d�ߎ����z�v�̐��x�������ł����A�����悤�Ȑ��x�Łu���ʊW�s���̌��z�v�Ƃ������̂�����܂��B
�u�d�ߎ����z�v�Ƃ́A�ߎ����E�����ɏd�ߎ�������ꍇ�Ɍ����ď����������z����A�Ƃ������x�ł��B
�ʏ�̑��Q�����́A��Q�҂ɂ��ߎ�������ꍇ�A���̕��͍��������āi���E���āj���Q�҂ɐ������邱�ƂɂȂ�܂��B�Ⴆ�Δ�Q�҂̉ߎ���30%�i�����Q�҂̉ߎ���70%�j�Ȃ�A��Q�҂͉��Q�҂ɁA�����̑��Q�̂�����70%���������ł���̂ł��B
�Ƃ��낪�����ӕی��ɂ��ẮA��Q�҂̋~�ϑ[�u�Ƃ��āu�ߎ��������Ă����E�����ɑS�z�x�����܂���B���������܂�ɂ���Q�҂̉ߎ��������ꍇ�i7���ȏ�j�Ɍ����āA���������i20������ő�50���j���z���܂���A�Ƃ���Ă���A���ꂪ�d�ߎ����z�ł��B
����Ǝ����悤�Ȑ��x�Ƃ��āu���ʊW�s���̌��z�v������܂��B����́u���̌�̌���Q�⎀�S�ɑ��āA�����ł����̂ƈ��ʊW������Αf�����z���܂����B�ǂ����Ă����ʊW�𗧏ł��Ȃ��ꍇ�ł��A50���������z���܂���v�Ƃ������x�ł��B
�f�����z�Ƃ́A������a�C�������Ă����l�����̂ɑ����āA���̌�Ɍ���Q���c�����莀�S�����肵���ꍇ�A���̌���Q�⎀�S�̌����̉��p�[�Z���g���͌��̕a�C�i�����ǁj�������Ȃ̂�����A���Q�z���炻�̕����������܂���A�Ƃ������̂ł��B
�Ƃ��낪�����ӕی��͔�Q�ҋ~�ς�ړI�Ƃ��Ă���܂��̂ŁA�f�����z�͂��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B
�u���S�A���邢�͌���Q�̌����̉��p�[�Z���g���͊����ǂ��������Ǝv�����ǁA�S�z�x�����܂���v�Ƃ������Ƃł��B
�������̌�̌���Q�⎀�S���A���̂������Ȃ̂����X�̕a�C�������Ȃ̂�������Ȃ��A�Ƃ����悤�ɁA���̂Ƃ̈��ʊW�����ł��Ȃ��ꍇ�A���������ƍٔ��⎦�k���ł́u���ʊW�s���̂��ߎx���z�[���v�ȂǂƂȂ肩�˂܂���B
�ł������̂悤�Ɏ��̂Ƃ̈��ʊW�����ł����ɕs���ȏꍇ�ł��A50���������z���Ă��Ƃ͎x�����܂��A�Ƃ����̂��u���ʊW�s���̌��z�v�Ƃ������x�ł��B
��ʎ��̂Ɍ��炸�A�ʏ�̑��Q�����ł͑��Q�͗����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł����A����𗧏�����Ȃ��Ă������ӕی��Ɋւ��Ă͋~�ϑ[�u������A�Ƃ������Ƃł��B
�ł�����A�Ⴆ�Έ�t�ȂǂɁu���̂Ƃ̈��ʊW�͕�����Ȃ��v�Ȃǂƌ����Ă��A�����ɂ�����߂�K�v�͂���܂���B
��������������ʊW�s���ł������ӂ���͔�������\��������܂����A�����ɂ���Ă͈��ʊW�����ł��邩������܂���̂ŁA��]�������܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

12��13����12��7���i�܂���12��6���j�̈Ⴂ�́H�i2016/2/2�j
- ���̂ʼn����̎O��߂̈�A�Ⴆ�Ђ��ߕt�߂����܂��A���ʓI�Ɋ߂̉��悪���������u�@�\��Q�v���c�����悤�ȏꍇ�A�����i��������Ȃ��������j�ɔ�ׂĊ����i�Ǐc�������j�̂Ђ��߂̉��悪3/4�ȉ��ɐ�������Ă���A����Q�����Ƃ���12��7�����F�肳���͂��ł��B
�ł����u�i�R�����j���搧��������̂ɓ������F�߂��Ȃ��H�v�ł����������悤�ɁA���搧��������ɂ��ւ�炸12��7�����F�肳�ꂸ�A�ɂ݂̏�Q�ł���12��13���Ƃ��ꂽ��A���邢�͊����Ɋ펿�I�������F�߂�����̂̑����l���킸����3/4�������߂�12��7���ł͂Ȃ�12��13�����F�肳��邱�Ƃ�����܂��B
����12���ł����A12��7����12��13���ō����o�Ă�����̂Ȃ̂ł��傤���B
12��7���i�@�\��Q�j���u�ꉺ���̎O��ߒ��̈�߂̋@�\�ɏ�Q���c�����́v�ŁA�펿�I�������F�߂�ꂽ�����ŌҁA�Ђ��A���߂̂����ꂩ�������ɔ�ׂĉ��悪3/4�ȉ��ɐ�������Ă���ꍇ�ɔF�肳��܂��B
12��13���i�_�o�Ǐ�j���u�Ǖ��Ɋ�łȐ_�o�Ǐ���c�����́v�ŁA�����Ɋ�łȒɂ݂₵�т�Ȃǂ̏Ǐc�����ꍇ�ɔF�肳��܂��B
���_���猾���ƁA����12���ł�12��7����12��13���ł͔����z�ɍ����o�Ă����̂����ʂł��B
�Ȃ��H�ǂ��ō������H
����Q�������F�肳���ƁA���̓����ɉ������u���LjԎӗ��v�Ɓu����Q�ɂ��편���v�v�����Q�ґ�����x�����܂��B
12���̏ꍇ�A�u���LjԎӗ��v�͓����ł����A�u�편���v�v�̍l������7����13���ł͈���Ă��܂��B
�편���v�Ƃ́A�u����Q���c���Ă��܂������߂ɈȑO�ɔ�ׂč���̘J���\�́i�܂�����j���������Ă��܂��B���́A����Q�̂��߂ɏ����������Ă��܂����������܂Ƃ߂ĕ����v�Ƃ������̂ł��B
��̓I�ɂ́A12���Ȃ�N����14�����A���㉽�N�����ɂ��ĕ����A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���͂����ΏۂƂȂ�N�����u���㉽�N���ƍl����̂��v�ł��B
12��13���́u�Ǖ��Ɋ�łȐ_�o�Ǐ���c�����́v�ł�����A��ȏǏ�͒ɂ݂ł��B�ނ��ł����͂��߂Ƃ��邱���u�ɂ݂̌���Q�v�́A��ʓI�ɂ́u������y������A���邢�͖{�l������Ă���v�ƍl�����Ă���A�u�ꐶ����Ȃ��v�ƍl�����Ă���12��7���́u�@�\��Q�v�ɔ�ׂ�ƁA�Ώ۔N���������Ă��܂��B
���ۂ̍ٔ��ł́A���̐l�̏ǏƂɑΏۂƂȂ�N�����ٔ��������f���܂��̂ő����ς���Ă��܂����A�ʏ�́u12��7���̋@�\��Q�̏ꍇ��67�܂Łi����҂́u���ϗ]���̔����v�j�v�A�u12��13���̊�łȐ_�o�Ǐ�̏ꍇ��5�N�`10�N�i������67�A���邢�͕��ϗ]���̔������邱�Ƃ͂Ȃ��j�v�Ƃ���Ă��܂��B
�܂�A�Ⴆ��40�̕�����ʎ��̂̉���Ō���Q����12�����F�肳�ꂽ�ꍇ�A�편���v��12��7���Ȃ�N����14����67�܂ł�27�N���A�ƂȂ�܂����A12��13���ł���ΔN����14����10�N���A�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�@���@�편���v�̏ڂ����v�Z���@�͂�����
����Q���c���悤�ȉ���Ɋւ��鑹�Q�����́A�편���v�����z�̑����̕������߂邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA����12���ł�7���ɂȂ�̂�13���ɂȂ�̂ł́A���Ȃ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
����Q�̐\��������O�ɂ����̒m����g�ɒ����Ă������Ƃ́A��L�̂悤�ȂɈ�������ʂƂȂ��Ă��邱�Ƃ��l����ƁA�ƂĂ��d�v�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂�
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���搧��������̂ɓ������F�߂��Ȃ��H�i2016/2/1�j
- ����Q�f�f���ɋL�ڂ��ꂽ�߉���̑����l����Q�F��̊�����Ă���ɂ�������炸�i�Ⴆ�Ђ��߂́u����/�L�W�v�̑����p�x�������ɔ�ׂĊ�����3/4�ȉ��ɐ�������Ă���̂Ɂj�A�����ӕی��i�����ӑ��Q�����������j����Y���ƔF�肷�邱�Ƃ�����܂�
����͈�t�ɂ����摪��l�̐M�p����F�߂Ȃ��A�Ɣ��f���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B
�����������������l���闝�R�́A�ȉ��̓�_���Ǝv���܂��B
�@������@���F���i����v�́j�ɏ]���ĂȂ���Ă��邩�ǂ��������Ƃ����ꍇ
�A�펿�I�����̓��e�Ɖ��搧���̓��e�Ƃɐ��������F�߂��邩�ǂ����i���茋�ʎ��̂��M�p�ł��邩�j�����Ƃ����ꍇ
������@�ɂ��Ăł����A���R�Ȃ������Q�����F��͑�����@���K���ł��邱�Ƃ��O��ł��B
�ł��������ӕی��i�����ӑ��Q�����������j�ł͑�ʂ̈Č����������钆�A�������s�����X�̈�t�̗͗ʂf�����������߁A�L�ڂ��ꂽ���l���ɐM�p�ł��Ȃ��ƍl���Ă���A�Ǝv���܂��B
�Ⴆ�Α����͈�t���㎈�≺�������킯�ł����A���҂͒ɂ݂�i���܂��̂ŁA������ǂ̒��x�䖝�����ċȂ��邩�͈�t�̔��f�ɂ��܂��B
���܂薳�������Đg�̂ɑ�����^���Ă͂����܂���̂ŁA�K���ȂƂ���ł���ȏ�͂������ĊԐڂ������Ƃ���߂�ł��傤���A���̒��x�����܂�ɂ��Â���A�������ʂƂ��Ă͈����l�ɂȂ�܂��B
���̂��߂Ɏ����ӑ��Q�����������Ƃ��ẮA���ۂɋL�ڂ��ꂽ�����l�����Ɍ������ʂƂ��Ď���ɂ����ƍl���Ă���A�Ǝv���܂��B
�����ő��肳�ꂽ������̐M�p���������邽�߁A���̂��Ƃ𗠕t����펿�����Ȃǂ̏������m�F���A���悪��������Ă��邱�ƂƂ̐������̃`�F�b�N���s���܂��B
����Q�f�f���ɋL�ڂ��ꂽ�����l�������F��̊�����Ă���ɂ�������炸�A�@�\��Q���۔F���ꂽ�ꍇ�A�ًc�\�����Ăł͂��̕����A�܂���搧���������I�ɐ����ł���펿�����Ȃǂ̏�����O��I�ɒT���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�܂��A�Ǐ�Œ莞�̑��茋�ʂ̐M�ߐ��Ƃ��ẮA���̎�����1��̌������ʂł͂Ȃ��A����܂ł̎��Ìo�߂̒��ʼn����摪��̌������Ȃ���Ă��邱�Ƃ��d�v�ł��B
����i���邢�͈�t���ւ�邽�тɁj���l������Ă���悤�ł͐M�p�����^���邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂��A����܂ł�����Ɖ��P���݂���悤�Ȃ�Ǐ�Œ莞�̑���l�ɂ��M�ߐ�������ƍl������ł��傤�B
�����o�N�ω���Ǐ�ɂ���Ắi�Ⴆ��RSD�Ȃǁj�A������舫�����邱�Ƃ����蓾�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�����𑍍��I�ɍl�����Ĕ��f����邱�ƂɂȂ�ł��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ԏӗ��ɂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����H�i�Ԏӗ��̎�ށj�i2016/1/27�j
- ��ʎ��̂ɑ����ĉ����������Q�҂͐F�X�ȑ��Q����܂����A���Ô��x�Ƒ��Q�ƈ���ĈԎӗ��͏����킩��ɂ��������ł��B
�Ԏӗ��͐��_�I�ȑ��Q�ƌ����܂����A�ǂ̂悤�Ȏ�ނ�����A�ǂ̂悤�ɋ��z�����܂��Ă���̂ł��傤���B
�Ԏӗ��́A�ׂ����l����ƁA�ȉ���4��ނ���܂��B

�E���Q�Ԏӗ�
�E���LjԎӗ�
�E���S�{�l�̈Ԏӗ�
�E�ߐe�҂̈Ԏӗ�
1.���Q�Ԏӗ�
����͌�ʎ��̂ʼn�����������Ƃɑ���Ԏӗ��ł��B
�ǂ̈Ԏӗ������_�I�A���̓I�ȋ�ɂɑ��鑹�Q�Ȃ̂ŋ��z�ɂ���͓̂���̂ł����A���Q�Ԏӗ��́u���Â����Ă������ԁv��u���ۂɓ��ʉ@���������v�Ɋ�Â��Čv�Z����܂��B�]���ď��Q�Ԏӗ��̂��Ƃ���ʉ@�Ԏӗ��Ȃǂƌ������Ƃ�����܂��B
�P���ɍl����A���Â��p�����Ă�����Ԃ������Ȃ�Ȃ�قǁA���ʉ@�̓�����������Α����قǁA���Q�Ԏӗ��͑����Ă������ƂɂȂ�܂��B
2.���LjԎӗ�
����́A���̂ɂ�����ɂ��Ĉ��̊��Ԏ��Â����Ă����肫�炸�Ɍ��ǂƂȂ�A�u����Q�����v���F�肳�ꂽ�ꍇ�Ɏx������Ԏӗ��ł��B
����Q�����ɉ����Ă����������z�����܂��Ă���܂����A���������ł��x�������i��ɕی���Ёj���l������LjԎӗ��ƁA��Q�ґ����l����ٔ���ł̌��LjԎӗ��ɂ͍�������܂��B
3.���S�{�l�̈Ԏӗ�
��ʎ��̂����S�����{�l�ɑ��Ă��A���S�̈Ԏӗ����x�����܂��B
�ȑO�́A���S���Ă��܂����l�͐��_�I����̓I�ȋ�ɂ͊����Ȃ����낤�A�Ƃ����悤�ȍl������A���҂̈Ԏӗ��͕s�v���Ƃ��ꂽ���オ����܂����B
���݂ł͎��S������Q�҂ɑ���Ԏӗ����A���Q�Ԏӗ�����LjԎӗ��Ƃ͕ʂɎx�����܂��B���ۂɂ͔�Q�Җ{�l�͎��S���Ă��܂��̂ŁA���S������Q�Ҏ��g�̈Ԏӗ������͔̂�Q�҂̑����l�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���z�́A��Q�Җ{�l���ƒ���Ŏ�Ɏ����Ă����u��Ƃ̎x���v�Ȃ̂��u��Ǝ�w�v�Ȃ̂��A�q���Ȃǖ��E�̐l�������̂��A�Ȃǂɂ���ĕς���Ă��܂��B
4.�ߐe�҂̈Ԏӗ�
���S���̂������ꍇ�́A���Q�҂����u���ڂ̔�Q�Җ{�l�ȊO�v�ł���A��Q�҂̋ߐe�҂ɑ���Ԏӗ��̔����`�����A���@711���Ō��߂��Ă��܂��B
���ڂ̔�Q�҈ȊO�̐l�̑��Q�����邱�Ƃ͈ٗ�Ȃ̂ŖY�ꂪ���Ȃ̂ł����A�ɖ��L����Ă��܂��̂ŁA�Y�ꂸ�ɐ������Ȃ���Ȃ�܂���B
�ߐe�҂Ƃ��A���@711���ł͔�Q�҂��u����v�u�z��ҁv�y�сu�q�v�ƂȂ��Ă��܂����A�ٔ��ł͂��傤�����̈Ԏӗ����F�߂��邱�Ƃ�����܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���Ə����ҁi�T�����[�}���ȊO�j�̋x�Ƒ��Q�i2016/1/24�j
- ���c�Ƃ⎩�R�ƂȂǁA�Ζ��悩�狋����������Ă���l�ȊO�̐E�Ƃ̐l�̋x�Ƒ��Q�͂ǂ��l����̂ł��傤���B
�T�����[�}���͎�Ɂu���������v�̌v�Z�ŁA��ЂȂNjΖ��悩�狋����������Ă���̂ŁA�u�x�����v�ŋx�Ƒ��Q�͌v�Z����A������₷���ł��B
�ł͌l���X�Ȃǂ̎��c�Ǝ҂������悤�ɍl���Ă����̂ł��傤���B
�x�Ƒ��Q�́A���̂ɂ�����̂��߂ɓ������A���ۂɉ������Ă��܂����������Ă邱�����ړI�ł�����A���c�Ǝ҂��T�����[�}���Ɠ����悤�ɍl����킯�ɂ͂����܂���B
���_�I�ɂ́A���c�Ǝ҂̋x�Ƒ��Q�́u�����̎��������������ꍇ�ɔF�߂���v�i�Ԃ��{���j�Ƃ���Ă��܂��B
�s���Y��݂��Ă��ĉƒ������Ă���l�Ȃǂ͉�������Ă�������������Ȃ��̂ŁA���̂悤�ȏꍇ�͔F�߂��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��������́u�������v�Ƃ͂����A�u���㌸�v�ł͂Ȃ��A�����i����j���珔�o��������������u�����v�����������A���x�Ƒ��Q�ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
���o��͍T������̂ł��B
�Ƃ͂����A�d�������Ȃ������i���X�ł����ΕX���Ă����j���Ԃ��������ꍇ�A�x��ł������߂Ɏg�p���Ȃ������o�������A�X���Ă��Ă��c�Ƃ��Ă��Ă�������o�������܂��B
�x��ł���Ύg��Ȃ��o���́A�Ⴆ�ΐ������M��i�①�ɂȂǂ͂����ςȂ��ł����j�A�ڑҌ��۔�A���ޗ���Ȃǂł��B
�x��ł��Ă��ς�炸������o��i�Œ��j�́A�Ⴆ�Ήƒ��A���Q�ی����A�d�Ō��ہA�����Ȃǂł��B
�����̌o��̂����A�x���Ԃł�������Œ��́A���Q�Ɋ܂߂Ă������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�܂莖�Ə����҂��A��ʎ��̂ɂ��x�Ƒ��Q�����Q�҂ɐ�������ꍇ�́A�����Ɍ����������z�ƁA���̊��Ԃɂ��������Ă����Œ������v���Čv�Z����K�v������Ƃ������Ƃł��B
������́A����⏊���������Ɍ����Ă��Ă��A�K���������̑S�Ă����̂̂��߂Ƃ͌���܂���̂ŁA�����������z�̂����̂ǂ̒��x�����̂ɂ��e���Ȃ̂��Ƃ��A�o��ɂ��Ă��ǂ̕������Œ��ƍl���Ă����̂��ȂǁA�X�ɓ��e����������K�v������A������Ɠ�������ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�L���x�ɂƑ�x�̎d�l�ŋx�Ƒ��Q�ɈႢ�H�i2015/6/8�j
- ������ƕs�v�c�ȋC�����܂���
�L���x�ɂ̏���͋x�Ƒ��Q�Ƃ݂Ȃ���邪��x�̏���͋x�Ƒ��Q�ł͂Ȃ�
�Ƃ���Ă��܂��B
��ʎ��̂̉���̂��߂Ɏd�����x�ꍇ�́u�x�Ƒ��Q�v���������A���Q�҂���x�����܂��B���̋x�Ƒ��Q�͎��ۂɋx�Ƃɂ�蔭���������Q�Ƃ������Ƃł����A�L���x�ɂ��g���Ēʉ@������×{�����肵���ꍇ���A�����͌���܂��L���x�ɂ͌���̂ŋx�Ƒ��Q�Ƃ��ĔF�߂��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�Ƃ��낪����̗×{��ʉ@����x��������ꍇ�ɂ́A��ʓI�ɂ͋x�Ƒ��Q�����������ƔF�߂��܂����B
����́A����������x�͈ȑO�x���i���j���Ȃǁj�ɏo�������̂ł��̑���ɕ����ɋx�ޓ����^����ꂽ���̂ł���A��x���g���Ēʉ@�����̂́A��Ђ̋x���ɒʉ@�������ƂƓ������A�ƍl�����Ă��邩��ł��B
�u�����Ɉړ��������j���ɒʉ@���������ł���v�Ƃ������Ƃł��B
����Ђ̋x���ɒʉ@�����ꍇ�ɂ͋x�Ƒ��Q�͔������܂���B
�ł�����A�L������x������l�������ɒʉ@�̂��߂ɉ�Ђ��x�ނ̂ł���A����L�������Ɏg�����Ƃ������߂��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����ސE�Ɖ��قł͋x�Ƒ��Q�ɈႢ�͏o�Ă���H�i2015/6/5�j
- ���̂̉���̂����Ŗ����ɓ������ސE������Ȃ����͋C�����A����ސE�Ɖ��قł͋x�Ƒ��Q�ɈႢ�͏o�Ă���̂ł����H
��ʎ��̂ɂ����䂪�����ŁA�x�Ƃ������Ȃ�����ȑO�ǂ���ɓ����Ȃ����߂ɉ�Ђ����߂���Ȃ��A�Ƃ����ɂȂ邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�͉\�Ȍ�������ސE�ł͂Ȃ������Ƃ����`�ɂ��Ă��炢�܂��傤�B
���Ò��ɉ�Ђ����߂�ƁA�����i�܂��͏Ǐ�Œ�j�܂ł̊��Ԃ̋x�Ƒ��Q�����ƂȂ�܂��B
��Ђ����߂���̊��Ԃɂ��Ă͉�Ђ���́u�x�Ƒ��Q�ؖ����v�����s����܂���A�̒��x��d���̓��e�Ȃǂ��瑍���I�ɔ��f���A�ސE�Ǝ��̂Ƃ̊Ԃɑ������ʊW���F�߂���x�Ƒ��Q���x������͂��ł��B
���̑������ʊW�̏ؖ����ǂ����邩�ł����A�����葁���͉̂�ЂɈ�M�����Ă��炤���Ƃł��B
���̂̉���̂��߂ɑސE����̂ł���A����ސE�ł͓���ł������قȂ��Ђɂ��̗��R�����ʂɂ��Ă��炢�₷���Ȃ�Ƃ������Ƃł��B
�������A��Ђ��ؖ��������ʂ�����ΕK���F�߂���Ƃ͌���܂��A�F�߂�ꂽ�Ƃ��Ă����x�͋x�Ƃ̊��Ԃ��ǂ̒��x���̖�肪�o�Ă��܂��̂ŁA�C�����ɕ��i�̗l�q�������Ɏ�邱�Ƃ𑱂��܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

6�����玩�]�ԂɌ�����!?��������@�{�s�i2015/5/29�j
- ����27�N6��1������������H��ʖ@���{�s����܂����A�����́u���]�Ԃɏ��Ƃ��͂����Ɛ^���ɁI�v�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
�V�������܂�́A��̓I�ɂ͈ȉ��̂Ƃ���ł��B
�@�i14�Έȏ�́j���]�ԉ^�]�҂��댯�s�ׂ��J��Ԃ����ꍇ�i3�N�ȓ���2��ȏ�j�A�s���{�������ψ���玩�]�ԉ^�]�҂Ɂu�u�K����悤���߁v���Ȃ���܂��B
�A���߂Ɉᔽ���u�K���Ȃ��ꍇ�ɂ͔����ɏ�����܂��B
�u�K��3���ԂŎ萔��5,700�~�A�ᔽ�����ꍇ�̔�����5���~�ȉ��ł��B
�����Ď��]�ԉ^�]�ҍu�K�̑ΏۂƂȂ�댯�s�ׂƂ́A�ȉ���14�̍s�ׂł��B
�i����@108��3��4�j
�@�E�M������
�@�E�Ւf���ؗ�����
�@�E�w��ꏊ�ꎞ�s��~��
�@�E�����ʍs���̒ʍs���@�ᔽ
�@�E�u���[�L�s�ǎ��]�ԉ^�]
�@�E�𐌂��^�]
�@�E�ʍs�֎~�ᔽ
�@�E�����ʍs���̏��s�ᔽ
�@�E�ʍs�敪�ᔽ
�@�E�H���ђʍs���̕��s�҂̒ʍs�W�Q
�@�E�����_���S�N�U�`���ᔽ��
�@�E�����_�L���ҖW�Q��
�@�E������_���S�i�s�`���ᔽ��
�@�E���S�^�]�`���ᔽ
���]�Ԃ̌�ʃ��[���ᔽ�⎩�]�Ԏ��̂̐[���������ɂȂ��Ă��܂�����A����͂�ނȂ�����Ȃ�ł��傤�ˁB
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���̏ňӌ����H���������H�i2014/12/25�j
- ���̂̏ɂ��Ď��̓����ґo���̈ӌ����Ⴄ�悤�ȏꍇ�A�ǂ������炢���ł��傤���B
���̌�������邱�Ƃ��l�����܂����A�����������Ă���ƌ���ɏ؋����c���Ă��Ȃ����Ƃ������ł����A��͂莖�̒���Ɏ����������s�����A�x�@�̋L�^���m�F����̂���Ԃ��Ǝv���܂��B
��ʎ��́i�l�g���́j����������ƁA���̎��̌���̊NJ��̌x�@�������������s���܂��B
�x�@�̎��������ł́A���̌���ňʒu�W���m�F���Đ}�ʂɗ��Ƃ����u��ʎ��̌��ꌩ��}�v���������ŁA���̌���̏���������u�������������v�����܂��B���̌㓖���҂ɘb���āu���q�����v�Ȃǂ��쐬���A���������킹�āu�Y���L�^�v�Ƃ����܂��B
�x�@�̎����������ɂ͔�Q�҂��~�}�Ԃʼn^��Ă��Č���ɂ��Ȃ����߁A���Q�҂̈ӌ��̐g�Ɋ�Â��č���邱�ƂȂǂ�����A�K�������S�Đ��m�Ƃ����Ȃ��ꍇ������悤�ł����A��{�I�ɂ͍ł��M���ł��鎑���ł��B
�Y���L�^�i�������������j�̓��ʂȂǂ�����͓̂����ҁi�܂��ٌ͕�m�j�Ɍ���܂����A��ʎ��̏ؖ���������ΕK�v������������܂��̂Ŏ擾���邱�Ƃ��\�ł��B
�܂��A��ʎ��̏ؖ����́u���̏Ɖ�ԍ��v�̗��ɊNJ��̌x�@���Ǝ��̏Ɖ�ԍ����L�ڂ���Ă��܂��B���̌x�@���ɓd�b�����āA���̎��̂��u�ǂ��̌��@�����v�u�����v�u�扽���̑����ԍ��v�ő���ꂽ�̂����܂��B
���̂��߂ɓ`���邱�Ƃ́u���������v�u�����ꏊ�v�u���Q�҂̎����Ɛ��N�����v�ł��B�����͑S�Č�ʎ��̏ؖ����ɋL�ڂ���Ă��܂�����A�����`����Όx�@���̕��ł͑����ԍ����������Ă����A�Ƃ����킯�ł��B
���̌�A�������ꂽ���@���ɘA�������āA
�u�����x�@�����瑗���ԍ����Ԃő��v���ꂽ�������i���Q�Җ��j�A������������Ɋւ��鎖���ɂ��āA�L�^�̓��ʉ{�����������̂ł����v
�Ɛ\���o��A���@���̕��ł�����ׂ��[�u���Ƃ��Ă���܂��̂ŁA������͌��@���̎w���ʂ�ɂ���L�^�̓��ʂ����炦��A���邢�͉{�����ł���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���@���ɂ���āA��x�\���݂ɍs���Č���ʂ̓��ɃR�s�[�����炦��Ƃ����A�d�b�Ő\������ł����ē�����x�����s�������Ƃ���A���邢�̓R�s�[�̓_�������ǎʐ^���Ƃ邱�Ƃ͋����A�܂��̓R�s�[���ʐ^���_�������ǁA���̏�Ŏ����ŏ����ʂ����Ƃ͋����A�ȂǁA�Ή��͗l�X�ł�����A���̌��@���̎w���ɏ]���Ă��������B�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

��ʎ��̂̎��ÂɘJ�Еی����g�������b�g�i2014/6/7�j
- �J�Еی����g�����Ƃ͔�Q�҂ɂƂ��ă����b�g������܂��̂ŁA�g����ł�����Ўg���Ă��������B
��ʎ��̂ŘJ�Еی����W���Ă���̂́A�Ɩ���܂��͒ʋΓr��ɂ����Č�ʎ��̂Ŏ��������ꍇ�ł��B���̂悤�ȏꍇ�ɐ��{���J���҂̕ی�̂��߂ɁA�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�Ɋ�Â��āA����������l��⑰�ɑ��ċ��t���s���Ƃ������̂ł��B
��ȋ��t�́A���Ô��x�ƕ⏞�i�ʏ�̋��^��6���j�A����Q���c�����ꍇ�̏�Q���t�A���S�����ꍇ�̈⑰���t�Ȃǂł��B
�����͂�������A�J�Ђ���x�����Ȃ������ꍇ�ɂ͉��Q�҂��x�������ƂɂȂ�܂��̂ŁA�u�ł͘J�Ђł͂Ȃ����Q�҂�����炦��������Ȃ����v�Ƃ��l�����܂��B
�ł����J�Ђ���́A���Q�҂���͎x�����Ȃ��u���ʎx�����v���x�����܂��B����͘J���������Ƃ̈�Ƃ��āA�x�ƕ⏞���t�A��Q�⏞���t�̑��ɁA�J�Еی��݂̂���u���������v�̂悤�Ȍ`�Ŏx��������̂ł��B
�܂��d�ĂȌ��ǂ��c�����ꍇ�́A����ɘJ�Еی��݂̂���x�����鋋�t�����傫���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�ʋЊQ�A�J���ЊQ�ł̌�ʎ��̂̏ꍇ�́A�K���J�Еی����g���悤�ɂ��܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�x�@�ɒʕȂ��ł���Ǝ��̑���Ɍ���ꂽ��i2014/5/14�j
- ���N�i2014�N�j��GW�A���͏�֎����ԓ��ŏa�ɂ͂܂��Ă��܂����B
�����ł�������ł���̂ɁA�����Ă���ƘH���ɎԂ�2��A�c�Ɏ~�܂��Ă��܂����B���̉����������ʉ߂��Ă���Ƃ��Ɍ������̂́A�Ȃ�ƁI
��̎Ԃ̉^�]��Ǝv����j�̐l���O�Ɏ~�܂��Ă���Ԃ̐l�ɂ�����n���Ă���Ƃ���ł����I
�����炭�Ǔ˂��Ă��܂����̂��Ǝv���܂����A�����ɎԂ̗l�q������ƁA����ʂ�߂��鎞�ɂ݂�����ł͂ւ��݂��Ȃ����A�����������������炢�������̂ł��傤�B
���̂̑��肪�u���Q�ُ͕�����̂Ōx�@�ɂ͓͂��Ȃ��ʼn������v�ƌ����Ă��邱�Ƃ��A���܂ɂ���܂��B���̏ꍇ�͉ߋ��̈ᔽ�⎖�̂������āA�Ƌ��̈ᔽ�_�������肬�肾�Ƃ������Ƃ̂悤�Ȃ̂ŁA�ʏ펄�́u�y���ڐG���̂łǂ��l���Ă��Ԃ������C����������������Ɗm�M�ł���ł��Ȃ�����A���ۂ��Ă��������v�Ƃ��b�����Ă��܂��B
�x�@�ɓ͂��Ȃ��ƌ�ʎ��̏ؖ��������s���ꂸ�A�ی����̎x����������ɂȂ��Ă��܂�����ł��B
�Ƃ͂����A�a�̐^���������A���炩�ɒN����������Ă��炸�Ԃ̏C�������s�v�̂悤�Ɍ����邱�̂悤�Ȏ��̂ł���A�u�܂��A��������ˁc�v�Ƃ��������ł��傤���B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����ӂ�7�����Z�Ƃ́H�i��t�̐f�f���ւ̏������ЂƂňԎӗ���7����������H�j�i2014/5/13�j
- �����ӂ̈Ԏӗ��́A�f�f���̎��ÍŏI�����u���������v�u���~�v�u�]��v�܂��́u�p���v�ƂȂ��Ă���ꍇ�A���ÍŏI����7�������Z���ĈԎӗ����v�Z���܂��B
�܂�A�Ō�̐f�f���Ɉ�t���u�����v�Ɂ���t���邩�A�u���~�v�Ɂ���t���邩�����̈Ⴂ�ŁA�Ԏӗ���7�����ς���Ă��܂��̂ł��B -
���Ê��Ԃ̍l���� �N�Z��
�i���ÊJ�n���j�@ ���̌�V���ȓ��Ɏ��ÊJ�n�����ꍇ�́A�u���̓��v�����ÊJ�n���Ƃ��܂��B
�A ���̌�W���ȍ~�Ɏ��ÊJ�n�����ꍇ�́A�u���ÊJ�n���O7�������Ê��Ԃɉ��Z�v���܂��B�܂����ÊJ�n����7���O�����ÊJ�n���ƂȂ�܂��B ���Â̒��f
�i�]��ȂǂŎ��Â𒆒f�����ꍇ�j�@ ���Â̒��f���Ԃ��P�S���ȓ��̏ꍇ�A���̒��f���Ԓ��̓��������Ê��ԂɊ܂߂܂��B �A ���Â̒��f���Ԃ��P�T���ȏ�ɂ킽��ꍇ�́A�����̎��Ê��ԂƍĎ��Ê��Ԃɕ������ē����̎��Ê��ԂɂV�������Z���܂��B �B ���f���Ԃ�15���ȏ�ɂ킽��ꍇ�ł��A�����Ë@�ւœ��ꏝ�a�ɂ����Ìp�����Ă��鎞�́A�ʎZ���đS�������Ê��ԂƂ��đΏۓ����ɂ��܂��B�������A���ʊW�ɋ^�`������ꍇ�͏�����܂��B �ŏI�� �@ �f�f���̎��ÍŏI�����u���������v�u���~�v�u�]��v�܂��́u�p���v�ƂȂ��Ă���ꍇ�A���ÍŏI����7�������Z���܂��B �A �u�������v�����ÍŏI������V���ȓ��̏ꍇ�A�u�������v���ŏI���Ƃ��܂��B �B �u�������v�����ÍŏI������W���ȍ~�̏ꍇ�A���ÍŏI���ɂV�������Z���܂��B - �ʉ@�ȊO�ňԎӗ��Ώۓ����Ƃ����ꍇ
�@���Ǎ��y�ѐҒ��̍��܁E�ό`���ŃM�v�X�����Ă���Ƃ� ���Ǎ��Ƃ́A�㎈�Ȃ�u��r���E�����E�ڍ��v
�����Ȃ�u��ڍ��E�����E�C���v�A���Ǎ��ɐڑ�����O��ߕ����̍��܁E�ό`���Œ��Ǎ����܂߃M�v�X�����Ă���Ƃ� �O��ߕ����Ƃ́A�㎈�Ȃ�u���b���E�����E�荪���v
�����Ȃ�u�����E�p���E�����E�G�W���E�����E�����E�������v�B�̊��M�v�X�p���Ă���Ƃ� �̊��M�v�X�Ƃ́A�Ғł̈��ÌŒ�̂��߂ɓ����ɑ����������� ���Ԏӗ��Ώۓ����Ƃ����M�v�X�Œ�̓M�u�X�V�[�l�A�M�u�X�V���[���A���q�i�V���[�l�j
�i�|���l�b�N��z���̃R���Z�b�g�A�������܌Œ�тȂǑΏۂƂ���܂���j���M�v�X�Œ肵�Ă���Ƃ��ɓ��ʉ@���������ꍇ�͏d�����đΏۓ��Ƃ͂��܂���B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���Q�����Œj���ɍ��H�i2014/4/12�j
- ��ʎ��̂̑��Q�����ł́A�j���ō�������̂ł��傤���B
���͐��N�O�܂ł́A��ɏ��Ղ��c�����ꍇ�̌���Q�ɒj���̍�������܂����B
�Ⴆ�Ί��4cm�i3cm�ȏ�5cm�����j�̐���̏��Ղ��c�����ꍇ�A2011�N4���܂ł́A�������Ղł��j�Ȃ�u�j�q�̊O�e�ɏX����c�����́v�Ƃ���14�����F�肳��A���Ȃ�u���q�̊O�e�ɏX����c�����́v�Ƃ���12�����F�肳��Ă��܂����B
�����ӂ̌��x�z�ł�14����75���~�ɑ���12����224���~�ƁA�������̑傫���Ȃ̂ɂ��Ȃ�̍��ł��B
����͕s�������Ƃ������Ƃ�2011�N5���ȍ~�͒j���̍��������Ȃ������Ƃ́i�j���Ƃ�12���ł��j�A�����m�̕��������Ǝv���܂��B
���̑��A�Ԏӗ��͂��Ƃ��ƒj���ɍ��͂���܂��A���ł��j���ō������鍀�ڂ�����܂��B������편���v�ł��B
�편���v�́A���S��������ǂ��c�����ꍇ�Ɂu�{�����S���Ă��Ȃ���i���ǂ��c��Ȃ���j��������ꂽ�͂��̎������A���Q�҂ɔ������Ă��炤�v�Ƃ������̂ł��B
����́A���̂ɑ������O�̔�Q�҂̎����������ƂɌv�Z���܂����A��Q�҂��w����Ǝ��]���҂Ȃǎ��ۂɎ����������A���z���ؖ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�ɂ͒����̓��v��������u�����Z���T�X�v���u���ϒ����v���g�����ƂɂȂ��Ă��܂��B
����͌����̒j���N��ʂ̕��ϒ����̓��v�Ȃ̂ŁA�����̕����Ⴂ���z�ɂȂ��Ă���܂��B�܂��A�E���Ă��Ȃ�20�̊w�������S�����ꍇ�A���̈편���v���v�Z����Ƃ��́A��ʓI�ɂ��j�Ȃ�u�j���̕��ϒ����v�A���Ȃ�u�����̕��ϒ����v�Ōv�Z����܂��̂ŁA�편���v�ɂ͂��Ȃ�̍������Ă��܂��܂��B
�܂��d���ɂ��Ă��Ȃ��A����20�̖��ł��A�j���ō������Ă��܂��Ƃ������ƂȂ̂ł��B����ߑR�Ƃ��Ȃ��̂́A�������ł͂Ȃ��͂��ł��B
�����܂�ɁA�j�ł����ł��u�i�j�����v�����j�S�J���ҕ��ϒ����v�ň편���v���Z�o����ٔ��Ⴊ�o�Ă��܂��B�ł�������͂��̗���ɂȂ�̂��ǂ����͕�����܂���B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ی���Ђ����k��s�ł��Ȃ����́H�i2014/4/7�j
- ����̎��̂ɔ����Ď����ԕی��ɓ����Ă���̂ɁA�ی���Ђ����k��s���Ă���Ȃ����Ƃ�����܂��B�����
��Q�҂̉ߎ����[���̏ꍇ
�ł��B��Q�҂������Ԃɏ���Ă��鎞�Ɏ����̂ł��A�ł��B
���k��s���s���C�ӕی���Ђ́A����ɑ��Ĕ����ӔC�̂���ی��_��҂ɑ����đ���ɂ������̂ŁA�ی��_��҂�㗝���Ď��k�������Ă��܂��B
�ł����ی��_��҂ɉߎ����Ȃ���A����Ɏx�����������͔������܂���B�ł�����u�ی��_��҂���Q�҂ł����āA������̉ߎ����[���Ȃ�Εی���Ђ͎��k���ł��Ȃ��v�̂ł��B
�ǂ̂悤�ȏꍇ���Ƃ����ƁA��Ɉȉ��̂悤�Ȏ��̂̂Ƃ��ł��B
�E �ԐM����a�Œ�Ԓ��ɁA����Ɍ�납��Ǔ˂��ꂽ�B
�E ���ԏ�ɒ��Ԓ��ɁA����ɂԂ���ꂽ�B
�E ���肪���S�ɐԐM���E�������M���̌����_�ł��݂����i�����ďՓ˂����B
�E �Ό��Ԑ��̑��肪�A�Z���^�[���C����傫���I�[�o�[���Ă������߂ɏՓ˂����B
������ɑS���ߎ����������߂ɕی���Ђ����k��s���Ă���Ȃ��I�H
�����Ȃ̂ł��B���߂Ă̎��̂őS���m����������Q�҂Ƃ��ẮA���̂悤�ȂƂ��ɂ͎����̎Ԃ��������Ă���u�l�g���Q�ی��v���g���Ď����̕ی���Ђɂ����b�ɂȂ�����A�u�ٌ�m��p���S�ۓ���v���g���Đ��Ƃɑ��k����Ȃǂ��āA�����ɕs���Ȍ��A���ʂɂȂ�Ȃ��悤�ɓw�߂܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���Q�z150���~�����ߎ�����50������ꍇ�̎x���z�́H�i2014/3/7�j
- �p�D����Q�͖����������A���Q�z�����Ô�70���~�A�x�Ƒ��Q20���~�A�ʉ@�Ԏӗ�60���~�̍��v150���~�������B������̉ߎ���50�����邪�A���葤�ی���Ђ���̎x�����͂�����H150���~�H120���~�H75���~�H
�`�D���Q�����i���́j�Ŕ�Q�҂Ɖ��Q�҂����k���̘b������������ꍇ�ɁA�o���ɉߎ�������悤�ȂƂ��A���Q�҂���x�����锅�����z�́A�ߎ����E����āu���Q�҂̉ߎ����v�݂̂��x�����܂��B
�ߎ���50�������Q�҂̑S���Q�z��150���~�������ꍇ�A���ʂɍl�����50�����ߎ����E�����75���~�����x�����܂���B�ł�����ʎ��́i�����Ԏ��́j�̏ꍇ�͎����ӕی�������A�u�C�ӕی���Ђ͎����ӕی�����x��������z��������Ďx���������Ă͂Ȃ�Ȃ��v���ƂɂȂ��Ă��܂��B
�����ӕی��ł͔�Q�҂̉ߎ���7���ȏ゠��ꍇ�łȂ��Ǝx���z�̌��z�͂���܂���B
�ł�����u��Q�҂̑��Q�z��150���~�ʼnߎ���50���������ꍇ�A���Q�҂��x�����ׂ����Q�����ӔC��75���~�ł����A�����ӕی�����120���~�x�����܂��̂ŁA���ʓI�Ɏx��������z��120���~�v�ƂȂ�܂��B
�u�ߎ����E�i7�������j��̋��z��120���~�������ꍇ��120���~���x������v�Ƃ������Ƃł��B
150���~�̑��Q�ʼnߎ�������50���ł������A���z��120���~�������̂�20�����i�����̉ߎ�20���Ɠ����j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ł�����Q�҂ɂƂ��ďd�v�Ȃ��Ƃ́A���̓���ł��B
�{���ł����75���~�ƂȂ��Ă��܂��Ƃ���A�����ӂ��������̂�120���~�ł܂������A���͂��̂���70���~�́A���Ô�Ŏg���Ă��܂��Ă��܂��B
��Q�҂ɉߎ����������邩��Ƃ����āA�a�@�����Ô�̎x������Ə����Ă����킯�ł͂Ȃ��̂ł��B
�܂�120���~�̂����A�x�Ƒ��Q�A�Ԏӗ��Ƃ��Ĕ�Q�Ҏ��g�����̂́A���Ô�������������c���50���~�ł��B
���E�O�̑��Q�z�͋x�Ƒ��Q20���~�ƈԎӗ�60���~�̍��v80���~�������̂��A50���~�i80���~�ɑ���62.5���������̉ߎ�37.5���Ɠ����j�ɂȂ��Ă��܂��܂����B
���̂悤�Ȃ��Ƃł�����A�����ɉߎ��������ꍇ�ɂ́A���Ô�����k���邽�߂Ɍ��N�ی����g�����Ƃ��������܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���k�����n�߂�܂łɏ������Ă������Ɓi2014/2/21�j
- ���̂ɑ������o�����قƂ�ǂȂ���Q�҂̕��́A���k���J�n�̃^�C�~���O�͂Ȃ��Ȃ�������܂���B
�ł�����ʏ�́A���Q�ґ��i�̕ی���Ёj���u���낻�늮�����Ǝv����̂Ŏ��Â��I�����Ă��������v�Ƃ��u���낻��Ǐ�Œ肾�Ǝv���̂Ō���Q�̐\�������Ă��������v�Ȃǂƌ����A���̂܂܈����������k���ɓ����Ă������Ƃ��Ǝv���܂��B
�\�\���낻�뎡�Â��~�߂�i�܂��͌���Q�̐\���́j�����Ȃ̂��H�\�\
���̗���ɏ���Ă����ƁA�ی���Ђ���u����Q�����ɂ͊Y�����܂���ł����v�u�ł������ꂾ�������܂��v�Ƃ����A���Q�����z�i���k���z�j�̒�Ă�����܂��B
�\�\����Q�ɂ͊Y�����Ȃ��̂��E�E�E�\�\
�\�\���k���z�͂��ꂮ�炢�Ȃ̂��\�\
�l���ŏ��߂āi�܂���2��ځA�܂���3��ځj�̎��̂ɑ����ď��肪�킩��Ȃ���Q�҂́A�u�����������̂��E�E�v�Ɨ���ɔC���Ă��܂��܂����A����Q�������������z���A������������u�����������́v�ł͂Ȃ���������܂���B
�������������́A�F�肳�ꂽ����Q�����͑Ó��Ȃ̂��A�ی���Ђ���������z���Ó��Ȃ̂��A�Ƃ��������Ƃ��A�C���^�[�l�b�g�⏑�ЁA���邢�͌�ʎ��̂̐��Ƃɑ��k����Ȃǂ��Ē��n�߂܂��B
�����ď��߂āu���������̂ł͂Ȃ��̂��ȁH�v�ƋC�Â��܂��B
���̎��_�ŏ��������������ƂɋC�Â��Ă��A�����Ď�x��ł͂���܂��A�����ƑO����s�����n�߂�ƁA�����Ƃ������ʂɌ��т��܂��B
�ł�����u�������g�ł����Q�����ɂ��ĕK�v�Ȓm����g�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����S�\�������Ă����ׂ��ł��B�ł��邾�����������ɁB
����i�ی���Ёj�̓v���Ƃ��Ăǂ�ǂ��Ƃ�i�߂Ă����܂����A��Q�҂̗���ł͂����̍�Ƃ��K�������������A�Ó��Ȃ��̂Ƃ͌���܂���B�ł����m������ǂ����ƁA�S�Ă������ɉ���Ă��܂��܂��B
�u����ǂ�Ȃ��Ƃ��N����̂��v�Ƃ����s�����傭���邽�߂ɂ��A����̂��Ƃ�������x�\�z�ł�����x�܂Œm����t���邱�Ƃ��]�܂����Ǝv���܂��B
�����͂����Ă��A�����I�ɂ͓�����Ƃł��B
����Ȏ��́A�����Ŗ₢���킹���ł���̂ł���ΐ��Ƃɖ⍇�����Ă��܂����Ƃł��B
���T�C�g�i��ʎ��̃T�|�[�g�Z���^�[�j�ł������߂��Ă���̂́A���T�C�g���܂߂������́u���Ɓv�ƌ�����Ƃ���ɓ�����������Ă݂邱�Ƃł��i���[���Ȃ�R�s�y�łł��܂��j�B
��������Ƃ��̉̎d������e�̈Ⴂ�ŁA�ǂ�����ԐM���ł���̂��������Ă���Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ߎ�������ƁA���炦�锅���������邾���ł͍ς܂Ȃ��H�i2014/2/7�j
- ��������Q�҂ɂȂ��Ă��܂������ǂ�����ɂ��ߎ�������ꍇ�A���Q�z�̂����ߎ��̊�����������������Ă��瑊�肩��x�������A�Ƃ������Ƃ͕�����Ǝv���܂��B�ł������ꂾ���ł͍ς܂Ȃ����Ƃ�����܂��B
�Ⴆ�Δ�Q�҂����]�Ԃɏ���āA�M���̂Ȃ������_�Ŏl�֎ԂƏo�������ɏՓ˂����������̂̏ꍇ�A�l�֎Ԃ��L�H�i�L�����H�j�Ŏ��]�Ԃ����H�i�������H�j�������Ƃ���ƁA��{�ߎ������́@���]�Ԃ�30���A�l�֎Ԃ�70���@�ł��B
���̎��̂Ŏ��]�Ԃɏ���Ă�����Q�҂݂̂���������āA���̉���̎��Ô��Ԏӗ��Ȃǂ̑��Q�z��500���~�������Ƃ��܂��i���]�Ԃ̏C��������܂ނƍl���܂��j�B
��Q�҂̉ߎ���30���Ȃ̂ŁA500���~��30���A150���~�����������ꂽ�c���350���~���A���肩��x�����܂��B�ł�������ŏI���ł͂���܂���B
���]�ԂƎl�֎Ԃ̎��̂̏ꍇ�A�l�֎Ԃ̕����A�^�]��͉�������Ă��Ȃ��Ă��Ԃ̓_���[�W���āA�C�����K�v�ƂȂ邱�Ƃ������ł��B
���ɎԂ̏C�������50���~�������Ă����Ƃ���ƁA�����C�����50���~�̂����A��Q�҂̉ߎ�����30���i15���~�j�͔�Q�҂̐ӔC�Ȃ̂ŁA��Q�҂����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�u�������͔�Q�҂Ȃ̂ɉ��Q�҂̏C������́I�H�v
�Ƌ����������ӊO�Ƃ�������Ⴂ�܂����A�����Ă悭�l���Ă݂�A�݂Ȃ�����܂��B
����قǁA�ߎ��̊������ǂ��Ȃ邩�͏d�v�Ȃ��ƂȂ̂ł�
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ߎ������͒N�����߂�̂��i2014/2/6�j
- �ߎ������i�ߎ����E���j�́A��Q�ґ��Ɖ��Q�ґ��ƂŎ咣���H���Ⴄ�ꍇ������܂��B���������ߎ������͒N�����߂�̂ł��傤���B
���_�I�Ȃ��Ƃ��������u�ٔ��������߂�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A�S�Ă̎��̂��ٔ��ɂȂ�킯�ł͂���܂���B
�ł�����ʏ�͎��k���������u��Q�ґ��Ɖ��Q�ґ������݂��b�������Č��߂�v���ƂɂȂ�܂��B
�ƌ����Ă�����������������ԂŎ咣���Ă��b�������ɂȂ�܂���A�b�������̎����Ƃ��āA�~�ς��ꂽ�ٔ�����Q�l�ɍٔ�����ٌ�m��܂Ƃ߂��Z�������\����Ă��܂��B
���ꂪ - �u������ʑi�ׂɂ�����ߎ����E���̔F���i�S��4�Łj�E�ʍ�����^�C���Y��16���v��u������ʎ��̑i�ב��Q�����z�Z���i�Ԃ��{�j�v
�Ȃǂł��B
�@�@�@���@�ߎ������̔��f�
�ߎ����������߂�̂͌x�@�ł��ی���Ђł��Ȃ��A�����ׂ����ƂɁu�b�������Ō��߂�v�킯�ł�����A��������Ƃ����m����g�ɒ�����K�v������̂��Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ǐ�Œ�͒N�����߂�̂��i2014/1/31�j
- �Ǐ�Œ�Ƃ́A��w�I�Ȗʂ�����u����ȏ㎡�Â𑱂��Ă��啝�ȉ��P�������߂Ȃ���ԂɂȂ�����ԁv�Ƃ���Ă��܂��B
����Ɠ����ɁA���Q�����̖ʂ��猩��ƁA�u���Q�z�Z��̊�_�v�ƍl�����܂��B
���Q�����ł́A�Ǐ�Œ�O�́u���Q�����v�A�Ǐ�Œ�Ȍ�́u���Ǖ����v�ƂȂ�܂��B���Q�����̑��Q�ɂ́A���Ô��ʉ@��ʔ�A�x�Ƒ��Q�A���Q�Ԏӗ��Ȃǂ�����A���Ǖ����ɂ͌��LjԎӗ��A�편���v�A����p�Ȃǂ�����܂��B
��Q�҂̕��������I�Ȉ�ۂ����̂́A�u���Ô�̎x�������Ǐ�Œ莞�܂Łv�Ƃ����Ƃ���ł��傤�B
�Ƃ���ł����u�Ǐ�Œ�̎����v�����߂�̂́A�N�Ȃ̂ł��傤���B
�����̕��́A�ی���Ђ���u���낻��Ǐ�Œ�Ȃ̂Ŏ��Ô��ł���܂��v�Ȃǂƌ����A����Q�f�f���������Ă���A�Ƃ����o�������Ă��܂��B���邢�͌���Q�f�f���Ȃǂ͑���ꂸ�A���ǂ̘b�͈����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����悤�ł��B
�ł�����w�I�Ȗʂł̏Ǐ�Œ�͈�t���f�f���邱�Ƃł���A�����ďǏ�Œ�̎��������Q������A���ɏd�v�ȈӖ��������܂�����A���̃^�C�~���O�͈�t�Ƒ��k���Ȃ���A��Q�҂����߂邱�ƂȂ̂ł��B
�ی���Ђ����߂邱�Ƃł͂���܂���B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�f�f���������Ă��炤�̂́A���܂ł������Ă����a�@�łȂ��ƃ_���H�i2014/1/29�j
- �_���Ȃ��Ƃ͂���܂��A��ʓI�ɂ͂���܂Ŏ��Â��Ă�����t�Ɍ���Q�f�f���̍쐬�����肢����̂����ʂł��B
�ł������炩�̗��R�i��t��������̌����Ǐ�Ɏ���݂��Ȃ��Ƃ��A�܂Ƃ��ȓ��e�̌���Q�f�f���������Ă���Ȃ��Ƃ��A���������u����Ȃ��̏����Ȃ��I�v�ƌ����Ă���Ƃ��j�ł��C���ł��Ȃ����Ȉ�t�ł���A����T���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B
�ł������̏ꍇ�́A�����Ȃ菉�Ζʂ̈�t�Ɍ���Q�f�f���̂��肢�͂ł��܂���A�������琔��A1�`2�����͒ʉ@�𑱂���K�v������܂��B
��������Q�f�f���쐬���������ē]�@����̂ł���A���߂ɍs���������������Ǝv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�f�f���͂������Ă��炦��́H�i���Ê��ԂU�����o�߂��Ȃ��ƌ���Q�̐\���͂ł��Ȃ��ƕ��������j�i2014/1/28�j
- ����Q�̒��x�͏Ǐ�Œ肵�����ɕ]�����s���i������Q���������߂�j���ƂɂȂ��Ă���A�]�����s��������
�@��w��Ó��ƔF�߂�����Ԃ�҂��ĕ]�����邪
�A�Ǐ�̌Œ�̌����݂�6�����ȓ��̊��Ԃɂ����Ă��F�߂��Ȃ����̂ɂ����ẮA�×{�̏I�����ɂ����ĕ]������
���ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@��w��Ó��ƔF�߂�����Ԃ��A6�����ȓ��̊��Ԃɂ��Ă̂��Ƃł����A����͎w�̌����Ȃ��u�펿�I�ȏ�Q�v�̂��Ƃ��ƍl��������ł��B
���̏ꍇ��6�����o�߂��Ă��Ȃ��Ă����ɖ߂炸�ǏŒ肵�����Ƃ�������܂��B
�_�o��Q�i�ɂ݂Ȃǁj���@�\��Q�i�߂̓����̏�Q�j�ɂ��ẮA����\��������܂��̂ŁA�A�̂悤��6�����Ԃ͗l�q�������A�������Ȃ������ȍ~�̑Ó��Ȏ����ŏǏ�Œ�ƍl���܂��B
�]���āu����Q�̐\����6�����ȏ�o�߂��Ă���v�Ƃ����l�����ɂȂ��Ă��܂��B
�ł����炩�Ȃ��G�c�ɂ�����
�u�_�o��Q�A�@�\��Q�̌���Q�̐\���́A��6�����ȏ�o�߂��Ă���v
�u�펿�I�ȏ�Q�̐\����6������҂��Ȃ��Ă��\�����Ă��悢�v
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�Ȃ��A��t�ɂ��肢�����3�����̎��_�ł�4�����̎��_�ł�����Q�f�f���������Ă���܂����A��L�̂Ƃ���\�����Ă��Ǐ�Œ�O�Ƃ��ē����͔F�肳��܂���A�u3�����A4�����ŏ����ꂽ����Q�f�f���̓��_�Ȃ��́v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�x�Ƒ��Q�ɂ��āi2014/1/27�j
- ��ʎ��̂ʼn�������Ă��d�����x�ނ��Ƃɂ���ċ����i�����j���������ꍇ�ɂ́A������u�x�Ƒ��Q�v�Ƃ��ĉ��Q�҂ɐ����ł��܂��B
���ۂɎ������������������ׂ������Ă��A��Ј��i�ߐl�j�̕��ŗL���x�ɂ��g�p���ċx�ꍇ��A��Ǝ�w�Ƃ��ĉƎ��ɏ]�����Ă�������A�x�Ƒ��Q�̐������\�ł��B
�����Đ�Ǝ�w�Ńp�[�g��A���o�C�g�����Ă�����́A���̃p�[�g��A���o�C�g�œ������^�̎��т����āA��Ǝ�w�Ő����v�Z�����ꍇ�Ɣ�r���āA�ǂ��炩�L���ɂȂ���Ő����ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
��ȕK�v���ނ́A
�E��Ј��̏ꍇ�͉�Ђ��L�ڂ����x�Ƒ��Q�ؖ����ƌ����[
�E���c�Ƃ̏ꍇ�͊m��\�����̍T��
�E�Ǝ��]���҂̏ꍇ�͉Ƒ����̋L�ڂ�����Z���[
�ȂǂƂȂ��Ă���܂��B
���炦�Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă�����Ǝ�w�̋x�Ƒ��Q���A�ӊO�ƍ��z�ɂȂ����肵�ċ�������A�������炦�Ȃ��ƌ����Ă���w���⎸�Ǝ҂̏ꍇ���l������ؖ��̎d���ɂ���ċx�Ƒ��Q�����炦���肷�邱�Ƃ�����܂��B
�x�Ƒ��Q�������ł��邩�ǂ��������ȏꍇ�A�������鏑�ނ��悭������Ȃ��ꍇ�Ȃǂ��A������߂��ɂ����k���������B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ٗp�ی��̊�{�蓖�i���ƕی��j���Ɏ��̂ɑ������ꍇ�A�x�Ƒ��Q�́H�i2014/1/18�j
- ���ƒ��Ōٗp�ی��i���ƕی��j��������Ă���悤�Ȏ����ɁA�Ⴆ�Όォ��Ǔ˂���鎖�̂ɑ����Ăނ��ł��ɂȂ����ꍇ�A�x�Ƒ��Q�⎸�ƕی��̋��t�͂ǂ��Ȃ�̂ł��傤���B
���_�Ƃ��Ă��u��{�I�ɂ͌ٗp�ی��͂��炦�Ȃ����A���̑���Ɏ��̂̑���i���Q�ҁj����x�Ƒ��Q���x������v�܂��͂��̋t�A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�ٗp�ی������邽�߂ɂ́A�A�E����ϋɓI�ӎv�Ƃ��ł��A�E�ł���\�͂����邱�Ƃ��K�v�Ƃ���Ă��܂��B
���Q�҂���u�x�Ƒ��Q�v���x������Ƃ������Ƃ́A�����Ȃ��Ƃ������Ƃł�����A���̊Ԃ̌ٗp�ی��̎x���͒�~����܂��B�ł����ʉ@���Ă��Ă���ɏA�E�ł����ԁi�y���Ȃǁj�ł���A�ٗp�ی��͎x�������̂ł��B
���������̏ꍇ�͉��Q�҂���̋x�Ƒ��Q�̎x�����͂���܂���A���炦��̂́u�ǂ��炩����v�ł���A��d�擾�͂ł��܂���B
���̍l�����́u��ʎ��̂̉���̂��߂Ɏd�������߂���Ȃ��Ȃ����v�ꍇ�����l�ł��B
�Ȃ��A�ٗp�ی��̎��Ԃ͌����Ƃ��ė��E���̗�������1�N�ł����A����Ȃǂ̂��߂Ɉ�������30���ȏ㓭�����Ƃ��ł��Ȃ��ꍇ�ɂ́A�n���[���[�N�ŏ���̎葱�����Ƃ邱�ƂōŒ���3�N�ԁA���Ԃ��������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɂȂ��Ă���܂��̂ŁA�d���Ŏ��Â������������Ȏ��ɂ͂��̎葱��������Ă����܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���k���ƈԎӗ��̈Ⴂ(2013/12/25)
- ��ʎ��̂́A���k���ƈԎӗ����Ăǂ��Ⴄ�̂��낤�B�Ƃ����^����������ł͂���܂��H
���_�I�Ȃ��Ƃ������Ɓu�Ԏӗ��͎��k���̈ꕔ�ł����v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���k���́A��ʎ��̔�Q�҂̑S�Ă̑��Q�����z�Ɋ��Z���āi�����Q�������j�A��Q�ҁA���Q�ґo�������ӂ������z�̂��Ƃł��B
��Q�҂̑��Q�̒��ɂ́A���Ô�A�x�Ƒ��Q�A���@�G��A�ʉ@��ʔ�ȂǂƋ��ɁA���_�I�ȋ�ɂ����K�Ɋ��Z�����u�Ԏӗ��v���܂܂�܂��B
�܂�A�Ԏӗ��Ƃ͎��k���i���Q�������j�̈�̍��ڂł���A�Ƃ������Ƃł��B
���k���Ƃ́A��Q�҂Ɖ��Q�ҁi�̕ی���Ёj�����k���z�����߂�b�������̂��Ƃł��B����́u�Ō�ɂ�����x�����ĉ������邩�v�̘b�������Ȃ̂ŁA��Q�҂̃P�K���������Ă���i�܂��͏Ǐ�Œ肵�Č���Q���������܂��Ă���j�n�߂܂����A���Ô�Ȃǂ̎���͕�����₷���̂ɑ��āA�Ԏӗ��͘b�������Ō��܂邠���܂��ȋ��z�ł��B
�ł������u�Ԏӗ��z�̑����m���Č����邱�Ɓv ���A���̂̌o���̏��Ȃ���Q�҂ɂƂ��ĂƂĂ��d�v�Ȃ��ƂȂ̂ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�߂̋@�\��Q�Ɖ���(2013/12/9)
- �߂̋@�\��Q�i�^����Q�j�́A�߂̋Ȃ���p�x�i����Ƃ����܂��j����������Ă����i���܂�Ȃ���Ȃ��Ȃ��Ă���j���x�ɂ���āA���߂��܂��B
�Ⴆ�Ώ㎈��3��߁i���A�r�A���j�≺����3��߁i�Ҋ߁A�G�A����j�̋@�\��Q������Q�̑ΏۂƂȂ�ꍇ�A���̊߂̉���𑪒肵�āA���E�ŏ�Q���c���Ă��Ȃ����̊߂̉���ɔ�ׂāA��Q���c���Ă�����̊߂̉��悪�ǂ̒��x��������Ă��邩�i���搧�������܂�Ȃ���Ȃ��Ȃ邱�Ɓj�ɂ���āA�ȉ��̂悤�ɓ��������܂��Ă��܂��B
�i���E�́j������������̊߂̉��悪��������Ă��Ȃ����ɔ�ׂ�
�u1/2�ȉ��Ȃ�w�������@�\��Q�x�Ƃ���10���v
�u3/4�ȉ��Ȃ�w�i�P�Ȃ�j�@�\��Q�x�Ƃ���12���v
�Ȃǂł��B
�������O��Ƃ��āu���̂ɂ��߂̓�������������錴���ƂȂ�펿�I�����i�ߕ����̍��܌�̖����s�ǁA�ߎ��ӑg�D�̕ϐ��ɂ��ߍS�k�A�_�o�̑����Ȃ��j�������Ă���v���Ƃ��K�v�ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���O�F��Ɣ�Q�Ґ���(2013/12/4)
- ���O�F��Ɣ�Q�Ґ����Ƃ́A����Q�̐\���̎d���̈Ⴂ�̂��Ƃł��B
���O�F���Ƃ́A����܂Ŏ��Â̎x�����Ȃǁu�C�ӈꊇ�v���Ă����C�ӕی���ЂɁA����Q�\���̎葱���Ȃǂ��������Ƃł��B
����ɑ�����Q�Ґ����́A�i����܂ŔC�ӈꊇ�Ή����Ă��Ă��j�C�ӕی��ɗ��܂��ɔ�Q�҂��璼�������ӕی��Ɍ���Q�̐\���葱��������葱���̂��Ƃł��B
���O�F��́A�C�ӕی���Ђ̒S���҂���Ë@�ւ���摜���W�߂��菑�ނ��W�߂��肵�Ă����̂ŁA��Q�҂ɂƂ��Ắu�ƂĂ��y����v�Ȏ葱���ł��B
����ɑ��Ĕ�Q�Ґ����́A�����Ŏ����ӂ��珑�������āu�\�����ށv���쐬������A��ӏؖ���������Ă����莖�̂̏�������鏑�ނ���������Ë@�ւ��玩���ʼn摜���W�߂Ă����肷��ȂǁA�v����Ɏ�Ԃ��������ĔώG�ł��B
�ł͔C�ӕی���Ђ�����Ƃ��͏�Ɏ��O�F��ɂ���悢�̂ł́H
�����A����Q�F��͑��Q�����ɑ傫���e�����邱�ƂȂ̂ŁA�C�ӕی��ɗ���Łi���O�F��j�A�S���҂Ɂu�ςȂ��Ɓv�����ꂽ���Ȃ��A���邢�͎����ł��ׂĂ��m�F���Ȃ����肽���A�Ƃ����ꍇ�ɂ́A��Q�Ґ����Ō���Q�̐\��������̂ł��B
�u�ςȂ��Ɓv�Ƃ́A�ی���Ђ̌ږ��̗]�v�Ȉӌ�����t������A�ꍇ�ɂ���Ă͕K�v�Ȃ��̂�t���Ȃ������肵�āA����Q���������ɂ����Ȃ�悤�ɂ��邱�Ƃł��B
- ����Q�̐\���葱���ɂ��Ă܂Ƃ߂��
�E���O�F���E�E�E�C�ӕی���ЂɎ葱���𗊂ށB�y�����ǕςȂ��Ƃ������̂ł́H
�E��Q�Ґ����E�E�E�����Ŏ����ӕی��ɐ\������B�葱�����Ƃ��ώG�Ŏ�Ԃ������邯�ǁA�C�ӕی���ЂɕςȂ��Ƃ������S�z�͂Ȃ��B
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��ʎ��̃T�|�[�g�Z���^�[�ł́A��Q�Ґ����������߂��Ă���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ی�������Ƙb���܂Ƃ܂�Ȃ��܂��̂���3�N�o�������ł��i�����̖��j(2013/11/26)
- ���Q�����������i���Q�҂���Q�҂̕ی���Ђɐ������錠���j�̎�����3�N�ł��B
��Q�҂������̐l�g���Q�ی��ɐ���������A���Q�҂������̎����ӕی��ɉ��Q�Ґ����������肷��u�ی��������v��3�N�Ŏ����ł��B
�ł͂�����3�N���A�ł����A�@���I�Ɍ������u���肪����F�߂��Ƃ��v����3�N�ł��B��̓I�ɂ́A�u����i���Q�ҁB�ی���Ђ��܂ށj����ꕔ���ł���Q�҂��x���������Ƃ��v�u����i�ی���Ёj�������z�̒�āi���z�̒j�̏��ʂ��Ō�ɂ��ꂽ�Ƃ��i�����ł��j�v�Ȃǂł��B���̑��Ɍ���Q�������F�肳�ꂽ�ꍇ���u�Ǐ�Œ���v����3�N�ł��B
��L�̑S�Ă̏o�����̂����A��ԍŌ�̂Ƃ�����3�N�������ł��B
�ł�����ʏ�A���Q�҂̔C�ӕی���Ђƌ��ǂ���z�̘b�����������Ă������A�����̐S�z�͂���K�v�͂���܂����B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����F��̃��[���E���d(2013/9/3)
- 1.��ȏ�̌���Q���c�����ꍇ�ɂ������A
2.�����@�{�s�ߕʕ\���y�ё��ɒ�߂��Ă��Ȃ�����Q���c�����ꍇ�ɂ������A
3.���̔����O�Ɋ��ɏ�Q���������ꍇ�ɂ����d�A
�Ƃ������戵���ɂ��A����Q���������߂��Ă����܂��B
�{���́A�����ɂ��Đ����������܂��B
���Ɍ���Q�̂������l����ʎ��̂ɂ�蓯�ꕔ�ʂɂ���ɏ��Q���A����Q�̒��x���d���Ȃ邱�Ƃ��u���d��Q�v�Ƃ����܂��B
���ɂ���������Q�́A��ʎ��̂������̂��̂Ȃ̂��ǂ����Ƃ��������Ƃ�₢�܂����B���̏ꍇ�A���d��̌���Q�̕ی����z��������̌���Q�̕ی����z���T�������z�����x�Ƃ��ĕی������x�����܂��B
�Ⴆ�A���ɕЕ��̉����𑫊߂��玸���Ă����l�i5���j���A���̌㎖�̂œ��ꉺ�����Ђ��߂��玸���Ă��܂����i4���j�ꍇ�A�u���̐l�̌���Q��4���ł����A���Ƃ���5���̏�Q���������̂ŁA���̕��͍��������čl���܂��B�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�����ӂ̌��x�z�Ō����ƁA4����1,889���~�ł����A��������5����1,574���~�������������u315���~�v���x���z�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�����F��̃��[���E����(2013/9/2)
- 1.��ȏ�̌���Q���c�����ꍇ�ɂ������A
2.�����@�{�s�ߕʕ\���y�ё��ɒ�߂��Ă��Ȃ�����Q���c�����ꍇ�ɂ������A
3.���̔����O�Ɋ��ɏ�Q���������ꍇ�ɂ����d�A
�Ƃ������戵���ɂ��A����Q���������߂��Ă����܂��B
�{���́A�����ɂ��Đ����������܂��B
����Q�����\�i�����@�{�s�ߕʕ\���y�ё��j���Y�����Ȃ�����Q�ɂ��Ă��A���̒��x�ɉ������e�����Ɂu�����v������̂Ƃ��ē������߂邱�ƂƂ���Ă���܂��B�ȉ���2�̃P�[�X������܂��B
�@�������Q�������Ȃ����Q�̌n��ɂ������Ȃ��ꍇ
�E�k�o�r���□�o�E���i12���j
�E�k�o���ށi14���j
�E�O�����U���i11���A12���A14���j
�A�������Q��������n��͂��邪�A�Y���������Q���Ȃ��ꍇ
�Ⴆ�A�����߂̗p��p���i8��6���j�A�Ȃ������Ђ��߂ɒ������@�\��Q���c�����i10��10���j�ꍇ�A����n��̒��ŕ����̕��@��p���āA�d������8����1�����N������7�������Ƃ��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�����F��̃��[���E�����i2013/8/30�j
- 1.��ȏ�̌���Q���c�����ꍇ�ɂ������A
2.�����@�{�s�ߕʕ\���y�ё��ɒ�߂��Ă��Ȃ�����Q���c�����ꍇ�ɂ������A
3.���̔����O�Ɋ��ɏ�Q���������ꍇ�ɂ����d�A
�Ƃ������戵���ɂ��A����Q���������߂��Ă����܂��B
�{���́A�����ɂ��Đ����������܂��B
�n��̈قȂ镡���̌���Q���c�����ꍇ�A�u�����v���s���čŏI�I�ɂ�1�̓������߂܂��B�����̎�茈�߂́A�ʕ\���̌���Q�ɂ��āA�ȉ��̂悤�ɂȂ��Ă���܂��B
�@5���ȏ�̌���Q��2�ȏ�c�� �� �d�����̓�����3�J��グ��
�A8���ȏ�̌���Q��2�ȏ�c�� �� �d�����̓�����2�J��グ��
�B13���ȏ�̌���Q��2�ȏ�c�� �� �d�����̓�����1�J��グ��
�C14���̌���Q�������c�� �� 14��
�Ȃ��A�ʕ\���̌���Q�ɂ��ẮA�ʌn��̕����͍s���܂���B
��ԏd������ 1�`5�� 6�`8�� 9�`13�� 14�� ��
��
�d
��
��
��1�`5�� �d������
+3��6�`8�� �d������
+2���d������
+2��9�`13�� �d������
+1���d������
+1���d������
+1��14�� �d������ �d������ �d������ 14��
���݂Ȃ��n��
�n��̈قȂ镡���̌���Q���c�����ꍇ�ł��A���L�̓��ꕔ�ʂɎc�����ꍇ�ɂ́A����̌n��Ƃ݂Ȃ��Ď戵�����Ȃ���܂��B
�@���ዅ�̎��͏�Q�A���ߋ@�\��Q�A�^����Q�A�����Q�̊e���݊�
�A����㎈�̋@�\��Q�Ǝ�w�̌������͋@�\��Q
�B���ꉺ���̋@�\��Q�Ƒ��w�̌������͋@�\��Q
���g�ݍ��킹������
�n�قȂ�A���ʂ��قȂ镡���̌���Q���A�ʁX�̌n��Ȃ̂ł�����O�I�ɂ܂Ƃ߂ĕ]�����܂��傤�A�Ƃ����K��ł��B
�㎈�A�����͍��E���ʌn��ł����A
�E���㎈���Ђ��߈ȏ�Ŏ���������
�E����̎�w�̑S���̗p��p��������
�E�������̗p��S�p��������
�E���������X�t�����߈ȏ�Ŏ���������
�Ȃǂɂ��ẮA�����ł͂Ȃ��g�ݍ��킹�����ƂȂ�܂��B
�������ł��Ȃ��P�[�X��
�����ł��Ȃ���O�I�ȃP�[�X�Ƃ��ẮA�ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
�@�����̌���Q�ɊY������悤�Ɍ����邪�A1�̏�Q���̊ϓ_�ŕ]�����Ă���ꍇ
�Ⴆ�A�E��ڍ��ɕό`���c���i12��8���j�A�E������1cm�Z�k�����i13��8���j�ꍇ�͕������ꂸ��ʓ����ł���12��8�����F�肳��܂��B
�A1�̌���Q�ɑ��̌���Q���ʏ�h������W�ɂ���ꍇ
�Ⴆ�A��r���ɋU�߂��c���i8��8���j�A�Ȃ������̕��ʂɊ�łȐ_�o�Ǐ���c�����i12��13���j�ꍇ�́A��ʓ����ł���8��8�����F�肳��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�̌n��̎�茈�߁i2013.7.8�j
- ����Q�����̔F���ł́A�g�̕��ʁE��Q�ԗl�ŃO���[�v���������Ă���܂��B���̃O���[�v���u�n���v�Ƃ����܂��B
�Ⴆ�Ή��L�́u��Q�n��̕\�v�ł͍ŏ��ɊႪ�o�Ă��܂����A��̏�Q�́A�ዅ�̏�Q�Ƃ܂Ԃ��̏�Q�̓�ɋ敪����āA�ዅ�̏�Q�̒��ł�����Ɏ��͏�Q�A�����@�\��Q�A�^����Q�A�����Q�Ȃǂɕ�����Ă��āA����炪���ꂼ��ʂ̌n��Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
����Q��2�ȏ�c�����ꍇ�A�u�����v�Ȃǂ��s���ČJ��グ�čŏI�I��1�̓����ɕ]�����܂����A���̏ꍇ�͎c������Q���ǂ́u�n��v�ɑ����邩�ɂ���ĕς���Ă��܂��̂ŁA�n��𗝉����邱�Ƃ��d�v�ł��B
��Q�n��̕\ ���� ��Q�̓��e �n��
�ԍ��� �ዅ�i����j ���͏�Q 1 ���ߋ@�\��Q 2 �^����Q 3 �����Q 4 �܂Ԃ�(�E���͍�) �������͉^����Q �E�@5
���@6�� ������(�����j ���͏�Q 7 ���k�i�E���͍��j ������Q �E�@8
���@9�@ �����y�ы@�\��Q 10 �� �y�ь���@�\��Q 11 �����Q 12 �_�o�n���̋@�\���͐��_ 13 �����A��ʕ��A�� �X���Q 14 ����������
�i�O���B����܂ށj����������̏�Q 15 �̊� �Ғ� �ό`���͉^����Q 16 ���̑��̊��� �ό`��Q�i�����A�����A�낭���A���b�����͍��Ս��j 17 �㎈ �㎈(�E���͍��j �������͋@�\��Q �E 18
�� 21�ό`��Q�i��r�����͑O�r���j �E 19
�� 22�X���Q �E 20
�� 23��w(�E���͍��j �������͋@�\��Q �E 24
�� 25���� ����(�E���͍��j �������͋@�\��Q �E 26
�� 30�ό`��Q�i��ڍ����͉��ڍ��j �E 27
�� 31�Z�k��Q �E 28
�� 32�X���Q �E 29
�� 33���w(�E���͍��j �������͋@�\��Q �E 34
�� 35
���̃y�[�W�̐擪�ց�

����Q�̒�`�i2013.7.5�j
- ����Q�Ƃ́A��ʎ��̂ɂ����
�@�������Q���������Ƃ��g�̂ɑ������Q��
�A��ʎ��̂Ƃ��̏Ǐ�Œ��ԂƂ̊Ԃɑ������ʊW������A
�B���̑��݂���w�I�ɔF�߂�����̂ŁA
�C���̒��x�������@�{�s�߂̓����ɊY���������
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@�́u���Q���������Ƃ��v�Ƃ́A����ȏ㎡�Â��p�����Ă����̌��ʂ����҂ł��Ȃ���ԂŁA�c�����Ǐ��R�I�o�߂ɂ���ē��B����ƔF�߂���ŏI��ԁi�Ǐ�Œ��j�ɒB�����Ƃ��������܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

��Q�⏞�N���i�J�Еی��̏�Q����7���ȏ�j�ƈ편���v�A�ǂ��炪���炦��́H�@�i2013/6/14�j
- ��ʎ��̂ɂ����䂪�����A�܂��͏Ǐ�Œ肵���̂��A���Q�ґ��̕ی���Ђɑ��Q��������������ꍇ�A����܂ł����J�Еی����狋�t���Ă����Ƃ�����A�����J�Еی�����̋��t���͍T�����Đ������܂��B
�Ⴆ�Ό���30���~�̐l�����̂ɂ������1�����d�����x�ꍇ�A�������ĉ��Q�ґ��Ǝ��k�������鎞�_�ł́A�J�Еی�����x�ƕ⏞�Ƃ���30���~��60���Łu18���~�v�����Ɏx�����Ă��邱�Ƃ������ł��B
���̂悤�ȏꍇ�ɔ�Q�҂��x�Ƒ��Q�̐���������Ƃ�����A1����30���~�̂����A�J�Еی����狋�t���Ă���18���~���T�����āA12���~�����Q�ґ��ɑ��Q���������������ƂɂȂ�܂��B
�܂�u���Q�ґ�����̑��Q�������ƁA�J�Еی�����̋��t�̓�d�擾�͂ł��Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B
�Ƃ���ŕs�K�ɂ��Č���Q���c�����Ƃ��A�J�Еی����g���Ă����ꍇ�ɂ́A����Q�����̐\����J�Еی��Ǝ����ӕی��i�����ԕی��j�̗����ɍs���܂��B
���̑O��50�ŔN����800���~�i���t��b���z��18,000�~�Ƃ��܂��j����������j����Q�҂��A�����J�Ђ������ӂ��A�ǂ�����u����Q7���v���F�肳�ꂽ�Ƃ��܂��B
�����ӕی������7������1051���~�x�����܂����A�ٔ����̊�Ȃǂōl����ƁA
���LjԎӗ��@1000���~
�편���v�@�@5050���~�i��800���~56���~11.274�j
�ŁA���v��6000���~�ƂȂ�܂��̂ŁA���Q�ґ��Ɣ�Q�ґ��ō��ӂ���A����Q����������6000���~���x�����܂��B
����A�����ɘJ�Еی��̕��ł�7�����F�肳��Ă��܂��B
�J�Еی���7���́u��Q�⏞�N���i��Q�N���j�v�ƂȂ�A1�N�Ԃŋ��t��b���z��131�����i��236���~�j���x�����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
������͔N���Ȃ̂ŁA��Q�҂͎��S����܂ł��炦�邱�ƂɂȂ�܂��B
�E���Q�҂���̑��Q��������6000���~�i�ꎞ���j
�E�J�Еی�����͖��N236���~���A���S����܂�
�����A��ق��u���Q�ґ�����̑��Q�������ƁA�J�Еی�����̋��t�̓�d�擾���ł��Ȃ��v�Ɛ������܂������A���̂悤�ɘJ�Ђ̕����N���ɂȂ����ꍇ�A�ǂ��l����̂ł��傤���B
�J�Ђ��疈�N236���~���炢�A���ꂪ6000���~�ɂȂ�̂�26�N��ł��B
�u���Q�҂���6000���~�����炢�A�J�Еی�����̏�Q�⏞�N���̎x����26�N�ォ��n�܂�H�v
�u�J�Еی�����̎x�����n�߁A26�N�ȓ��Ɏ��S������6000���~�ɒB���Ȃ��̂ŁA���̍��z�����Q�҂��x�����H�v
�u���Q�҂���̔�����67�܂łƂ������ƂɂȂ��Ă��邩��A68����J�Ђ̎x�����n�܂�H�v
�����ł͂���܂���B���ۂ̎�舵���́A
�u��Q�҂����Q�҂��瑹�Q�������ꂽ�ꍇ�i��̗�ł�6000���~�j�A���̌�J�Еی������7���ɑ����Q�⏞�N����3�N���o�߂�����Ɏx������v
�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
��Q�⏞�N����3�N����708���~�i236���~�~3�N�j�ł�������܂��A���k�̎���6000���~������Ă����Q�҂ɑ��āA�J�Еی��̏�Q�⏞�N����4�N�ڂ���͎x������Ƃ������Ƃł��B
�ȉ��̒ʒB�Ɋ�Â��Ă���܂��B
�i�ʒB�j�@��41.6.17�610��
�ЊQ������3�N���o�߂����Ƃ��́A���̎x����~�z�����Q�����z�ɖ����Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A�ی����t�͊J�n�����B
���̒ʒB�̂��ƂƂȂ�͈ȉ��̂Ƃ���B
�J�Еی��@
��\����̎l
�Q �@�O���̏ꍇ�ɂ����āA�ی����t����ׂ��҂����Y��O�҂��瓯��̎��R�ɂ��đ��Q���������Ƃ��́A���{�́A���̉��z�̌��x�ŕی����t�����Ȃ����Ƃ��ł���B
��̗�ł����ƁA3�N����708���~�͍T������܂����A����ȍ~�͊��ɉ��Q�҂���x�����Ă��鑹�Q�������ɉ����A�J�Еی��̏�Q�⏞�N���ƁA��d��肷�邱�ƂɂȂ�܂��B�������ނȂ��A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B
���̂悤�Ȃ��Ƃ�����܂��̂ŁA�Ɩ��゠�邢�͒ʉ@�r��̌�ʎ��̂ł́A�K���J�Еی����g���悤�ɂ��܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ߎ����E�Ƒ��v���E�ǂ�����ɂ���ׂ����@�i2013/6/13�j
- ����͑��v���E���u�ߎ����E����O�ɍT�����邩�v�u�ߎ����E������ɍT�����邩�v�ɂ���āA��Q�҂������z�i����j���ς���Ă���Ƃ������������܂����B
���_�Ƃ��Ắu��Q�҂ɂƂ��Ă͑��v���E�́A�ߎ����E�O�ɍT�����ꂽ���������v�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
����ł͈�ʓI�ɁA���I�A���I���t�̂����A�ǂ̂悤�Ȃ��̂��ߎ����E�O�ɍT�������̂��A�ߎ����E��ɍT�������̂��A�Ƃ������Ƃ����Ă݂܂��B
���ߎ����E�O�ɍT�����ׂ����́�
1.���N�ی��i�×{���t�j
�×{���t�͎Љ�ۏ�I�����������̂ŁA���N�ی�����x����ꂽ���Ô�́A�ߎ����E�O�ɍT������܂��B���ʂƂ��đ��Q�Ƃ��čl�����Ȃ����ƂƓ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�{���͎��Ô���A�����̉ߎ����͎����ŕ��S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��킯�ł�����A��Q�҂ɂ��ߎ�����������ꍇ�́A���N�ی����g���āu���Q�Ƃ��čl�����Ȃ����ƂƓ����v�Ƃ������������Ƃ������Ƃł��B
2.�����N���A�����N���i�V��N���j
�V���b�N���A�V������N���̎҂����S�����ꍇ�A���̈편���v�����F�߂��Ă��܂��B���Ȃ킿�u�V��N�������Ă����l�����S�����ꍇ�A���S�������߂Ɏł��Ȃ��Ȃ����V���b�N���A�V������N�����A�{���ł���Ύł��Ă����͂����Ƃ��Ĉ편���v�Ƃ��Đ����ł���v�Ƃ������Ƃł��B
���́u�편���v�Ƃ��Đ�������V��N���v�́A�ߎ����E�O�ɍT������ׂ��i�܂�ߎ����E����Ȃ��j�Ƃ���Ă��܂��B
3.�����⏞�ی�
��Q�҂��ی����S���A�����ɔ����Ď��q�̎�i�Ƃ��ĉ������邵�Ă�����̂�����A���Q�̔����ł͂Ȃ����Q�̕⏞��ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ����ׂ��Ȃ̂ŁA�ߎ����E�O�ɍT������ׂ��Ƃ���Ă��܂��B
���ߎ����E��ɍT�����ׂ����́�
1.�����ӕی��y�щ��Q�҉����̔C�ӕی�
���Q�̔�����ړI�Ƃ�����̂ł�����A���R�ߎ����E��������ɍT������܂��B
���ǂ��炩���܂��Ă��Ȃ����́�
1.�J�Еی�
����ł́A�ǂ���̗������܂��B
�u�J�Еی����t�́A��Q�҂̎����Q���Ă�����ŁA���Q�҂ɑ��鑹�Q�������������Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ��āA���N�ی��Ɠ���̎�舵���������i�ߎ����E�O�ɍT������j�v�ƁA
�u���̑��Q�U��Ɠ��l�Ɉ������Ƃ����Q�����@���ɂ��Ȃ��Ƃ����i�ߎ����E��ɍT������j�v
�Ƃ����悤�ɁA����͕�����Ă��܂��B
������́A���̌o���ł͔C�ӕی���Ђ́A���N�ی��Ɠ����悤�Ɂu�ߎ����E�O�ɍT�����āi�܂��Q�҂ɏ����L���Ɂj�v�����z���v�Z���邱�Ƃ������悤�Ɏv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���N�ی����g�����ꍇ�̑��v���E�i2013/6/12�j
- ��Q�҂��A���Q�ґ��̕ی���ЂƑ��Q�������z�̘b�������i���k���j������Ƃ��A�ߎ����E�i�ߎ������j���������������ꍇ�́A�ȉ��̂悤�ȏ����ōl���܂��B
1.��Q�҂̑����Q�z���v�Z����
�@��
2.�ߎ�����������ꍇ�́A�ߎ����E����i���Q�z����ߎ������������������j
�@��
3.���������z����������
�@��
4.�c�������������Q�҂Ɏx������
��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B
1.��Q�҂̑����Q�z���o���č��v���܂��B�Ⴆ�Ύ��Ô��x�Ƒ��Q�A�Ԏӗ��Ȃǂ����킹�������Q�z��1000���~�������Ƃ��܂��B
�@��
2.��Q�҂ɉߎ�������ꍇ�A�����Q�z�����Q�҂̉ߎ��������������܂��i�ߎ����E�j�B�Ⴆ����Q�҂̉ߎ���30���������Ƃ���ƁA�����Q�z1000���~�̂�����300���~�͔�Q�҂������ŕ��S���Ȃ���Ȃ�܂���B���������āA700���~���u��Q�҂����Q�҂ɐ����ł�����z�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
�@��
3.���Ô�͂���܂ʼn��Q�ґ��̕ی���Ђ���a�@�ɒ��ڎx�����Ă�����Ă���悤�ȏꍇ�A�u�������z�v�Ƃ������������܂��B�Ⴆ�����Ô200���~�������Ă����Ƃ���ƁA700���~����200���~�����������܂��B
�@��
4.700���~����200���~�������������A500���~���A�u������Q�ґ������Q�҂Ɏx��������z�v�ƂȂ�܂��B
�u��Q�҂�30���̉ߎ�������v�Ƃ������̗�ł����ƁA���Â��Ă���Œ��Ɏ��Ô�Ƃ��ĕی���Ђ���a�@��200���~���x�����Ă��܂����A�����������Ô�200���~�̂�����30���i60���~�j�͔�Q�҂��x����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł��B
�ł�����u�ߎ����E��Ɏ��Ô�����������i�T������j�v�Ƃ����͕̂�����Ǝv���܂��B
�ł����A���̂悤�ɑ��葤�ی���Ђ��瑹�Q�̔����Ƃ��Ďx����ꂽ���̂��u�ߎ����E��ɍT������i���������j�v�͓̂��R�ł����A���I���邢�͎��I���t�i�J�ЁA���ہA�����ی��Ȃǁj�̒��ɂ́A�u�ߎ����E�O�ɍT������ׂ����v�Ƃ������̂�����܂��B
�Ⴆ�Ώ�̗�ł����ƁA���Ô��200���~�����N�ی����g���Ď��Â����Ă����ꍇ�ɂ́A��L�́u�ߎ����E��ɍT���v�ł͂Ȃ��A�u�ߎ����E�O�ɍT���v�Ƃ����悤�ɕς��܂��B
1.���Q�z1000���~����
2.��Ɏ��Ô�200���~���T�����܂��i1000-200��800���j
3.�����30���A�ߎ����E���܂��B�i800-�i800�~30���j��560���~�j
560���~�ƁA��قǂ�500���~�Ɣ�ׂ�Ə������炦����z�������Ă��܂��B
���̂悤�ɁA�ߎ����E�Ƒ��v���E������ꍇ�A���̐��W�͏d�v�ɂȂ��Ă���̂ł��B
�i���̍��z��60���~�́A���N�ی������S���Ă��܂��j
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ٗp�ی��Ȃǁ@�i2013/6/11�j
- ��ʎ��̂ɑ����ĉ��������ƁA�����ԕی�����̋��t�݂̂Ȃ炸�A�J�Еی�����ی��Ȃǂ̌��I�A���I���t�����邱�Ƃ�����A������i���Q�ҁj�ւ̑��Q���������Ƃ̒��������ɂȂ邱�Ƃ�����܂�
�������ی��E���Q�ی���
��ʎ��̂ʼn���������莀�S�����肵���Ƃ��ɁA�e��̐����ی��A���Q�ی��A�܂��͑��Q�ی�����̋��t������邱�Ƃ�����܂��B
���̓��e�ɂ���āA���Q�z����T������ׂ����ǂ����i���Q�҂ւ̑��Q���������z�Ɋ܂߂�ׂ����܂߂�ׂ��ł͂Ȃ����j�̎�舵�����Ⴂ�܂��B
���ٗp�ی��i���ƕی��j��
�ٗp�ی��́A�J���̈ӎv�E�\�͂�L����J���҂����Ƃ����ꍇ�Ɂu��{�蓖�v�����t�������̂ł��B�ٗp�ی��̎x���ƌ�ʎ��̂̊W�́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B
�@�ٗp�ی����Ɏ��̂ɑ������ꍇ
�ٗp�ی����̐l�����̂ɑ��������ł��A���_�I�ɂ͉��Q�҂ɑ���x�ƕ⏞�̐����͉\�ł��B���̏ꍇ�A���͈̔͂Ōٗp�ی��̎x���͒�~����܂��B
�A��ʎ��̂������Ŏ��Ƃ����ꍇ
��ʎ��̂ɂ���ĘJ���\�͂���������Q�҂����ق��ꂽ�Ƃ��́A�J���\�͂��������߁A�ٗp�ی��͓K�p����܂���B
�������ی�@��
�����̂��ߍŒ���x�̐������ێ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��l�ɑ��āA�Œᐶ�����ێ����邽�߂ɕK�v�Ȍ��x�ōs���鋋�t�ł��B
���t�̎�ނ́A�����}���A����}���A�Z��}���A��Õ}���A���Օ}���ł��B
�����ی��@��
����ɂ���Đ�����S�g�ω��ɋN�����鎾�a���ɂ���ėv����ԂƂȂ�A�����A�r���A�H�����̉��A�@�\�P���A�Ō�A��Â�v����l���A�\�͂ɉ��������퐶�����c�߂�悤�A��ÁE�����T�[�r�X�����鐧�x�ł��B
�����ł͂Ȃ��T�[�r�X���x������i����1�������ȕ��S�j�A�T�[�r�X����ɂ͗v���F�肪�K�v�ł��B
�Ȃ��A65�Έȏ�́u��1����ی��ҁv�ɂ��ẮA�v���̗��R����ʎ��̂ł����Ă��F��̑ΏۂƂȂ�܂����A40�`64�́u��2����ی��ҁv�ɂ��ẮA��ʎ��̂������Ƃ���ꍇ�ɂ͉��ی��̓K�p�O�ƂȂ��Ă��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���N�ی��@�i2013/6/7�j
- ��ʎ��̂ɑ����ĉ��������ƁA�����ԕی�����̋��t�݂̂Ȃ炸�A�J�Еی�����ی��Ȃǂ̌��I�A���I���t�����邱�Ƃ�����A������i���Q�ҁj�ւ̑��Q���������Ƃ̒��������ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�����N�ی���
1.��|
�T�����[�}���A���٘J���҂܂��͂����̎҂̔�}�{�҂́A�Ɩ��O�̎��R�ɂ�鎾�a�A�����A���S�Ɋւ��ĕK�v�ȕی����t���Ȃ����x�ł��B
2.���t�̓��e
�@�×{�̋��t
�i��}�{�҂̏ꍇ�͉Ƒ��×{��j���a�ɕK�v�ȗ×{���̂��̂����t����B�ی���Ë@�ֈȊO�̈�Ë@�ւŎ��Â����Ƃ��́A�×{�̂��ߕK�v�ƔF�߂�ꂽ�͈͂ł��̔�p�����t�����B�ꕔ���S���͒ʏ��ی��ҁA��}�{�ҋ���3���B �A���a�蓖�� �J���ł����������x�����Ȃ������ꍇ�A1�N6���������x�Ƃ��Ă����⏞����B �B������
�i�Ƒ���������Q�҂����S�����ꍇ�A�����̂��߈��z���x������B
3.���t�̗v��
���N�ی��͋Ɩ��O�̎��R�ɂ�萶�������a���ɂ��ĕی����t���������̂Ȃ̂ŁA�Ɩ����ʋΓr��̎��̂̏ꍇ�́A���N�ی��͗��p�ł����A�J�Еی����g�����ƂɂȂ�܂��B
��Ë@�ւɂ���Ă͌�ʎ��̂ł̉���̎��ÂɌ��N�ی����g�����Ƃɓ�F�������Ƃ��������܂����A�g���Ȃ��킯�ł͂���܂���B
��Q�҂ɂ��ߎ�������悤�ȏꍇ�́A���N�ی��𗘗p����A�����I�Ɏ��Ô�̕����͉ߎ����E�̑ΏۂƂȂ�Ȃ��Ƃ������_������܂��̂ŁA���̂悤�ȏꍇ�͌��N�ی��𗘗p���܂��傤�B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�J�Еی��@�i2013/6/5�j
- ��ʎ��̂ɑ����ĉ��������ƁA�����ԕی�����̋��t�݂̂Ȃ炸�A�J�Еی�����ی��Ȃǂ̌��I�A���I���t�����邱�Ƃ�����A������i���Q�ҁj�ւ̑��Q���������Ƃ̒��������ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B
�����ł́A��ʎ��̂ɑ������ꍇ�Ɍ������ׂ��A���I���I���t�ɂ��Đ������܂��B
���J�Еی���
1.��|
��ʎ��̂ŘJ�Еی����W���Ă���̂́A�Ɩ���܂��͒ʋΓr��ɂ����Č�ʎ��̂Ŏ��������ꍇ�ł��B
���̂悤�ȏꍇ�ɐ��{���J���҂̕ی�̂��߂ɁA�J���ҍЊQ�⏞�ی��@�Ɋ�Â��āA����������l��⑰�ɑ��ċ��t���s���Ƃ������̂ł��B
2.���t�̓��e
�@�×{���t
�i�×{�⏞���t�j�ʏ�͎��Ô�x������B �A�x�Ƌ��t
�i�x�ƕ⏞���t�j�×{���ɒ������x�����Ȃ������ꍇ�ɕ⏞������́B �B��Q���t
�i��Q�⏞���t�j����Q���c�����ꍇ�A���̒��x�ɉ����Ĉ��̈ꎞ���i14������8���܂Łj���邢�͔N���i7���ȏ�j���x��������� �C�⑰���t
�i�⑰�⏞���t�j�⑰�ɑ����̔N���i��O�I�Ɉꎞ���j���x��������́B �D���Ջ��t
�i�����j���V���s�҂Ɏx��������� �E���a�N��
�i���a�⏞�N���j�×{�������ɂ킽��A��Q�̒��x���d���Ƃ��A�x�ƕ⏞���t�ɑウ�ċ��t�����B �F���ʎx���� �x�ƕ⏞���t�A���Q�⏞���t�A�⑰�⏞���t�A���a�⏞�N�������t�����Ƃ��A�J���������Ƃ̈�Ƃ��āA��L���t�ƕ����Ďx�������B
3.���t�̗v��
�J�Ђ͋Ɩ��ЊQ��ʋЊQ�Ŏx������܂����A���̌�������ʎ��̂ɂ��ꍇ�����R�K�p����܂��̂ŁA��Q�҂͎����ӕی��i���Q�ҁj�ւ̐����ƂƂ��ɁA�J�Еی��ւ̐��������邱�Ƃ��\�ł��B
�ǂ���ɐ������s���Ă������̂ł����A��Q�҂ɉߎ�������悤�ȏꍇ�́A�J�Еی����g�p���Ȃ��Ɣ�Q�҂ɕs���Ȍ��ʂƂȂ�܂��̂ŁA�����ӂ��������B
�ގ��̐��x�Ƃ��āA��Q�҂����ƌ������ł���ꍇ�͍��ƌ������ЊQ�⏞�@�A�n���������ł���ꍇ�͒n���������ЊQ�⏞�@�i���Ёj������܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���މ@���J��Ԃ��ꍇ�̈Ԏӗ��v�Z���@�@�i2013/6/3�j
- �i���j���٘A��ʎ��̑��k�Z���^�[�����x���u���Q�����z�Z���v���Ԏӗ��v�Z�̕\�́A���̒���ɓ��@���A�މ@��ɒʉ@�𑱂���A�Ƃ����O��ō���Ă��܂��B
�Ⴆ�u���̌�2�������@������A�މ@��12�����ʉ@���Â������i���Ê��Ԃ͑S����14�����j�v�Ƃ����ꍇ�ɁA���@2�����ƒʉ@12�����̌�������}�X�̐��l���Ԏӗ��z�ƂȂ�܂��B
�ł������ۂɂ́A�Ď�p�Ȃǂ̂��߂ɍēx���@����Ƃ������Ƃ�����Ǝv���܂��B
�Ƃ���ł��̈Ԏӗ��v�Z�̕\�́A���@�̂݁i�ʉ@�݂̂����l�j������ƁA1�����̋��z�������Ă���̂�������܂��B
�Ⴆ�ŏ���1�������@�����53���~�ł����A10�����ڂ���11�����ڂ�1�����Ԃł�8���~���������܂���B
����1�����ł��A���̂��玞�Ԃ������Ă����1�����̉��l���������Ă��Ă��܂��B
��قǂ̘b�ɖ߂�܂����A(a)�u���̌�2�����ԓ��@������A�މ@��12�����Ԓʉ@���Â������i���Ê��Ԃ͑S����14�����ԁj�v�Ƃ����ꍇ�ƁA(b)�u���̌�1�����ԓ��@���A�މ@��12�����Ԓʉ@���Â�������A1�����ԍē��@�����v�Ƃ����ꍇ�A�Ԏӗ��͂ǂ��l����̂ł��傤���B

���̂悤�ȏꍇ�A�l�����Ƃ��Ắ@�@���Z�����i�ώZ�����j�Ɓ@�A�ڂ��ؕ����@������܂��B
�@���Z�����i�ώZ�����j�Ƃ́A��x�މ@���Ă���ē��@�����Ƃ����悤�Ȏ����̂��Ƃ��l�����A�P���ɓ��@������ʉ@������S�č��Z����Ƃ������@�ł��B
14�����Ԃ̎��Ê��Ԃ̂�����2�����̓��@���Ԃ��A�ŏ���2�����ł����Ă��A���ō��킹��2�����ł����Ă������Ƃ������Ƃł��B
�A�ڂ��ؕ����@�Ƃ́A���@���Ă��������A�ʉ@���Ă����������l������l�����ł��B
��قǂ́u�ŏ���1�������@�A���̌�12�����ʉ@�A���̌�1�������@�v�Ƃ����ꍇ�A��x�ڂ̓��@�́u���̌�13�����ڂ���14�����ڂɂ����Ă�1�������@�v�ƍl���Čv�Z���܂��B
�܂�(a)�u���̒���2�������@�v�͈Ԏӗ�101���~�Ȃ̂ɑ��āA(b)�u���̒���1�����{���̌�13�����`14������1�����ō��v2�����v�̈Ԏӗ����u53���~�{6���~�v�́A���v59���~�A�ƂȂ�̂ł��B
���̑��ɂǂ�����ʉ@��������A�ʉ@���ɂ��ẮA����12�����ʉ@�ł�(b)�̕������̓��ɂ��߂��̂ŁA
(a)�̒ʉ@��110���~�i�u14����162���v�|�u2����52���v�j
(b)�̒ʉ@��130���~�i�u13����158���v�|�u1����28���v�j
�ƁA���(b)�̕������z�ɂȂ�܂��B
���@���ƒʉ@�������v�����
(a)�ŏ���2�������@���Ă��̌�12�����ʉ@�@�́@211���~�@�i101�{110�j
(b)�ŏ��ƍŌ��1�������@�A���̊�12�����ʉ@�́@189���~�@�i59�{130�j
�ƂȂ�܂��B
�������ۂ̍ٔ��ł́A���̒���̓��@���A���̂��玞�Ԃ��o�߂��Ă���̓��@���킸��킵���ɂ͕ς��Ȃ��A�Ƃ��A���̒����2�������@�������1��������2�x���@��������킸��킵���A�Ȃǂ̎�����l������̂ŁA�ǂ���̕�����D��I�Ɏg���ׂ��ł��Ȃ��A�K�X�������ɂ�鐔�l���Q�l�ɎZ�肷��A�Ƃ������Ƃɂ��Ă���悤�ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���҂̈Ԏӗ��@�i2013/5/31�j
- ���@�ɂ́u��g�ꑮ�v�Ƃ����l��������܂��B�u���錠����`�����A���̓���̐l�ɐꑮ���āA���̐l�ɑ�������n�Ȃǂɂ��ړ]������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B
�Ⴆ�A�V��N����������Ă���l���S���Ȃ����ꍇ�A���̑����l�́A�S���Ȃ����l�������Ă����u�N�������炤�����v�𑊑����邱�Ƃ͂ł��܂���B�N�������炤�����͈�g�ꑮ�I�Ȃ��̂�����ł��B
�i�V��N���ɂ��ẮA�����ł͂Ȃ��u�{�l�����炤�͂��������̂Ɏ��S�������߂��炦�Ȃ������v�Ƃ����편���v�i�����j�͐����ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��j
���͈Ԏӗ��i���_�I�ȑ��Q�j�𐿋����錠���ɂ��Ă��A�͈̂�g�ꑮ���ƍl�����Ă��܂����B
�Ԏӗ���������Ď����̍��Y�ɂȂ�����Ɏ��S�����炻�̍��Y�͑������邯�ǁA�Ԏӗ��𐿋����Ȃ��܂��S������A�����l�ɂ͎��S�����l�ɑ����ĈԎӗ��𐿋����錠���͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�ł�����O�̔���ŁA�u��Q�҂����S����O�ɂ���i�Ԏӗ������j���s�g����ӎv��\�������ꍇ�Ɍ����đ��������v�Ƃ���܂����B����́u�c�O�����v�Ƃ����ėL���Ȃ̂ł����A��Q�҂��u�c�O�A�c�O�v�ƌ����Ď��S�����ꍇ�ɂ͈Ԏӗ��𐿋�����ӎv��\�������A�Ƃ������̂ł��B
���̌�̔���Łu�������v�͈ӎv�\�������A�u�����āv�͈ӎv�\�����Ă��Ȃ��A�ȂǁA�������̔��Ⴊ�o�܂����B
�u�E�E�E�Ȃ����v
���Ċ����ł���ˁB
����܂�ςȂ̂ŁA���a42�N�̍ō��قŔ��Ⴊ�ύX����܂����B
�u���S�Ԏӗ��́A��Q�҂̎��S�ɂ���ē��R�ɔ������A���������A�Ə����铙���ʂ̎���̔F�߂��Ȃ�����A��Q�҂̑����l����������v
���ł͓��R�ɁA�����l�����҂̈Ԏӗ��𑊑������Ƃ��āA���Q��������Ă��܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����I�Ԏӗ��͔F�߂��邩 (2013/5/30)
- �����I���Q�����i�܂��͐��ٓI���Q�����j�́A�����ȍs�ׂ��������Q�҂ɑ��āA���ۂɐ��������Q�̔����ɉ����āA����ɑ��z�������������x���킹�邱�Ƃɂ���āA���Q�҂ɐ��ق������A�Ȃ��������ɂ����铯�l�̍s�ׂ�}�~���悤�Ƃ�����̂ł��B
���͓��{�ł́A���̒����I�i���ٓI�j���Q�����́A�F�߂��Ă��Ȃ��A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�����́A���Q�҂ɑ��ČY���ł̔����⒦���ɂ���ė^�����Ă���A���Q�҂����Q�҂ɑ��閯����̐ӔC�ł��鑹�Q�����z���I�ɑ��z���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A�Ƃ����l�����̂悤�ł��B
�ł������ۂ̍ٔ���ł́A���Q�҂���Q�҂Ɏx�����ׂ����Q�����z���A�u���Q�҂̈����^�]��M�������A�Ђ������ȂLj����Ȃ��̂ɂ��ẮA�Ԏӗ��z���Ă���v���̂������ł��B
�ǂ��������ƂȂ̂ł��傤���B
�ٔ����̗���Ƃ��ẮA�����^�]�A���Ƌ��^�]�A�Ђ��������̈����Ȏ��̂̏ꍇ�ɈԎӗ��̑��z���l������̂́A���ٓI�Ԏӗ���F�߂����̂ł͂Ȃ��A����ɂ���Q�҂��邢�͈⑰�������_�I��ɂ��傫�Ȃ��̂ł���ƍl���邩��v�������ł��B
���ƂȂ��D�ɗ����܂��A�悭�l���Č���Δ�Q�҂̑��Q�����́A���Q�҂��ی��ɓ����Ă���Εی�����x�����A�Ԏӗ����������z���Ă����Q�Ҏ��g�����ق��Ĕ��ȓx�������A�Ƃ������Ƃł��Ȃ��ł��ˁB
��������A�Ԏӗ��̑��z�ɂ���Q�҂������͈⑰�̋C�����������ł����炮�̂�������Ȃ��A�ƍl����A�m���Ɂu���قł͂Ȃ���Q�҂̐��_�I��ɂ��傫������v�Ƃ����������A�����Ȃ̂��ȂƎv���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����]�@�\��Q�͉���(2013/5/29)
- �����]�@�\��Q�́A��V���]�����������̌��ǂł��B
��ʎ��̂Ȃǂ̊O�����̍����]�@�\��Q�̏ꍇ�A�F�m�ǂȂǂ̂悤�Ȑi�s���ł͂Ȃ��A
���镔��������̂ł��B
�]�����́A�]�ɊW����_�o�זE���E�����Ď����Ă����Ԃł��B
�_�o�זE�͈�x������Ƃ��������Ă��Ȃ��ƌ����Ă��܂��B
�ނ����̎��ÂŎ��̐_�o���ƁA�������̎��͈ꐶ�_�o������܂����ˁB
�畆�⍜�͍Đ����Č��ʂ�Ɏ���܂��B
�ł����]�́A�_�o�זE�̌����Ƃ������͈ꐶ�c�邱�ƂɂȂ�܂��B
�Ƃ��낪���ۂɂ́A�c�����זE�����̎���ꂽ�@�\�������Ȃ��āA�J�o�[����
�������ʂ����܂��B
���Ƀ��n�r���𑱂���ƁA������x�̎��_�܂ʼn���̂ł��B
���ǂł���ȏ�A����ꂽ�@�\�S�Ă�����Ƃ����킯�ɂ͂����܂��A
�����]�@�\��Q�͔]�������オ�ň��ŁA���̌㏙�X�ɉ�
�u�����͍������悭�Ȃ�v�̂ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

���ӏ�Q�Ƃ́@�i2013/4/23�j
- ���ӏ�Q�͕����ʂ�u���ӗ͂��ቺ���邱�Ɓv�ł����A���ӗ͂Ƃ��W���݂͂̂Ȃ炸�A�������̂��Ƃɓ����ɒ��ӂ���������A�����̏�玩���ɕK�v�ȏ���I�������p���A��������Ȃǂ̔\�͂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���ӏ�Q�ɂ͈ȉ��̂悤�Ȏ�ނ�����܂��B
���
�Ǐ�
�Ή��̃|�C���g
�����I���ӂ̏�Q ���ӗ͂�W���͂����������Ĉ�̂��Ƃ𑱂���A�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���₷�����߂ɓr���œ����o���A���肩��͖O�����ۂ��Ƃ�����ۂ�������܂��B ���܂߂ɋx�e������悤�ȃX�P�W���[����g�ނ悤�ɂ���B �I��I���ӂ̏�Q �����̏��̒�����A���K�v�ȏ����I�ԁA�Ƃ����\�͂��ቺ���A���낢��Ȃ��̂ɔ�������B�ׂ̐l�̍�Ƃ��C�ɂȂ��āA�����̂��Ƃ������ɗׂ̐l�Ɍ��o������A�Ȃǂ����̏�Q�B �ׂ̐l�Ǝd�������Č����Ȃ��悤�ɂ���ȂǁA�C���U�錴������菜���B �z���I���ӂ̏�Q �������̂��Ƃɓ����ɒ��ӂ������Ȃ���s������A�Ƃ����\�͂��ቺ����B3�l�ȏ�ʼn�b������Ƃ��A����Ȃ̐l�Ɖ�b�����Ȃ���^�]����A�Ƃ������Ƃ�����Ȃ�B
�Ȃ�ׂ�������悤�ɂ���B
�@�@�@
���ӂ̓]���̏�Q �ЂƂ̂��Ƃɒ��ӂ������Ă���Ƃ��ɁA���̕ʂ̂��ƂɋC�t���Ē��ӂ��ւ���A�Ƃ����\�͂��ቺ����B�p�\�R���𑀍삵�Ă���Ƃ��ɓd�b�����Ă��C�Â��Ȃ��Ƃ��A�d�b���I���������d�b�̂��Ƃɒ��ӂ��s�����܂܂ŁA�Ȃ��Ȃ��p�\�R����Ƃɖ߂�Ȃ��B ���͂̋��͂ŁA���ӂ̓]�����K�v�Ȃ��������B
�p�\�R����������Ă���Ƃ��͓d�b�ɏo��K�v�������ɂ���ȂǁB
�m�F�̌����Ȃǂ́A��������������������@���@�u���ӏ�Q�̌����v
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�m�\��Q�Ƃ́@�i2013/4/22�j
- �m�\�Ƃ��A�Ⴆ�ΐV������ʂ⍢��Ȗ��ɏo���������ɁA�K���L���ȕ��@�ŁA������������������肷��K���͂�A���t��L���Ȃǂ��g���ĊT�O�ŁA���ۓI�Ȏv�l������\�́A����Ɗw�K����\���A�Ƃ������͂Ƃ����܂��B
�m�\��Q�Ƃ́A�����̗͂����Ȃ��Đ����������ɂ��ǂ蒅���Ȃ���Ԃł��B
��ʎ��̂ȂǁA�O�����̔]�����������Ƃ��鍂���]�@�\��Q�Œm�\��Q���F�߂��邱�Ƃ͂悭����܂��B
�ł��������]�@�\��Q�̏ꍇ�͐i�s���ł͂Ȃ��A�������Ώ�����Ή��P�����҂ł��܂�����A���̏Ǐ�ɑ���I�m�Ȑf�f�A���ÁA���n�r���e�[�V�����𑱂��Ă����܂��B
�O�����ł͂Ȃ��������̎����ł̒m�\��Q�͔��ǂ̎����ɂ��A���̊w�K���N����O�i��V�I��18�Έȉ��Ȃǁj�ɔ��ǂ����ꍇ�����_���B�x���A�܂����m�I��Q�Ƃ����A���̒m�I�@�\����U�l��������Ɍ�V�I�ɔ��ǂ����ꍇ���F�m���ƌĂт܂��B
�F�m�ǂ͐i�s���ŁA�m�\��L�������X�ɒቺ���Ă����_�������]�@�\��Q�Ƃ̈Ⴂ�ł��B
�m�F�̌����Ȃǂ́A��������������������@���@�u�m�\�e�X�g�̎���v
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����]�@�\��Q�ł̎��s�Ƃ́@�i2013/4/18�j
- ��ჂȂǂ̉^����Q���Ȃ��A����ꂽ���Ƃ��������Ă���ɂ�������炸�A���퐶���ŕ��i�s���Ă������삪���܂��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ����s�Ƃ����܂��B
�T�^�I�Ȏ��s�ɁA�ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����܂��B
- ���߉^�����s�E�E�E��Ⴢ⊴�o��Q���Ȃ��̂ɁA���̏�̍d�݂����܂����߂Ȃ��������A�|�P�b�g�Ɏ������Ƃ��ɏ��w���������������肵�Ă��܂�������Ȃ��ȂǁB
- �ϔO�^�������s�E�E�E���ԓI�E��ԓI�ȓ������Ɉُ���������Ă���A�Ⴆ�Γ�����g�킸�A���Â���ł��Ă���܂˂̓�������悤�Ƃ��Ă��ł��Ȃ�������A�u�o�C�o�C�v�Ǝ��U���Ă��Ă��A�O���߂Ɏ肪����������̑��x�œ��������Ƃ��ł��Ȃ��ȂǁB
- �ϔO�����s�E�E�E�ϔO�^�������s���P�ꕨ�i�̑���̖��ł���̂ɑ��āA�ϔO�����s����A�̉^���A�����K�v�ȍs�ׂ���Q������Ƃ����Ⴂ������܂��B����̖��O�A�g�p���@��������̂ł����A�u����܂��ĕ����ɓ����v�Ƃ�������A�̓��삪�ł��Ȃ���Ԃł��B
- ���o��ʎ��s�E�E�E�ϔO�^�������s�������ʂɋN���������̂ŁA���J�𐁂��Ȃ��Ƃ���ł����ł��Ȃ��A�Ȃǂ̏Ǐ����܂��B
- ���s���s�E�E�E���s�̂悤�ȁA���ɏK�킸�ɂł���悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
- �J�Ꮈ�s�E�E�E�J��̂悤�ȁA���ɏK�킸�ɂł���悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
- ���ߎ��s�E�E�E�̂ƈߕ�����ԓI�ɓK���ł����A�ߕ��̏㉺�A���\�̋�ʂ����Ȃ��B�{�^�����������Ȃ��A�Ȃǂ̏Ǐo�܂��B
���s�̊m�F�̌����Ƃ��ẮA�E�F�X�^����������nj����iWAB�����j�̉��ʍ��ځu�s�ׁv���s���܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����]�@�\��Q�ł̎���ǂƂ́H�@�i2013/4/17�j
- �l�͘b������A��������A��������A�ǂ肵�Č��t���g�����Ƃő��l�Ƃ̈ӎv�a�ʂ�}���Ă��܂����A��������@�\�̏�Q�Ŏ���̐l�Ƃ��܂��R�~���j�P�[�V���������Ȃ��Ȃ���������������Ƃ����܂��B
�����������t���o�Ȃ�
���̒��ŃC���[�W���Ă��A��������܂������\�����t���o�Ȃ���Ԃł��B
- �ď̏�Q�E�E�E���Ă�����̖̂��O���o�Ă��Ȃ��u���o���ď̂̏�Q�v���b�̒��Ō��t���o�Ă��Ȃ��u��z�N��Q�v
- ���Q�E�E�E��������������Ƃ��C�u���v�Ŏn�܂���������Ȃǂ����܂�ɉ����Ď����悤�Ȍ��t��������̂�����ȏ��
�m�F�̌����Ȃǂ́A��������������������@���@�u����@�\�Ɋւ��錟���v
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����]�@�\��Q�ƔF�m�ǂ̈Ⴂ�@(2013/4/16)
- �����]�@�\��Q�̌����́A�傫���u�������v�̂��̂Ɓu�O�����v�̂��̂ɕ������܂��B
��ʎ��̂ł̍����]�@�\��Q�́A�������O�����ł��B
�������̑�\�͔]�����ŁA�����Ƃ��Ă���ԑ����Ƃ���Ă��܂��B�]�����͈ȉ��̂悤�ɕ������܂��B
�]�����@�\�@�]�[���c�]�̌��ǂ��l�܂�
�@�@�@�@�\�@�]�o���c�ד������j���Č��t�����NJO�ɂł�
�@�@�@�@�\�@���������o���c����ᎂȂǂ��j��Ĕ]�̕\�ʂ𒆐S�ɏo������
�O�����̔]�����́A��ʎ��̂�]�|�A�]���œ����ɊO������Ռ�������邱�ƂŋN����܂��B
�O�����]�����@�\�@�]�����c�Ռ��ɂ��]�̎����ɍ��ł�ڂ���B
�@�@�@�@�@�@�@�\�@�т܂��������c�����ւ̉�]��˂���̗͂ɂ��A�_�o�זE��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�b�g���[�N���`�����鎲��������
�@�@�@�@�@�@�@�\�@�}���d���O�����c���W�����܂ɂ���Ĕ]����ł���d����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�Ɍ������܂�
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����]�@�\��Q�̒�`�@(2013.04.14)
- ��ʎ��̂Ŕ]����������ƁA�̂̉^���@�\��_�ɏd��ȉe�����^�����܂��B
���̔]���������������Ƃ���ĎЉ�A�������̂́A�^���@�\��_�@�\�ɏ�Q���c��A���̑O�Ɠ����悤�Ȑ�����d�����ł��Ȃ����Ƃ�����܂�
���̂悤�ɁA�]�̑����������Ŕ]�̒��ł̏��������܂��ł��Ȃ��Ȃ�A���̌��ʘb�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�����A����̂��Ƃ�������Ȃ��Ȃ�����A�L���͂��������肷�邱�Ƃ������]�@�\��Q�ł��B
�����]�@�\��Q�́A��w�I�ɂ͓��ꂳ�ꂽ��`�͖����A�]�����ɋN������F�m��Q�S�ʂ��������̂̂悤�ł��B����ɑ��������J���������g��ł��鍂���]�@�\��Q�Ɋւ��錤���ł́A�s���I�ɉ��\�̂悤�ɒ�`���Ă��܂��B
�T�D��v�Ǐ�Ȃ� 1.�]�̊펿�I�a�ς̌����ƂȂ鎖�̂ɂ���A���a�̔��ǂ̎������m�F����Ă���B
2.���ݓ��퐶���܂��͎Љ���ɐ�����A���̎傽�錴�����L����Q�A���s�@�\��Q�A�Љ�I�s����Q�Ȃǂ̔F�m��Q�ł���B�U�D�������� �l�q�h�A�b�s�A�]�g�Ȃǂɂ��F�m��Q�̌����ƍl������]�̊펿�I�a�ς��m�F����Ă��邩�A���邢�͐f�f���ɂ��]�̊펿�I�a�ς����݂����Ɗm�F�ł���B �V�D���O���� 1.�]�̊펿�I�a�ςɊ�Â��F�m��Q�̂����g�̏�Q�����ĔF��\�ł���Ǐ��L���邪�A��L�T-2�̎�v�Ǐ����������
2.�܂��͔��LjȑO����L����Ǐ�ƌ��������͏��O
3.��V�������A���Y���]�����A���B��Q�A�i�s�������͏��O
���ۂɂ͌����Ŕ]�̏��Ձi�u�펿�I�a���v�Ƃ����܂��j���m�F���邱�Ƃ�����P�[�X������A���ǂ��ǂ����ł��߂邱�Ƃ�����܂��B
��ʎ��̂Ȃǔ����Ɋւ��悤�ȏꍇ���A���̒�`�ɓ��Ă͂܂�̂��ǂ��������f�����ɏd�v�ƂȂ�A���߂��悤�ȏꍇ�A��Q�҂₻�̉Ƒ��́A���ǂł��邱�Ƃ��ؖ����邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�܂��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ȃ͑��l���@�i2013.02.04�j
- ��ʎ��̂ɂ�鎩���ԕی��̐����ł́A���܂Ɂu���l���v�����ƂȂ�܂��B
�����ӕی����C�ӕی��̑ΐl�����ӔC�ی��́A����l�i�ی��ɓ����Ă���l���L����ی��ҁj���A���l�̐�����g�̂��Q���đ��Q��^�����Ƃ��ɁA���̑��Q���������Q�҂ɑ����čs���i�������Ă����j���̂ł��B
�ł����玩�����N���������̂Ŏ�������������Ă��A�������������Ă���ΐl�����ی�����͎x����������܂���B�ΐl�����͑��l�Ɏx�������̂�����ł��B
����͓�����O�ŁA�N�ł��킩�邱�Ƃł��B
�ł��������i�L����ی��ҁj���N���������̂ŁA�����̉�����i�z��ҁj�ɉ���������Ă��܂����ꍇ�͂ǂ��ł��傤���B
�u������͎����Ƃ͕ʐl�Ȃ̂�����A����͓��R�ΐl��������x������ł��傤�v
�L���ی��҂͎����ł���A������ł͂Ȃ��̂����瓖�R������A�ƍl���܂��B
���_�Ƃ��ẮA�������N���������̂ʼn�����ɉ���������Ă��܂����ꍇ�A�����ӂ���͑��Q���������x�����܂��B
����͏��a47�N�̍ō��ٔ����i�u�Ȃ͑��l�v�����j�ȍ~�A�����ӂ���x������悤�ɂȂ����̂ł����A����܂ł͎����ӂ́A���̂悤�ȏꍇ�̎x�����ɂ͂��܂艞���ė��܂���ł����B
���̂悤�Ȏ��̂ŁA�Ƒ��̈�������Q�����ӔC�i���j���A������������Q�����������i���j�����ꍇ�A�ȂɌ��炸�����̐e���̏ꍇ�͎����I�ɍ��z����ł����A�ʏ�Ȃ瑊�E����č��������[���A���̍��z�̂����̏o����͖����͂��Ȃ̂ɁA�ی��ɉ������Ă��邽�߂Ɂu���҂Ɠ������z�̍��ҁv�̍��z�̒��g�������Ă͂��������I
������Ȃ͑��l�ł͂Ȃ��A�ی����甅�����͕����Ȃ��A�Ƃ��������������悤�ł��B
�ł������a47�N�̍ō��ٔ�����
�u�����@3���́A�E�E�^�s���p�ҁE�E�E�y�щ^�]�ԈȊO�̂��̂𑼐l�Ƃ����Ă���̂ł����āA��Q�҂��^�s���p�҂̔z��ғ��ł��邩��Ƃ����āA���̂��Ƃ����ŁA�������Q�҂��E�ɂ������l�ɓ�����Ȃ��Ɖ����ׂ��_���͖����i�ȉ����j�v
�Ƃ���A����ȍ~�A�����ӂł͑��l�Ƃ��Ĕz��҂ɑ��Q���������Ă��܂��B
���ӂ���ׂ��Ȃ̂́A�����ӂł͂Ȃ��C�ӕی��͖Łu��ی��҂̕���A�z��ҁA�q������Q�҂ɂȂ����Ƃ��͑ΐl�����̎x�����͂Ȃ��v�Ɩ��L����Ă���A���̂Ƃ���ΐl�����̕ی����i�������j�͎x�����܂���B
�����A�C�ӕی��͂��̂悤�ȁi�e���Ԃ̎��̂́j�ꍇ�A�ΐl�����ی��̑����l�g���Q�ی��Ⓥ��ҏ��Q�ی��Ȃǂŕ⏞���J�o�[�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�Ȃ������Ɠ���l���ł͂Ȃ��Ƃ���������O�̂��Ƃ��A���\����̂ł��B
���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����N�҂̐e�̐ӔC�i2012.04.25�j
- �����N�̖��Ƌ��^�]���N���������̊֘A�ł��B
18�̖��Ƌ��̏��N���Ԃ��^�]���ĕ��s�҂�瀂��E���Ƃ����l�g���̂��N�������ꍇ�A�ȑO���������܂������A���̎Ԃ̕ی����g����A�����ɂ��Ă͂Ƃ肠�������v�ł��B
���̉��Q�ԗ����C�ӕی��ɓ����Ă��Ȃ��A���邢�͓����Ă��Ă��ΐl�������^�]�Ҍ���i�Ƒ�����Ƃ�26�Ζ����s�S�ۂȂǁj�̓��t���Ă���ƁA��Q�҂͎����ӕی�����̕⏞�������Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
�����ӂ̕⏞�݂̂ł͑���܂���A�����ӂ��镪�͐�����������悤�ɁA��Q�҂̉Ƒ������Ɨp�Ԃ������Ă��Ď����ԕی��ɓ����Ă���A�����i��Q�ҁj�̕ی��̐l�g���Q�ی��△�ی��ԏ��Q�ی�����x�����܂����A���Ɨp�Ԃ������Ă��Ȃ��ꍇ�͉��Q�Җ{�l�ɐ������邱�ƂɂȂ�܂��B
�ł�18�̏��N�Ɏx�����\�͂��������Ƃ͖��炩�ł��B
���̂悤�ȏꍇ�A�u���Q�҂͖����N�Ȃ̂�����e�ɐ�������悢�v�ƒP���ɍl����킯�ɂ͂����܂���B
���Q�҂͖����N�Ƃ͂����A�u12�`13�Έȏ�̎҂͐ӔC�َ��\�͂�����v�Ƃ��āA�u�ӔC�͖{�l�ɂ���A�e�́i���@714���́j�ē`���҂̐ӔC�͖����v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă���̂ł��B
���̏ŁA��Q�҂����Q�҂̐e�ɐ���������@�A�Ƃ����������́A2�Ƃ��肠��܂��B
�ЂƂ́A�e���̂��̂ɐӔC���������Ƃ��āA���@709���̕s�@�s�אӔC��₤�����ł��B
������́A�����@3���Ō����u�^�s���p�ҐӔC�v���e�ɂ������A�Ƃ��ĐӔC��₤���Ƃł��B
�^�s���p�ҐӔC�́A�Ԃ̎������A���̎Ԃ̉^�s�ŗ��v����́A�Ƃ������l�̐ӔC�Ƃ������Ƃł����A�����Ƃ���ɂ��ƍ���̋T���s�̎��̂̎Ԃ́A����҂̒m�荇���̎ԂƂ̂��Ƃł�����A�e�ɉ^�s���p�ҐӔC�����߂�͓̂�����ł��B
��������ƁA�u�e�{�l�ɕs�@�s�אӔC������v�Ƃ��Đe�ɔ����������邱�Ƃ��낤�Ǝv���܂��B
���̏ꍇ�̏��������܂�ȒP�ł͂Ȃ��A�ō��ق�
�@�ē`���҂������̊ē�����Ή��Q�s�ׂ̔������h�~���꓾������
�A���̊ē������ɂȂ���������
�B�ē������ɕ��C���Ă����Γ��Y���Q�s�ׂ���������Ƃ̊W�R������ʓI�ɂ������ꍇ�ł���������
�̗v�����K�v�Ƃ��Ă��܂��B����̏ꍇ�ɂ���3�v���͊Y������ł��傤���B
�u�Y������̂��v�Ɨ�����A�ٌ�m����̎�r�����҂��Ă��܂��B
�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�T���s�̎��́@�i2012.04.24�j
- ���s�ł́A����̋_���ł�8�l���S���̂ɑ����āA����i����24�N4��23���j�ɂ��T���s�ő傫�Ȏ��̂�����܂����B
�W�c�o�Z���̎����̗�ɎԂ��˂�����ŁA�D�w�̏�����7�̎��������S���A���̑��ɂ�����2�����ӎ��s���̏d�́i����24�N4��24�����݁j�Ƃ����A�ɂ܂������̂ł��B
���Q�ԗ����^�]���Ă������Q�҂́A18�Ŗ��Ƌ��A������^�]�������Ƃ̂��Ƃł��B �Ƒ��̓{��△�O���́A���ɂ͑z�����ł��Ȃ��قǂł��B
�Ƒ������Q�҂Ɍ�����]�ނƂ����C�����͂悭������܂����A18�̏��N�Ƃ������ƂŁA5�N���x�̒����A�܂��͋����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����\�z������܂��B
����ł͉Ƒ��͓���[���ł��Ȃ����낤�ƁA�N�ł��v���܂��B
����͉��Q�Җ{�l�́u�Y���v�̘b�ł����A����Ƃ͕ʂɉ��Q�҂͔�Q�҂ɖ�����̐ӔC�Ƃ��āA���Q���������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B 18�̖��Ƌ��^�]�A�Ƃ������ƂŁu�Y�����y���v�Ƃ������ƈȊO�ɂ��A�u������Ɣ��������x������̂��v�Ƃ����S�z���A�Ƒ��ɂ͔����Ă��邱�ƂɂȂ邩������܂���B
��Q�҂̉Ƒ��Ƃ��Ă͂��炭�͂����̂��Ƃ��l����]�T�͂Ȃ���������܂��A������ƌ������Ă݂܂��B
�܂��A���Q�ԗ��ɂ��Ăł��B ���������X�ɂ͂˂��y�����Ԃ͒N�̏��L���Ȃ̂��Ƃ��A�ΐl�����ی��i�C�ӕی��j�ɓ����Ă����̂��Ȃǂɂ��āA���̂Ƃ���͂���Ă��܂���B
�������̎Ԃ����Q�҂̉Ƒ����ۗL����Ԃ������Ƃ��āA���̎ԂɔC�ӕی����|�����Ă��āA�{�l��������N���������i26�Ζ����s�S�ۂȂǁj��������A�Ƃ肠�������̎Ԃɂ����Ă���ΐl�����ی����g���A��Q�҂ɔ��������x�����܂��B
�܂�u���̎Ԃ��C�ӕی��ɓ����Ă���Δ���������Q�҂ɕ�����v�Ƃ������Ƃł��B
���Ƌ��^�]�̏ꍇ�͑ΐl�����͎x����Ȃ��A�Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��B
���ɂ��̎Ԃ������ӕی��i�����ی��j�݂̂ŁA�C�ӕی��ɓ����Ă��Ȃ��A������u���ی��ԁv�������ꍇ�͂ǂ��ł��傤���B
�����ł������ꍇ�A�Ƃ肠��������̎Ԃ̎����ӕی��ɐ������邱�Ƃ���̕��@�ł����A�d���⎀�S�̏ꍇ�͎����ӕی������ł͓��ꑫ��܂���B
���̂悤�ȏꍇ�́A��Q�҂̕��̉Ƒ������Ɨp�Ԃ������Ă���A���́u�����̉Ƒ��̎��Ɨp�Ԃ̎����ԕی��v�ׂ܂��B
���̏ꍇ�A�C�ӕی��ɓ����Ă���u�l�g���Q�ی��v��u���ی��ԏ��Q�ی��i����j�v��t���Ă���͂��ł��B
�ł������Q�҂́A������̎����̕ی��̐l�g���Q�ی��△�ی��ԏ��Q�ی��ɐ������܂��B
��������Ɣ�Q�҂́A���Q�҂��{����Q�҂ɑ��Ĕ�������ׂ��u���Q�������v�������̕ی������邱�ƂɂȂ�܂��B
�����̕ی���Ђ́A������Q�ґ����������Ă���ی���A���Q�Җ{�l�ɐ������܂��i���������ɑ����Ƃ��ď������邱�Ƃ�����悤�ł��j�B
�܂�A��Q�Җ{�l�i�܂��͈⑰�j�̑���ɁA�����̕ی���Ђ����Q�҂ɐ������Ă����A�Ƃ����C���[�W�ł��B
�Ƃ���ł��̂悤�ɉ��Q�҂����ی������������Ɏ����̉Ƒ������Ɨp�Ԃ������Ă��Ȃ������ꍇ�A�l�g���Q�ی��Ȃǂ͓��R����܂���B
���̏ꍇ�ɂ͂Ƃ肠���������ӂ�����x�z�����������ɁA�����ӂ��镔���ɂ��Ă͉��Q�Җ{�l�ɐ������Ă��������Ȃ��A���ɂ炢�ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

���]�Ԃ̌�ʃ��[���@�i2012.04.03�j
���̂Ƃ��뎩�]�Ԃ��W���鎖�̂��悭�b��ɂȂ�܂��B
����͔N�X���]�Ԃ��W���鎖�̂������Ă��邩�炾�Ǝv���܂����A�ŋ߂ł͔N�Ԃ̌�ʎ��̂̂����A���]�ԗ��p�҂������҂ƂȂ������̂́A�S�̂�20�����Ă���悤�ł��B
���[����}�i�[�����Ȃ����]�ԗ��p�҂������A�Ȃ�Ă��������������܂����A�����������]�Ԃ̃��[�����āA�͂�����c�����Ă���ł��傤���B
�u���]�Ԃ��y�ԗ��Ȃ̂�����A�����Ƃ��Ďԓ��𑖂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��I�v �Ƃ��������x�̂��Ƃ͒m���Ă��Ă��A�����������玩�������]�Ԃɏ���Ă���Ƃ��A���C�Ȃ��ᔽ�����Ă��邩���B
�����ō���́A���]�Ԃɂ��Ă̎�ȃ��[���Ɣ������ꗗ�\�ɂ��ċ����Ă݂܂��B
�܂��͒ʍs�ꏊ����@�ł��B
���e�� ���� �ԓ��ʍs�̌��������Ǝԓ��̋�ʂ�����Ƃ���ł́A�ԓ���ʍs����̂������ł���A�ԓ��̍����i�ԗ��ʍs�т̖������H�ł͍����[�j��ʍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B3�����ȉ��̒����܂���5���~�ȉ��̔����^2���~�ȉ��̔����܂��͉ȗ� �����ɂ�����ʍs���@���]�Ԃ�������ʍs����ꍇ�́A�ԓ����̕��������s���Ȃ���Ȃ炸�A���s�҂̒ʍs��W����ꍇ�́A�ꎞ��~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B2���~�ȉ��̔����܂��͉ȗ������_�ł̒ʍs �M���@�̂�������_�ł́A�M���@�̐M���ɏ]��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B3�����ȉ��̒����܂���5���~�ȉ��̔��� �M���@�̂Ȃ������_�ŁA�ꎞ��~���ׂ����Ƃ������W����������ꍇ�́A�ꎞ��~���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A����������L�����ɏo��Ƃ��͏��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�ԐM���œn���Ă��܂����肵�Ă��܂��H
����Ȃ��Ƃ������由��5���~�ł��B
���Ɏ��]�Ԃ̏����ł��B
���e �� ���� ���S�^�]�̋`�� ���H�y�ь�ʓ��̏ɉ����A���l�Ɋ�Q���y�ڂ��Ȃ��悤�ȑ��x�ƕ��@�ʼn^�]���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B 3�����ȉ��̒����܂���5���~�ȉ��̔��� ��ԁA�O�Ɠ�����є����̓_�� ��ԁA���]�Ԃœ��H�𑖂�Ƃ��́A�O�Ɠ�����є����i�܂��͔��ˋ@�ށj��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B 5���~�ȉ��̔��� ��l���̋֎~ ���]�Ԃ̓�l���́A�e�s���{�������ψ���K���Ɋ�Â��A6�Ζ����̎q�����悹��Ȃǂ̏ꍇ�������A�����Ƃ��ċ֎~����Ă���B 2���~�ȉ��̔����܂��͉ȗ� ���C�тщ^�]�̋֎~ ���C��ттĎ��]�Ԃ��^�]���Ă͂Ȃ�Ȃ��B 5�N�ȉ��̒����܂���100���~�ȉ��̔��� ���i�̋֎~ �u���i�v�̕W��������Ƃ���ȊO�ł́A����ő����Ă͂Ȃ�Ȃ��B 2���~�ȉ��̔����܂��͉ȗ�
���C�тщ^�]�͔���100���~�I�I
���݉�̋A��ɋC�y�Ɏ��]�Ԃɏ��Ȃ��ł���ˁB
�Ō�ɁA����21�N�Ɉꕔ�������ꂽ�����s���H��ʋK���̓��e�ł��B
���e �� ���� �P�����^�]���̋֎~ �P�������A����S���A�������������W���A�܂��͈��������������̂�����@�ŁA��^������֎ԁA���ʎ�����֎ԁA�����@�t�����]�Ԃ܂��͎��]�Ԃ��^�]���Ȃ����� 5���~�ȉ��̔��� ���]�Ԃ��^�]���̌g�ѓd�b���̋֎~ ���]�Ԃ��^�]����Ƃ��́A�g�ѓd�b�p���u����ŕێ����Ēʘb���A�܂��͉摜�\���p���u�ɕ\�����ꂽ�摜�𒍎����Ȃ����ƁB 5���~�ȉ��̔��� �c����l����p���]�Ԃ��^�]����ꍇ�̏�Ԑl���̐����� �E16�Έȉ��̉^�]�҂́A��ւ܂��͎O�ւ̎��]�Ԃ̗c���p���Ȃɗc����l����Ԃ����邱�Ƃ��ł���B
�E16�Έȏ�̉^�]�҂����S��������c����l����p���]�Ԃ��^�]����ꍇ�́A���̗c���p���Ȃɗc����l����Ԃ����邱�Ƃ��ł���B2���~�ȉ��̔����܂��͉ȗ�
�c����l����p���]�ԂƂ́A�^�]�҂̂��߂̏�ԑ��u�Ɠ�̗c���p���Ȃ�݂��邽�߂ɁA�K�v�ȋ��x�A�������\���̗v���������ʂȍ\����L���鎩�]�Ԃ̂��Ƃł��B
�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�편���v�̑Ώۊ��Ԃ͉���67���@�i2012.03.14�j
��ʎ��̂Ō��ǂ��c�������i����Q�������F�肳�ꂽ���j��A���S�����ꍇ�ɁA�편���v�����Q�ґ�����x�����܂��B
�편���v�Ƃ́A������Q�҂������Ă����珫�����Ă����͂��������̂Ɏ��S�������߂ɓ����Ȃ��Ȃ������v�i�����j�̂��Ƃł��B
���ǂ̏ꍇ���A��Q�҂Ɍ��ǂ��c���Ă��܂������߂ɁA�������̊����ŘJ���\�͂��������Ă��܂����߂ɓ����Ȃ��Ȃ������v�i�����j���편���v�ƌ����܂��B
�Ⴆ��47�Ŏ��̂ɂ���Ď��S���Ă��܂�����Q�҂̏ꍇ�A���S���Ȃ���Γ����Ă������v�́A���̒��O�̔N���������ƍl���āA����������̊����́u������T���v���������������z���A����20�N�ԁi67�܂Łj�ɓn���Ď������A�ƍl���Ă�����편���v�Ƃ��ĉ��Q�҂��x�����܂��B
67�Ƃ����N���́A�ʏ�p�����鐔�l�ł��B �u���̂ɑ���Ȃ����67�܂œ������͂����v�ƍl���Ă���̂ł��B
�ٔ��ł����������Z���^�[�ł����k���ł��A�i�ނ��ł��Ȃǂ̐_�o�Ǐ�͕ʂł����j�편���v��67�܂łƂ��Ă��܂��B
�Ȃ�67���H
�����́A�Ȃ��37�N�O�́A1975�N4�����̕ʍ�����^�C���Y��1���ɂ���܂��B
�u�ғ��A�J�I��������67�Ƃ����̂͑�12���\�i���a44�N�j0�Βj�q�̕��ϗ]��67.74�ɂ�������̂ł���B���ׂĂ̔N��̎҂̕��ϗ]���������̔N��̎҂̏A�J�\���ԂƂ͂����Ȃ��ł��낤���A�ꉞ0�̂�����̗p�����v �Ƃ���܂��B
0�̕��ϗ]���Ƃ́A������u���ώ����v�ł��B
�܂�1975�N�̕��ώ�����67�ł���A���̎��Ɂu�A�J�\�N���67�܂Łv�ƌ��߂����Ƃ��A���܂��ɍٔ��⎦�k���ł��g���Ă���̂ł��B
���݂̕��ώ����́A�j���ł�79.64�����ǁA����ł����̂��H
67�ƌ��܂�����������m���Ă��炸���Ǝv���Ă��܂����A���̂Ƃ���ٔ����͕ύX�������͂Ȃ��悤�ł��B
�Ȃ��A67�������₠�邢��67�ɋ߂��N��̕��̈편���v���l����ۂɁA�u�A�J�\�N���́A���̔N��̒j�q�i�܂��͏��q�j�̕��ϗ]���̔����v�Ƃ����v�Z���@�����̂���ʓI�ł��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�⑰�N�����A���S�편���v�Ƃ��Đ����ł��邩�@�i2012.02.21�j
�e����I���t�i���ɔN���j���Ă��������ʎ��̂Ŏ��S���Ă��܂������A�������Ă���Ζ{������͂��������e�틋�t���A���S�������߂Ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂������Ƃɑ����u�편���v�v�Ƃ��Đ����ł���ꍇ������܂��B
�Ⴆ�Ύ��S�����{�l�����t���Ă����u�V���b�N���v���u�V������N���v���A�u�{���͕��ϗ]���܂ł͐����Ă��āA���̕��͎�ꂽ�͂����v�Ƃ��āA�편���v�Ƃ��Đ����ł��邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
��Q�����N���i��Q��b�N�����܂ށj��������̋��ϔN���������ŁA�편���v�Ƃ��Đ����ł���Ƃ������Ⴊ����܂��B
�ł����u�⑰�N���v�̓_�����i�편���v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��j�Ƃ������ƂɁA����ł͂Ȃ��Ă���܂��B
�⑰�N���Ƃ́A�����N���̔�ی��҂�ҁi����Ȃ���j�����S�����ꍇ�ɁA������Ɏx������N���ł��B
���̏ꍇ�̉����A��ʎ��̂ŖS���Ȃ����Ƃ��ɁA�u�����Ă�������炦���͂��̈⑰�����N�����v�Ƃ͂����Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B
�V������N�����편���v�Ƃ��Ĕ����̑ΏۂɂȂ�̂ɁA�⑰�����N���������̑ΏۂƂȂ�Ȃ��͕̂s�v�c�Ȋ��������܂��B
�편���v�̑ΏۂƂȂ邩�Ȃ�Ȃ����ɂ��ẮA�����Ƃ��Ĉȉ��̍l����������悤�ł��B
�u���Y�i�N���j���t���A�J���Ή��i�����j�̌㕥���̂悤�Ȑ����ƍl������ꍇ�͈편���v��������B ���Y�i�N���j���t���A���҂̐����̌p����O��Ƃ���悤���Љ�ۏ�I���t�ƍl������ꍇ�i�Ⴆ�ΐ����ی�Ȃǁj�͈편���v���������v
�v����ɁA�V��N���͉ߋ��Ɏ����ŕی������x�������Ή��Ȃ̂Łu���炦�Ȃ���Δ����̑ΏۂƂȂ�v���A �����ی�̂悤���Љ�ۏ�I���t�́A���t�̊�b�ƂȂ鎑���͔�Q�Ҏ��g�Ƃ͖��W�ɋ��o����Ă�������Ȃ̂ŁA�u���炦�Ȃ��Ă������̑Ώۂł͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃł��B
���̍l�������ƂɁA�⑰�N�������������ҁi������j���ی����S���Ă������̂ł͂Ȃ����A����ɍč�������{�q���g��������t���ł����鐫���̂��̂Ȃ̂ŁA�Љ�ۏ�I�����������ƍl�����A�편���v�Ƃ��Ă̔����̑ΏۂƂȂ�Ȃ��A�Ƃ����̂���ʓI�Ȕ��f�ƂȂ��Ă��܂��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�Ԑډ���ɂ��āi��v�^���ƎQ�l�^���̈Ӌ`�j�@�i2012.02.14�j
�㎈��3��߁i���A�r�A���j�≺����3��߁i�Ҋ߁A�G�A����j�����搧���i���܂�Ȃ���Ȃ��Ȃ邱�Ɓj������Q�����̑ΏۂƂȂ邱�Ƃ͂���܂��B
�O��Ƃ����u���̂ɂ��߂̓�������������錴���ƂȂ�펿�I�����i�ߕ����̍��܌�̖����s�ǁA�ߎ��ӑg�D�̕ϐ��ɂ��ߍS�k�A�_�o�̑����Ȃ��j�������Ă���v���Ƃ��K�v�ł����A
�u�i���E�́j������������̊߂̉��悪��������Ă��Ȃ����ɔ�ׂ�1/2�ȉ��Ȃ�w�������@�\��Q�x�Ƃ���10���v
�u3/4�ȉ��Ȃ�w�i�P�Ȃ�j�@�\��Q�x�Ƃ���12���v
�Ȃǂł��B
����Ƃ́A���̊p�x���H�Ƃ������Ƃł����A������u��v�^���v�Ɓu�Q�l�^���v�𑪂邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�ꍇ�ɂ���Ă͎�v�^�������ł��\���܂���B
��v�^���Ƃ́A�u�e�߂ɂ��������̓���ɂƂ��čł��d�v�Ȃ��̂������v�Ƃ���Ă��܂��B�Ⴆ�Ό��߂Ȃ�
1.�����i�O������B�C��t���̏�Ԃ���r��O���ɏグ�A���̂܂ܓV��܂�180�x�グ�Ă����j
2.�O�]�i��������B�C��t���̏�Ԃ���A�r��^���Ɍ������ďグ�A���̂܂ܓV��܂�180�x�グ�Ă����j
�̓�ł��B
�������Q�l�^���Ƃ́A����̓���Ŏ�v�^���قǏd�v�łȂ��i�ƍl�����Ă���j�^���ł��B
���߂Ō�����
1.�L�W�i�������B�C��t���̏�Ԃ���A�r������ɏグ��j
�ł��B
���݂̎�舵���ł́A����Q�������F�肳���v���Ƃ��ẮA�Ⴆ��
�u�������@�\��Q�v�̏ꍇ����v�^����̂����ǂ��炩��1/2�ȉ��ɐ�������Ă���悢�A
�u�i�P�Ȃ�j�@�\��Q�v�̏ꍇ����v�^���̂����ǂ��炩��3/4�ȉ��ɐ�������Ă���悢�A
�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�܂�����Q�����́A��v�^���̉���Ō��܂��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�ł͂Ȃ��Q�l�^��������̂��B
�Q�l�^���́A�ȉ��̂悤�ȏꍇ�ɎQ�l�ɂ���܂��B
�u�����F��͌����Ƃ��Ď�v�^���ɂ�蔻�f����邪�A��v�^���̐����������]���̑ΏۂƂ���鐔�l�i1/2�Ƃ�3/4�̂��Ƃł��j���킸���ɏ���ꍇ�́A�Q�l�^����1�ɂ��ĉ���p�x��1/2�܂���3/4�ȉ��ɐ�������Ă���Γ����F�������v
�Ƃ������Ƃł��B �u�킸���ɏ���v�̂킸���Ƃ́A�����Ƃ���5�x�ł����A���߁A��߁i���j�A�Ҋ߂̋��ȁE�L�W��10�x�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�ł�����u���Ӗ����v�Ȃ�Ďv�킸�ɁA����Ƃ��Q�l�^���������Ă��炤�悤�ɂ��܂��傤�B
�Ȃ��A�㎈�E�����i��w�E���w�������j�̎�v�^���ƎQ�l�^���́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B
���� ��v�^�� �Q�l�^�� ���� �E����
�E�O�]-���]�E�L�W
�Ђ��� �E����-�L�W
��� �E����-�L�W �E���-�ڋ� �O�r �E���-��O
�Ҋ� �E����-�L�W
�E�O�]-���]�E�O��-���� �Ђ��� �E����-�L�W
���� �E����-�L�W
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�����i�H�j�ȉ��d��Q�@�i2012.02.07�j
��ʎ��̂̌���Q���l����ꍇ�A�u���d�v�Ƃ����F����@������܂��B
����́A���ȏ��I�ɂ�
�u���ɐg�̏�Q��L���Ă����҂��V���ȍЊQ�ɂ��A���ꕔ�ʂɐg�̏�Q�̒��x�����d�������́v
�ł���A���̏ꍇ�̑��Q�z��
�u���Y����Q�ɊY��������z����A���ɂ���������Q�̊Y��������z�ɉ��������z���T���������z�v
�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
�Ⴆ�A���ɕЕ��̉����𑫊��i����̂��Ƃł��j���玸���Ă����l�i5���j���A���̌㎖�̂��������̑����Ђ��߂��玸���Ă��܂����i4���j�ꍇ�A�u���̐l�̌���Q��4���ł����A���Ƃ���5���̏�Q���������̂ŁA���̕��͍��������čl���܂��v�Ƃ������̂ł��B
�����ӂ̌��x�z�Ō����ƁA4����1,889���~�ł����A��������5����1,574���~�������������u315���~�v���x���z�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���̏ꍇ�A�u���d4��5���v�u������Q5��5���v�ȂǂƋL�ڂ���܂��B
�Ђ��߂���ؒf����Ă��܂��悤�Ȏ��̂ɑ������ꍇ�A���Ƃ��Ƒ��߂����������Ă��悤�����܂����u�Ђ��߂���ؒf�v�����Ƃ������ʂ͕ς��Ȃ��悤�ȋC�����܂���ˁB
��������D�ɗ����܂���B
�����ȑO����`�������Ă����������Č��ŁA�����O���ɂ�铪�W�����܁A�O�������������o���A�Ȃǂ̏d�����A�����]�@�\��Q�Ɛf�f���ꂽ������������Ⴂ�܂����B
���̕��̍����]�@�\��Q�͌�ʎ��̂ɂ�铪���O���������Ȃ̂ł����A���͎��̂ɑ����O�����Q���������ŁA�m�I��Q�A�^�����B��Q�A�Ă�A�ȂǁA��r�I�d���Ǐ���A���t���b���Ȃ���Ԃł����B
�܂�u�ɂ��v�Ƃ������Ȃ��̂ł��B���̂ɑ���������A������x���䂪���Ă�����B
���̕��̌���Q�̐\���͂Ȃ��Ȃ���������܂������A���Ƒ��Ƌ��͂��Ȃ���Ȃ�Ƃ��������ʂ���퐶���Ȃǂ̏��ނ����낦�A�\���������ʂ�
�u���d2��1���v�u������Q3��3���v
�ƂȂ�܂����B
�F�茋�ʂƂ��ẮA���Ƒ��������A�Ó����낤�ȂƔ[���ł���͈͂ł����B
���݂̏�Ԃ�2�����x�A���̑O�̏�Ԃ��܂���������3�����x�Ƃ���Ă��d���Ȃ����ȁA�Ƃ������Ƃł��B
���̌��ʂ́A�u���ɑ����������Ă���l���A���̂łЂ��������������v�ꍇ�ɔ�ׂĂ��D�ɗ����܂����B
�Ƃ���������Q�i���̌���Q�j�̏ꍇ�́A������i�����ނ��j���Ⴂ�܂��B
�����Q�̓��e���A�u�����ɑr�����A�܂��͎������̑啔���i�����镔����4����3�ȏ�j���������ĕ�ԁi�قĂj��������v���A�u3�{�ȏ�Ȃ�14��2���v�Ƃ��u5�{�ȏ�Ȃ�13��5���v�A�u7�{�ȏ�Ȃ�12��3���v�Ȃǂƌ��߂��Ă��܂��B
�r����啔���̌������m�F�ł���A���ۂɕ�Ԃ����Ă��Ȃ��Ă��F��̑ΏۂƂȂ�܂��B
�����ď�L�̉����̌����⍂���]�@�\��Q�̏ꍇ�̂悤�ɁA�����Q�̏ꍇ��������Q�Ƃ����l����������A
�u�r�����͑啔�����������Ă��ĕ�Ԃ��ꂽ����i��Ԃ͂��Ă��Ȃ��Ă��悢�j�����̑O�Ɋ��ɂ������v�ꍇ�A����͊�����Q�Ƃ���܂��B
���̏ꍇ�A��\�I�Ȋ�����Q�́u���I�ǁi�ނ����j�v�ł��B���I��4�x�iC4�j�̒i�K�i�܂�ƂĂ��Ђǂ��ނ����j�́A�������̑啔�����������Ă������A�Ƃ݂Ȃ����̂ł��B
��̓I�Ɍ����ƁA�Ђǂ��ނ�����3�{�������l�����̂ł����4�{�������ꍇ�A���v7�{�ƂȂ�
�u���d12��3���v�u������Q14��2���v�ƔF�肳��܂��B
�����ӂł�
224���~�|75���~��149���~
���F��z�ł��B
����ɂ́A�Ђǂ��ނ�����2�{�������l�����̂ł����1�{�������ꍇ�A���v3�{�Ȃ̂ŁA���d��14���ł���������Q�͔�Y���i����Q�ɒB���Ă��Ȃ��j�ł�����A�����ȁu14��2���v�ł��B
������Q���͍T������܂���B
�ނ������āA������Ǝ����̂����̂悤�ȋC�����܂��E�E�E�B
�����āA���̂Ŏ���1�{���������Ƃ͂Ƃ��Ă��C�̓łł����A�ł����ʂȂ�u����Q�i�V�v�Ȃ̂ɂ��܂��܂ނ�����2�{���������ƂŌ���Q���F�肳���̂��āA���t�͈������ǂ�����Ƃ����ȋC�����܂��H
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

���Ղ̌���Q�i�O�e�X��Ɋւ��鎩���ӂ̌���Q��������(2012.02.02)
- ���̃R�����i2010�N6���j�ɂ����Ղ̌���Q�̂��Ƃ��q�ׂĂ���܂����A2010�N5��27���̋��s�n�ٔ����Ɋ�Â��āA2011�N5��2��
�Ɏ����ԑ��Q�����ۏ�@�{�s�߂̉����ɂ��ʕ\����߂��܂����B
�O�e�X��i���Ձj�̌���Q�������A�ȉ��̂悤�ɕς���Ă���܂��B
�i���j
7��-12�@�@���q�̊O�e�ɒ������X����c������
12��-14�@�@�j�q�̊O�e�ɒ������X����c������12��-15�@�@���q�̊O�e�ɏX����c����
14��-10�@�@�j�q�̊O�e�ɏX����c������
�@�@��
�i�V�j
7��-12�@�@�O�e�ɒ������X����c������
9��-16�@�@�O�e���������x���X����c������
12��-14�@�@�O�e�ɏX����c������
�ύX�̑傫�ȖړI�͒j���̋�ʂ��Ȃ������Ƃł����A����ɔ���
�u�V����9����݂��v�A�u14�����폜�v����܂����B
�X��̒��x�ɂ��ẮA����܂ł́u�������X����c���v�Ɓu�X����c���v�ɉ����A�V���ɐ݂���ꂽ9�����u�������x�̏X����c���v�Ƃ����\�����Ȃ���Ă��܂��B
���߂Ĉȉ��ɊO�e�X��ɂ��Ă̔F����������܂��B
�u�O�e�ɒ������X����c�����́v�Ƃ́A�����Ƃ��āA���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ŁA�l�ڂɂ����x�ȏ�̂��̂������B
�@ �����ɂ����ẮA�Ă̂Ђ��i�w�̕����͊܂܂Ȃ��j�ȏ��ፍ��܂��͓��W���̂Ă̂Ђ��ȏ�̌���
�A ��ʕ��ɂ����Ă͌{����ȏ��ፍ�����10�~���ݑ�ȏ�̑g�D�זv
�B �z���ɂ����ẮA�Ă̂Ђ��ȏ��ፍ�
�u�O�e�ɑ������x�̏X����c���v�Ƃ́A�����Ƃ��āA��ʕ��̒���5�Z���`���[�g���ȏ�̐��ŁA�l�ڂɕt�����x�ȏ�̂��̂������B
�u�O�e�ɏX����c���v�Ƃ� �����Ƃ��āA���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�ŁA�l�ڂɂ����x�ȏ�̂��̂������B
�@ �����ɂ����ẮA�{����ʈȏ��ፍ����͓��W���̌{����ʈȏ�̌���
�A ��ʕ��ɂ����ẮA10�~���݈ȏ��ፍ��܂��͒���3�Z���`���[�g���ȏ�̐���
�B �z���ɂ����ẮA�{����ʈȏ��ፍ�
���̐V������́A����22�N6��10���ȍ~�ɔ����������̂ɂ��ēK�p����邱�ƂɂȂ��Ă��܂�
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�
���Ղ̌���Q�@�i2010.06.11�j
- �J�Ђł������ӂł������ł����A��Ȃǂɏ��Ղ��c�����ꍇ�A����Q���F�肳��邱�Ƃ�����܂��B
�Ⴆ�Ί�̐���̏��Ղł���A5cm�ȏ�̒���������u�O�e���������X����c���v�Ɣ��f����A3cm�ȏ�5cm�����̒����ł���A�u�O�e�ɏX����c���v�Ɣ��f����܂��B
�Ƃ��낪�J�Ђ������ӂ��A�����u�O�e���������X����c���v����Q�ł����Ă��j���ɍ�������܂��B�Ⴆ���u���q�̊O�e���������X����c���v�ꍇ��7�����F�肳��܂����A�u�j�q�̊O�e���������X����c���v�ꍇ��12���ƂȂ�܂��B
���z�Ō����ƁA�����ӂ̎x����i���x�z�j�ł�7����1,051���~�A12����224���~�ƂȂ�A�����u�O�e���������X����c���v�Ȃ̂ɒj���̈Ⴂ�ł���قǂ̍������܂��B
�u���q�̊O�e�ɏX����c���v�ꍇ��12���i������224���~�j�ŁA�u�j�q�̊O�e�ɏX����c���v�ꍇ��14���i������75���~�j�̍��ł��B
���̂��Ƃ��A�u�@�̉��̒j���������߂����@14���ɔ����Ĉጛ���v�Ƃ����������A5��27���ɋ��s�n�قŌ����n����A�����T�i�������Ɋm�肵���A�Ƃ����j���[�X���������܂����B
���̔����Ɋ�Â��ĘJ�Ђ̊���������A�ƌ��J�Ȃ����\���Ă���A���̌��ʂ͎����ӂɂ��e��������A�Ƃ������ԈႢ�Ȃ������ӂ���������邱�ƂɂȂ�͂��ł��B
�m���Ɏ����A���߂ď��Ղ̌���Q�́u�j���̈Ⴂ�v�����Ƃ��́A
�u�܂���̏��ՂŒj����������͎̂d���Ȃ������v
�Ƃ����C�����ƁA
�u�Ȃ�ƂȂ��j��������������������Ă���悤�ȋC������Ȃ��v
�Ƃ����v�����A���ꂼ�ꊴ�������̂ł����B
���̌�A�����ƌ�ʎ��̂̋Ɩ��������Ȃ��čs����ł́A�u�O�e�̏X�ɑ������Q�͒j���ō�������̂�������O�v�Ƃ������Ƃł���Ă��܂����̂ŁA�}�q���Ă����Ǝv���܂��B
����̔����ƁA��������������i���������̍s���ɂ́A�ǂ������������܂����B
�����ւ̕⏞��������̂��A�j���ւ̕⏞���オ��̂��͕�����܂��A��������ӂ��Č��Ă��������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�u���Q�ҁv�u��Q�ҁv�Ƃ́@�i2010.05.20�j
- �����ԑ��Q�����ۏ�@�i�����@�j�ł́A�P�K�������l����Q�ҁA�P�K���������������Q���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
���ɐM���@�̂Ȃ������_�ŁA�ԓ��m���o�������ɂԂ����đo���̉^�]�肪�P�K�������悤�ȏꍇ�A���̌����_�̏ɂ����܂����A�K������������S�ʓI�Ɉ����A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ�������Ǝv���܂��B
�Ⴆ�A���Ȃ��̕������Ȃ舫�����ǎ����Q�O�����炢�͈����A�Ƃ��������ŁB
�ǂ���ɂ������Ȃ�Ƃ��ߎ�������ꍇ�A�����@��͈���̐l���A��Q�҂ł�������Q�҂ł������Ƃ����ɂȂ�܂��B
�܂肱��͎����ɉߎ����傫���Ƃ��Ă��A�������P�K�����Ă����瑊��̎����ӂ�C�ӕی��ɔ�Q�҂Ƃ��Đ����ł���Ƃ������Ƃł���A���̂��ƂɎ����@�̈Ӌ`������܂��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

���ǂƌ���Q�@�i2010.03.17�j
- ��ʎ��̂Ɍ��炸�l���ЊQ�Ŕ�Ђ����ꍇ�A���Â����Ă���БO�̏�Ԃɂ͊��S�ɉ��Ȃ����Ƃ�����܂��B���̂悤�ȑ̂�_�̕s������ʓI�ɂ́u�����v�ƌĂ�ł���܂����A���Q�����̕���ł��u����Q�v�ƌĂԂ��Ƃ�����܂��B
����͎����ӕی���J�Еی����A�c��������Q�̒��x�ɉ��������������߁A�ی����̌��x�z�����߂Ă����Ƃ������x�ɂȂ��Ă��邽�߂ł��B
�����ӂ�J�Ђŏ�Q�̒��x���Ƃ��ĕ\�����A�ꗗ�\�ɂ������̂��u����Q�����\�v�ƌĂ�ł���A��Q�̏d�y�̎w�W�Ƃ���Ă��܂��B
�������Q�����̏ꍇ�ł����̘J�Ђ⎩���ӂ̋K��ɂ��Ă͂߂đ��Q�����ɔ��f������Ƃ������@������Ă���܂��̂ł��̂悤�ɌĂԂ��Ƃ������̂ł����A���ۂɂ͂��̓�i���ǂƌ���Q�j����ʂ��Ȃ��Ŏg���Ă��邱�Ƃ������Ǝv���܂��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

���c�s����i�i�Ǐ�Œ��̎��Ô�j�@�i2010.03.04�j
- ����22�N3��3���̓��o�V���ɁA���c�s�����Q�ی���Ёi�����������Q�ی��j���i�����Ƃ����L�����o�Ă��܂����B�u���c�s�ɏZ�ޕ��̌�ʎ��̂ɂ�鎡�Ô���s�����S���Ă���̂ŁA������v�Ƃ����i���ł��B
�s���ی���Ђ��i�E�E�E�H
��ʎ��̂ŃP�K�����Ď��Â�����ꍇ�A�ʋΓr���̎��̂Ȃ�J�Еی����g���܂����A����ȊO�̏ꍇ�͌��N�ی����g���Ď��Â����Ă��A���N�ی����g�킸�Ɂu���R�f�Áv�Ŏ��Â����Ă��A�ǂ���ł����܂�Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B����P�K�����ꂽ���c�s�̕��́A�������N�ی����g���Ă����悤�ł��B
�������N�ی����g���ꍇ�A�ʏ�u�����̃P�K�v�̎��Âł���A���Ô��3���͎��ȕ��S�����āA�c���7���͎s�撬�������S���܂���ˁB���̂��߂ɍ������N�ی������Ă���킯�ł��B
�ł�����ʎ��̂ł̃P�K�̎��Âɍ������N�ی����g�����ꍇ�A���ȕ��S��3���Ɋւ��Ă͉��Q�ҁi���ۂɂ͉��Q�ґ��̑��Q�ی���Ёj�������܂����A�c���7�����A�s�����Q�ҁi���̕ی���Ёj�ɐ������āA������Ă��܂��B
����́A��ʎ��̂́u�����̃P�K�v�ł͂Ȃ��A�u���Q�҂ɕ��킳�ꂽ�P�K�v�Ȃ̂ŁA�x�����ӔC�͉��Q�҂ɂ����A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��邩��ł��B
��������ʎ��̔����̗���Ƃ��ẮA�P�K���Ǐ�Œ肵�������Q�����̔F����A�Ǐ�Œ���ȍ~�̔��������܂Ƃ߂ĕ����A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��B
����̔�Q�҂̕��́A�u�܂��ɂ݂��c���Ă���̂Ŏ��Â𑱂������v�Ǝ咣���A���������ł��邠���������ۂ́u�������Ȃ��͏Ǐ�Œ肵�Ă���̂ŁA����Q�̔F����ĉ������B�]���ďǏ�Œ�ȍ~�̎��Ô�͕����܂���v�Ǝ咣���A���݂��̎咣���Η����Ă����悤�ł��B
�ł������Â͂��̂܂ܑ�����ꂽ�̂ŁA���Ô��7���S�������Ă��钬�c�s����̐����������������ۂ͋��ۂ��Ă����̂ŁA���c�s����i�Ƃ������d��i�ɏo���Ƃ������Ƃł��B
���̍l���Ƃ��ẮA�����������ۂ̎��Ô�x�������ۂ������Ȃ̂������Ȃ̂��Ƃ������Ƃ�����܂����A�����炭���_�Ƃ��Ắu��Q�҂����̎��_�ŏǏ�Œ肵���̂��A���邢�͂܂����Ă��Ȃ��̂��v�Ƃ������ƂɂȂ�悤�Ɏv���܂��B
���̏�ŁA���݂͉��Q�҂͔�Q�҂̏Ǐ�Œ�ȍ~�̎��Ô�͕���Ȃ��Ƃ������Ƃ���ʓI�ł����A���̕����ɂ��Ă͂ǂ̂悤�Ȕ��f�������̂��i�Ǐ�Œ�ȍ~�̎��Ô���ƂȂ�̂��ǂ����j�ɂ��āA���ڂ��Ă���܂��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

��ʎ��̓����҂ɕs�R�ȓd�b�H�@�i2009.07.24�j
- ����d�b�ł����k�������������ł��B
���k�҂̕��i�`����Ƃ��܂��j�͔�Q�҂ŁA�����̎ԁi�l�֎ԁj���^�]���Ă��Č����_��ʉ߂��悤�Ƃ��Ă�����A�ꎞ��~�����Č����_�ɐi�����Ă����^�N�V�[�ƏՓ˂��܂����B
�Ԃ͑o�����\���A�`����ɂ̓P�K�͂Ȃ��悤�Ɍ��������ǎ��̓��͎ɂނ̂ŁA�O�̂��ߕa�@�ɍs���Đf�Ă��炢�܂����B�ł�����l�g���̂ł��B���̍ۂ̎��̏������A�x�@���Ă�ł�����Ƃ����Ȃ��܂����B
�Ƃ��낪�`����́A���̌�̑��������̘A�����e�⌾����s�R�Ɏv���A�u�����������Ƃ��Ă���̂ł����H�v�Ǝ��̎������֓d�b�ő��k�����Ă��܂����B�`�������ɂ́E�E�E
������i�^�N�V�[��Ёj�̕ی���Ђ��Ɩ����j������`����̌g�тɓd�b���������Ă��āA���k�̘b�������Ȃ肵�n�߂܂����B���̎��͂��܂�b�����Ă����Ȃ��������̂ň�U�d�b���A���̌�`����A�g�тɎc���Ă����ԍ��ɐ܂�Ԃ��܂����i������g�тł����j�B���̎��d�b�ɏo�������
�u�͂��B�����i�l���j�ł��v�Ɩ�����������Ȃ̂ŁA�`�����
�u����A�ی�������Ȃ���ł����H�v�ƕ����ƁA
�u���A�����ł��B�ی����ł��v
�ƁA���Ƃ��s�R�B�`�����
�u�z���g�ɕی�������ł����H���ی��ł����H�v�ƕ�����
�u�`���t�ی��ł��v
�Ɩ�����������ł��B���̑��ɂ�
�u����̕������̂Łv�ƌ����̂�
�u�����A���̂��ƕa�@�ɍs���Đl�g���̂ɂȂ��Ă��܂��v
�Ƃ`�������Ɓu����A�����ł����v�ȂǁA���Ԃ�c�����Ă��Ȃ��l�q�B
���̂܂܂`���b���ƁA���肪�������e��
�u�����ɂ��Ă��������A�Ԏӗ�2,000�~�Ŏ��k���ė~�����v
�Ƃ̂��Ƃ����������ł��B
�`����͕s�R�Ɏv���A���̏�͈�U�d�b���A�^�N�V�[��Ђɖ₢���킹�܂����B
�`���^�N�V�[��ЂɁA���̂悤�ȓd�b�����������A�{�����H�������̓����Ă���ی���Ђ͂`���t���H�Ɩ₢���킹���Ƃ���A�^�N�V�[��Ђ���̕Ԏ���
�u�����������Ă��鎩���ԕی��͕x���Ђł��B�������`���t�ƊW������̂��A�`���t�ɈϔC���邱�Ƃ�����̂��Ȃǂ͕�����Ȃ��v
�Ƃ̂��ƁB�����ł`����͕x���Ђɓd�b���ĕ����Ă݂�ƁA
�u�����͂���ȓd�b�͂��Ă��Ȃ����A���̑��Q�ی���ЂɎ��k�����ϔC���邱�ƂȂǂ͂Ȃ��v
�Ƃ̕Ԏ��ł����B����ᓖ����O���B
���̎��_�ł`����͉����Ȃ������炸�A���̎������֓d�b���Ă��܂����B
������L�̓��e��d�b�ł`����Ɉ�ʂ蕷�������ƁA����͂��̂��Ƃ��ƕ����܂�����A
�u�d�b�������͍̂����B���̂��������̂͂��ƂƂ��v
�Ƃ̂��Ƃł����B
�ŏ��A���͂`����̘b���Ă���Ƃ��A�܂�Ԃ��d�b����������l���ŏo�āA�������x���Ђ̂͂��Ȃ̂ɂ`���t�ƌ����Ă��܂����̂́A�㗝�X�̐l�������̑��Q�ی���Ђ̕ی�����舵���Ă��ĊԈႦ��������̂��ȁA�Ȃ�Ďv���Ȃ��畷���Ă��܂������A�ڂ��������Ă݂�ƁA���Ƃ������ł����̂̂Q����Ɏ��k�̘b�i�����������Ȃ̂ɈԎӗ��̘b�I�j���o��̂͂��܂�ɂ��s���R�����A�l�g���̂Ȃ̂ɕ������̂��Ǝv���Ă��邵�A�m���ɕςȂ��Ƃ��炯�B���͂`�����
�u����͂����炭�U�荞�ߍ��\�܂����A�܂��͐U�荞�ߍ��\���̂��̂�����A�C�����ĉ������B�v
�Ƃ��`�����܂����B
�����
�u������x�d�b��������A����ɂ͐�ɐV��������^�����A�b�����܂����đ��߂ɓd�b���A�����Ɍx�@�ɘA�����Ă��������B���̓d�b�ԍ����x�@�ɋ����Ă��������v
�Ɛ������܂����B
���̎��ɂ`���S�z���Ă����̂́A�����̏Z����g�єԍ���m���Ă���̂ŁA�x�@�ɒʕ����ƂɎd�Ԃ��Ȃǂ�����Ȃ����A�Ƃ������Ƃł����B����
�u���̂悤�ȐS�z���x�@�ɑ��k���Ă��������B�x�@������Ă���܂������ۂɂ���Q��Ȃǂ͂قƂ�ǂȂ������ł���v�Ƃ��`�����܂����B
���̌�͘A�����Ȃ��悤�ł����A����x���̏o�����������܂��ƁA
�E �����炭���\�t�͎��̌����ڌ����āA�Ԃ̃i���o�[����`����̌l���Ȃǂ���肵���̂ł͂Ȃ���
�E ���̂̏����āA���݂��P�K�������l�q���Ȃ������̂ŕ������Ǝv�����̂ł͂Ȃ���
�E ���\�t�̘b�́A�`����Ɂu�����̈Ԏӗ��Ƃ���2,000�~�����v�Ƃ������̂ł����B���̂̏���ߎ��͈��|�I�Ƀ^�N�V�[�ɂ���Ɣ��f�������炾�Ǝv���܂����A���̓W�J���獼�\�𐬗������邽�߂ɂ͂ǂ�����̂��H�@�����炭�`����̑㗝�l�ȂǂƏ̂��ă^�N�V�[��Ђɔ������𐿋�����̂ł͂Ȃ����H�ƍl���܂����B�����o�����鑊��͑��ɂ��Ȃ��ł���ˁB
�E ���肪���߂Ď��̂ɑ�������ʂ̕��Ȃ�܂������A�^�N�V�[��Б���Ɏ��k��������Ĕ������킹�邱�Ƃ��ł���悤�ɂ͎v���܂���̂ŁA���̂܂ܐi�ꍇ�͂ǂ��Ȃ��Ă����̂��A�Ȃǂ�������Ƌ�������Ƃ���ł��B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�ނ��ł��Ō���Q�������Ƃ�ɂ́@�i2009.06.22�j
- �ނ��ł��i��ŔP���A�����Ȃǁj�̏ꍇ�A�����g�Q����l�q�h�Ȃǂ̉摜�ňُ킪�m�F�ł��Ȃ����Ƃ������ł�����A����Q�������l�����邽�߂ɂ́A����Q�f�f���̏����������ɏd�v�ł��B
�����Ɍ������ʂ����m�ɋL�ڂ���Ă��邩�A�����Ɏ��o�Ǐ�̓I�ɋL�ڂ���Ă��邩���m�F���A��������K�v������܂��B
��̓I�ɂ́A�Ⴆ���_�o���Ǐ�U���e�X�g�i�X�p�[�����O�e�X�g��W���N�\���e�X�g�j�Ő_�o���̏�Q���m�F���A�k��ؗ̓e�X�g���F���˂Ȃǂ����Đ_�o��Q���ʂ�������x���肵�āA�l�q�h�Ȃǂ̉摜�ňُ폊�����m�F�ł���̂ł���Ώ�L�̌������ʂ������I�ɐ����ł���̂ŁA�����S�Ă̂��Ƃ������̂���؋��Ƃ��ēY�t�܂��͋L�ڂ���̂ł��B
�ł����炲�����Ō���Q�f�f���̓��e���������A�ꍇ�ɂ���Ă͌���Q�f�f���̋L�ړ��e�ɂ��Ĉ�t�ɑ��k�����Ă��炤�Ƃ��A���ґ������t�ɕK�v�Ȍ������ڂ̗v�]���o���A�Ƃ������炢�̏��������Ă������Ƃ��]�܂����ł��B
�����l���̐��ۂ͐\���̑O�ɂǂꂭ�炢�������ł��Ă��邩�ɂ������Ă���A�Ƃ����Ă����������ł͂���܂���B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

��Q�Ґ����Ō���Q�������@�i2009.06.09�j
- ��ʎ��̂̔�Q�҂̕��́A�P�K�����Ă��܂��B�d���A�y���Ȃǒ��x�̈Ⴂ�͂���܂����A�݂Ȃ���P�K�̂��߂ɓ������Ƃ��ł����Ɏ���������A�ꍇ�ɂ���Ă͎��Ô�A��ʔ�Ȃǂ̎�����ꎞ���ȕ��S��������ȂǁA��ύ����Ă������������������Ⴂ�܂��B
�ȑO�A�Ⴂ�����̕��Ɂu����Q�����͂P�P�����������A���㔅���͂ǂ��Ȃ�̂�������Ȃ��̂ŗ͂�݂��ė~�����v�Ƃ������˗����������������Ƃ�����܂���
����Q�̓��e�͐Ғ��̕ό`��Q�ŁA�P�P���Ȃ̂Ō��\�d�����ǂł��B��Q�҂͕ό`��Q�̑��ɐg�̂ɒɂ݂��c���Ă���̂ő��������������̂ɁA���葤�C�ӕی���Ђ̒S���҂ɔ����z�̂��Ƃ��Ă��̂�肭���B���Ԃ���߂��ăC���C����������������悤�ł��B
���͈˗����āA�܂����O�F��Ō��܂��Ă������Q�����ɂ��āA�����ӕی�����o�锅�������Q�Ґ����Ő�ɉ�����邱�Ƃɂ��܂����B
�P�P���Ŏ����ӕی�����x������̂͂R�R�P���~�ł��B���̌�A���葤�C�ӕی���Ђ̒S���҂͔�Q�Җ{�l����̗v�]����ɉ����Ȃ��l�q�ł����̂ŁA��ʎ��̕��������Z���^�[�Ɏ��k������\�����݁A��S���������Ĕ�r�I�����ł�����e�ŁA���k���邱�Ƃ��ł��܂���
�ŏ��Ɏ�����Q�҂̕��ɐ����������Ƃ��́A��ʎ��̕��������Z���^�[�Ɏ��k������\������ł��R�`�U�����͂�����A�Ƃ������ƂłȂ��Ȃ����f�����ɂ����l�q�ł������A��Q�Ґ������邱�Ƃɂ�肻�̑O�ɂR�R�P���~���m�ۂł����Ƃ������Ƃň��S�����A�Ë����邱�ƂȂ��S���������Ď������l�����邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ�����܂����B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�^�]��͏�q�̐g�̂̈��S���]���ɂ��Ă܂ŋ}�u���[�L��������K�v���͂Ȃ��@�i2009.06.04�j
-
�����n��H20/11/17�̔����ł��B
�^�N�V�[�ɏ�Ԓ��̂S�Q�Ώ������}�ɍ��܂��w���������Ƃɂ���āA�^�N�V�[�͂قڋ}�u���[�L�B���̂����ŏ����͌z�ŔP�����A�����]�@�\��Q���c�����Ƃ����i���ł��B
��Q�҂̂��̏����i�����j�ɑ��āA�퍐�ł���^�N�V�[��Ђ́u�����͓ˑR�^�]��ɍ��܂��w�������̂�����A�^�N�V�[���̃V�[�g�x���g��肷��Ȃǂ̈��S�{�݂𗘗p�����葫�����肵�āA�^�N�V�[�̋}���i�A�}��ԂȂǂɂ��h�ꂩ�玩���̊�Q��h�~����`��������̂ɂ����ӂ�������A�ߎ����E���ׂ��ł���v�Ǝ咣���������ł��B
�u�}�ɋȂ���Ƃ��Ȃ����������̂�����A�}�u���[�L�����邱�Ƃ͗\�z���Ȃ����v�Ƃ��������Ƃł��B
�ł��ٔ����̔��f�́A�u��q���ˑR���܂��w�������Ƃ��Ă��A��U�ʂ�߂��Ă�������Ԃ��������A��q�̐g�̂̈��S���]���ɂ��Ă܂Ńu���[�L��������K�v���͂Ȃ��I�v�Ƃ̂��Ƃł����B
����Ⴛ���ł��ˁB�����Ă݂�Γ�����O�A�펯�I�Șb�ł��B
�ł��ȑO���̃N���C�A���g���������̘b�ł����A���̕��͗F�l�ɗU��ꂽ�̂ł��₢�₻�̗F�l���^�]����Ԃ̏���Ȃɏ���āA�Ă̒肻�̎Ԃ̎������̂Ɋ������܂�܂����B
�ی�������u�^�]��͔n�͂������������Ă��Ȃ�������Ȃɏ悹������A�X�s�[�h���o���댯�����������Ƃ͗\�z�ł����ł���B������ߎ����E���Č��z���܂��B�v�ƌ���ꂽ������������Ⴂ�܂����B
�Ȃ���̔���̃^�N�V�[��Јȏ�̕ςȗ����ł����A�펯�I�ɍl����܂������������Șb�ł���ˁB�펯�͂���̎咣�ł��B
�������Ȍ��z�͔F�߂���͂�����܂���B
�@�@�@�@���̃y�[�W�̐擪�ց�

�i�r�Q�[�V����
-
��ʎ��̂ɑ����Ă��܂��������Q�҂ɂȂ�����
- ��Q�҂ɂȂ�����
- ���̌���ł��Ă͂����Ȃ�
- �������������Ƃ�
-
�����ӕی��ɂ��������ӂ̂����݂ƈԎӗ��v�Z
- ���Q�Ґ����A��Q�Ґ���
- �����Ӑ����̕K�v����
- ��������x�����܂�
�C�ӕی��ɂ���
- �C�ӕی��̎��
- �����ӕی��Ƃ̈Ⴂ
-
�ߎ����E�ɂ����ߎ����E�Ƃ�
- �ߎ������̔��f�
- �ߎ������̏C���v�f
���Q�����z�̎Z��
- �����ł���l�Ɛ����͈�
- ���Q���̂̐ϋɑ��Q
- �x�Ƒ��Q
- ���Q�Ԏӗ��i���ʉ@�Ԏӗ��j
- ����Q�ɂ��편���v
- ���LjԎӗ�
- ����Q�����F�肷��̒N�H
- �ނ��ł��ǂ̏ꍇ
- ���S���̂̑��Q����
- �����ɂ���
���I�E���I���t�Ƒ��v���E
- ���t�̎�|�Ɠ��e
- ���v���E���āH
- �ߎ����E�Ƒ��v���E�̐��
- ��Q�N���i�J�Ёj�̑��v���E
���k���ɂ���
- ���Q�҂�3�̐ӔC
- ���k���ƈԎӗ��̈Ⴂ
- ���k���͂��n�߂�H
- ���k���e�Ǝ��k��
����͂��Вm���Ă�������
- ���������Z���^�[�̊���
- ���{�ۏ᎖�ƂƂ�
- �����Əڂ���
- ��ʎ���Q&A
- �T�C�g�}�b�v
- �n�V���g�̃R����
- ���������̃T�|�[�g
- �ߋ��ɂ������������k���[��
copyright © ���{�s�����m������ all rights reserved.



