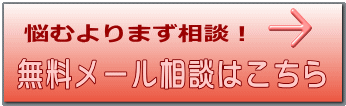造影検査(関節、脊髄、血管)
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
造影検査
造影検査には以下のようなものがあります。
1.関節造影検査
造影検査とは、造影剤と呼ばれる薬を体内に投与して、X線やMRIなどの画像検査を行う検査です。臓器や血管の状態を調べるために行います。
関節疾患に対しては、補助的画像検査として古くから行われてきましたが、最近は関節今日の進歩とMRI検査の発達によって減少傾向にあります。
関節の部位としては膝、股、肘、足、手関節などに対して行われます。
関節包、軟骨、靱帯などの関節構成体の状態や関節面の不整、適合性などを調べることができますが、造影剤を用いるため薬剤アレルギーが起こる可能性もあります。
2.脊髄造影検査
脊髄造影検査は、様々な原因による脊柱管内の神経組織の圧迫の位置や程度を評価する検査です。現在の脊椎脊髄病疾患の病態把握や今後の治療方針を決定するために必要な検査です。MRIよりも骨病変の描出に優れています。
背中に麻酔(痛み止め)をし、腰椎に針を刺して、くも膜下腔に造影剤を注入してX線透視と撮影を行います。造影剤は非イオン性の水様性ヨード造影剤などを用い、血管造影剤は使えません。
前後屈位や側屈対で撮影を行うことで、姿勢による変化も評価できることが利点で、また体内金属がある場合は閉所恐怖症などでMRI検査ができない場合にも有用です。
X線による脊髄造影後にCTによる脊髄造影を行うことで、骨性因子、軟部組織、神経組織の横断面の評価をすることができます。
3.血管造影検査
血管造影検査(アンギオグラフィ)とは、カテーテルを脚の付け根や肘の血管から挿入して造影剤を注入し、X線撮影を行うことで血管の状態を調べる検査です。
カテーテルを目的部位の近くまで進めることにより、詳細な血管像を得ることが可能となります。
動脈撮影は、外傷による動脈損傷の証明や、腫瘍の広がりと悪性度の診断などに有用です。
静脈造影では、静脈瘤の拡張蛇行や静脈閉塞部位の欠損などが確認できます。
4.造影CT、造影MRI
造影CT検査は、造影剤を静脈注射して撮影するCT検査で、腫瘍や血管などの病変をより詳細に診断するために用いられます。
この検査では、マルチスライス技術の進歩により、動脈形態の観察が可能になっています。
肺血栓塞栓症(はいけっせんそくせんしょう)に確定診断に有用です。中枢側肺動脈の血栓だけでなく、葉動脈や区域枝動脈レベルの血栓も抽出できます。それと同時に下肢や骨盤などの静脈血栓も探すことができます。
造影MRIは、MRI検査で造影剤を使用することで、血管や臓器の血流状態や病気の性質を詳しく診断する検査です。
造影剤を使用することで、腫瘍や炎症などではコントラスト(信号)が強調されます。
| 関連項目 |
- 後遺障害の定義と系列
- 等級認定のルール
(併合、加重) -
診断書、レセプトのポイント診断書の見方
- レセプトの見方
- 後遺障害診断書のポイント
- 関節可動域について
-
部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- ↳下肢の外傷・種類と
後遺障害 - もっと詳しく
当事務所について
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去の相談メール