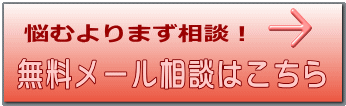一般画像検査(X線、CR、MRI、エコー)
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所(交通事故サポートセンター)
一般画像検査
一般画像検査には以下のようなものがあります。
1.単純X線検査
骨や関節疾患の画像検査でまず行われるのが単純X線検査です。X線を使って靭帯を撮影することによって骨折、骨腫瘍、骨髄炎、関節炎など、骨病変の多くはその異常が捉えられます。
撮影は2方向以上で撮ることが基本ですが、頚椎は7方向(前後、側面前屈・中間・後屈位、両斜位)、腰椎は6方向(前後、側面前屈・中間・後屈位、両斜位)が一般的です。
主な部位別計測法は以下のとおりです。
●脊椎
頸椎では椎間孔を、腰椎では分離症などをみるために両斜位も撮影することが望ましいです。また、すべり症などの不安定性を評価するためには前後屈も撮影します。
●肩関節
正面からと斜め前からに加え、上肢の挙上が困難な場合は度は上腕骨頭と関節窩の評価のためにスカプラY(関節窩に対して垂直方向から。体の背面から斜めに撮るような感じ)の撮影をします。
●肘関節
正面、側面の二方向に加え、橈骨頭や尺骨鉤状突起の評価のためには斜位像が有効です。
●手関節
正面と側面の二方向に加え、必要に応じて尺屈位、背屈位、グリップ位などを追加します。
●股関節
正面、側面の二方向が基本で、正面はなるべく両側を撮影して左右を比較します。側面は股関節を開排位で撮影するのが一般的ですが、大腿骨頚部骨折などで動きが制限されている場合は大腿骨頚部軸射撮影(股関節を斜めから撮影して股関節頚部を詳しく見る方法)を行います。
●膝関節
正面、側面、軸射像の三方向撮影が基本です。特に膝蓋大腿関節の様子を見るためには軸射像は必須です。
●足関節
正面と側面の二方向が基本ですが、これで診断が難しい場合には斜位像を追加します。
2.CT検査
CTはコンピュータ断層撮影のことで、X線を使って体内の断面像を撮影します。X線透過性をコンピュータ演算で算出するため、単純X線写真より濃度分解能に優れています。
マルチスライスCTでは高精細容積画像データが得られますので、三次元画像表示が可能となります。特に脊椎、肩関節、骨盤、足関節などの複雑な部位に発生した病変には単純X線やMRIよりも有用です。
3.MRI検査
MRI(磁気共鳴画像)検査は、強い磁石と電波を使って磁場を発生させて、身体の内部を画像化する検査です。
がんなどの病気の部分と正常な組織の違いを画像上のコントラストで区別しやすく、また縦、横、ななめなど、さまざまな方向の断面を画像にすることができます。
X線を使わないので、被ばくの心配もありませんが、MRI検査で用いる磁石や電波は金属などの影響を受けるため、体の内外に金属類がないかなど事前の丁寧な確認が必要です。
MRI検査では、関節内骨折、感染症、変性疾患などの場合の軟部組織の確認をします。
関節内骨折では、関節内外の関節支持組織の状態を把握する目的で撮影します。
感染症では、骨髄炎、関節炎、などの診断に有用です。
変性疾患では、脊柱管の狭窄度や椎間板の変性、椎間板ヘルニアなどの確認ができます。
MRIの画像では、白くて明るく見える部分を「高信号」、黒くて暗く見える部分を「低信号」といいます。
T1強調画像とT2強調画像があり、脂肪はT1強調像では明るく(高信号)写り、T2強調像では比較的暗く(比較的低信号)見えます。
水などの液体はT1強調像では比較的暗く、T2強調像では明るく見えます。
T1強調像は、正常軟部組織の解剖学的構造が分かりやすいです。T2強調像は,水が白く、出血が黒く見えるので、急性期の病変が分かりやすいです。
4.エコー検査
超音波(エコー)検査は、超音波を発して体内の状態を画像化して確認する検査です。
他の画像検査と比べて体に対する侵襲が少なく、リアルタイムに画像が得られ、動かしながらでも観察できます。
また装置を移動させることができるので、ベッドサイドでの検査も容易にできます。
整形外科領域においては、関節や四肢の痛み、しびれ、関節可動域制限や筋力低下といった機能障害を生じるすべての疾患がこの検査の対象となります。
| 関連項目
|
- 後遺障害の定義と系列
- 等級認定のルール
(併合、加重) -
診断書、レセプトのポイント診断書の見方
- レセプトの見方
- 後遺障害診断書のポイント
- 関節可動域について
-
部位別の障害等級認定基準部位別障害等級一覧表
- 眼の障害
- 耳の障害
- 鼻の障害
- ↳下肢の外傷・種類と
後遺障害 - もっと詳しく
当事務所について
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去の相談メール