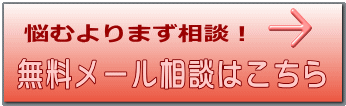慰謝料は傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料、近親者の慰謝料がある
TEL.03-5393-5133
〒177-0042 東京都練馬区下石神井1-8-27-305
橋本行政書士事務所
慰謝料にはどのようなものがある?(慰謝料の種類)
Q.慰謝料を調べていたら、○○慰謝料というものがいくつかあるようです。どのようなものがあるのですか?
A.交通事故に遭って怪我をした被害者は色々な損害を被りますが、治療費や休業損害と違って慰謝料は少しわかりにくい部分です。
慰謝料は精神的な損害と言われますが、どのような種類があり、どのように金額が決まってくるのでしょうか。
慰謝料の種類は?

慰謝料は、細かく考えると、以下の4種類あります。
・傷害慰謝料
・後遺症慰謝料
・死亡本人の慰謝料
・近親者の慰謝料
1.傷害慰謝料
 これは交通事故で怪我をしたことに対する慰謝料です。
これは交通事故で怪我をしたことに対する慰謝料です。
どの慰謝料も精神的、肉体的な苦痛に対する損害なので金額にするのは難しいのですが、傷害慰謝料は「治療をしていた期間」や「実際に入通院した日数」に基づいて計算されます。従って傷害慰謝料のことを入通院慰謝料などと言うこともあります。
単純に考えれば、治療を継続している期間が長くなればなるほど、入通院の日数が多ければ多いほど、傷害慰謝料は増えていくことになります。
→ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法は?
2.後遺症慰謝料
これは、事故による怪我について一定の期間治療をしても治りきらずに後遺症となり、「後遺障害等級」が認定された場合に支払われる慰謝料です。
後遺障害等級に応じてだいたい金額が決まっておりますが、同じ等級でも支払い側(主に保険会社)が考える後遺症慰謝料と、被害者側が考える裁判基準での後遺症慰謝料には差があります。
→ 後遺症慰謝料の考え方や金額の目安は?
3.死亡本人の慰謝料
交通事故で死亡した本人に対しても、死亡の慰謝料が支払われます。
以前は、死亡してしまった人は精神的や肉体的な苦痛は感じないだろう、というような考えから、死者の慰謝料は不要だとされた時代がありました。
現在では死亡した被害者に対する慰謝料も、傷害慰謝料や後遺症慰謝料とは別に支払われます。実際には被害者本人は死亡していますので、死亡した被害者自身の慰謝料を受け取るのは被害者の相続人ということになります。
金額は、被害者本人が家庭内で主に収入を得ていた「一家の支柱」なのか「専業主婦」なのか、子供など無職の人だったのか、などによって変わってきます。
→ 死亡事故の損害賠償は?
4.近親者の慰謝料
死亡事故だった場合は、加害者から「直接の被害者本人以外」である、被害者の近親者に対する慰謝料の賠償義務が、民法711条で決められています。
直接の被害者以外の人の損害を賠償することは異例なので忘れがちなのですが、条文に明記されていますので、忘れずに請求しなければなりません。
近親者とは、民法711条では被害者の「父母」「配偶者」及び「子」となっていますが、裁判ではきょうだいの慰謝料が認められることもあります。
→ 損害賠償請求の範囲や請求できる人は?
| 関連項目 |
-
交通事故に遭ってしまったら加害者になった時
- 被害者になった時
- 事故現場でしてはいけない
- 実況見分調書とは
-
自賠責保険について自賠責のしくみと慰謝料計算
- 加害者請求、被害者請求
- 自賠責請求の必要書類
- 請求から支払いまで自賠責保険徹底研究
任意保険について
- 任意保険の種類
- 自賠責保険との違い
-
過失相殺について過失相殺とは
- 過失割合の判断基準
- 過失割合の修正要素
損害賠償額の算定
- 請求できる人と請求範囲
- 傷害事故の積極損害
- 休業損害
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害による逸失利益
- 後遺症慰謝料
- 後遺障害等級認定するの誰?
- むち打ち症の賠償金
- むち打ちで後遺障害をとる
- むち打ちQ&A
- 死亡事故の損害賠償
- 時効について
公的・私的給付と損益相殺
- 給付の趣旨と内容
- 損益相殺って?
- 過失相殺と損益相殺の先後
- 障害年金(労災)の損益相殺
示談交渉について
- 加害者の3つの責任
- 示談金と慰謝料の違い
- 示談交渉はいつ始める?
- 示談内容と示談書
これはぜひ知っておきたい
- 紛争処理センターの勧め
- 政府保障事業とは
- もっと詳しく
- 交通事故Q&A
- サイトマップ
- ハシモトのコラム
- 当事務所のサポート
- 過去にいただいた相談メール